

この記事は、夫婦それぞれのNISAを合算設計して、月1万円から実務に落とし込むためのガイドです。
個人口座のルール、贈与税の注意、名義一致の実務、枠再利用(簿価)のポイントまで、迷わない手順を1本化します。
基礎は👉 薬剤師のNISA商品ガイド、配分は👉 リスク許容度別テンプレ をどうぞ。
\まずは夫婦それぞれのNISA口座を準備/
最初に決める「前提ルール」



個人口座・名義の原則
- NISAは一人一口座の個人口座です。
- クレカ積立・口座引落は原則証券口座と同一名義が必要です(各社規定に従う)。
※本文の「夫婦合算で設計」は家計管理上の考え方であり、実際の売買・保有は各人の口座で行います。
資金の出所と贈与の注意
- 片方がもう一方の拠出を肩代わりする場合、年間110万円超の資金移動は贈与税の対象となる可能性があります。
- 家計の共有口座から拠出する、入出金履歴を残すなど、資金の出所を整理しましょう。
※口座名義と資金の出所が一致していると実務上スムーズです。
※税制・取扱いは将来変更の可能性があるため、最新情報は各社・公的資料をご確認ください。
新NISAの要点(再確認)
- 非課税で保有期間は無期限です。
- 売却枠は翌年以降に簿価ベースで再利用できます(評価額ではありません)。
- 海外ETFの配当は現地源泉税が残ります(日本側は非課税)。
詳しくは👉 売却枠の再利用のコツ
役割分担の型(コア・サテライトで崩れにくく)



分担の例(月合計2万円のケース)
| 口座 | 役割 | 配分例 | 狙い |
|---|---|---|---|
| Aさん | コア | 全世界株 100%(月1万円) | 家計の土台を安定化 |
| Bさん | コア+サテライト | 全世界株 70%+S&P500 30%(月1万円) | 成長アクセントを付与 |
※スマホでは表が画面幅を超えます。横にスワイプしてご覧ください。
配分テンプレは👉 リスク許容度別テンプレ を参考に。
入金の設計(クレカ積立/口座引落)



実務のポイント
- クレカ積立はポイント還元を得つつ自動化できるのが利点です。
- 口座引落は家計口座と近く、資金繰りの見通しが立てやすい利点があります。
※クレカ・引落は原則証券口座と同一名義が前提です。
※上限・締切・名義要件は変更される場合があります。最新仕様は各社公式でご確認ください。
設定ガイド👉 SBIの自動積立設定
年次メンテと再配分(±5%目安)



チェック手順
- 各口座の評価額と配分をスプレッドシートに集約します。
- 目標配分からの乖離が±5%を超えたら、翌月の積立やスポット買付で近づけます。
- 暴落中の売却によるリバランスは原則避け、取り崩しは必要額のみで行います。
年次点検は👉 NISA年次メンテのチェックリスト を参照。
\分担が決まったら積立設定へ/
ケース別シナリオ(育休・住宅・教育)



よくある3パターン
- 育休期:一時的に積立額を下げ、再開時に元へ戻します。
- 住宅頭金:半年〜1年前から分割で現金化し、価格ブレを平準化します。
- 教育費:年数回の定率・定額取り崩しで家計へ取り込みます。
暴落時の行動は👉 暴落プレイブック(ルール)
Q&A(よくある疑問)
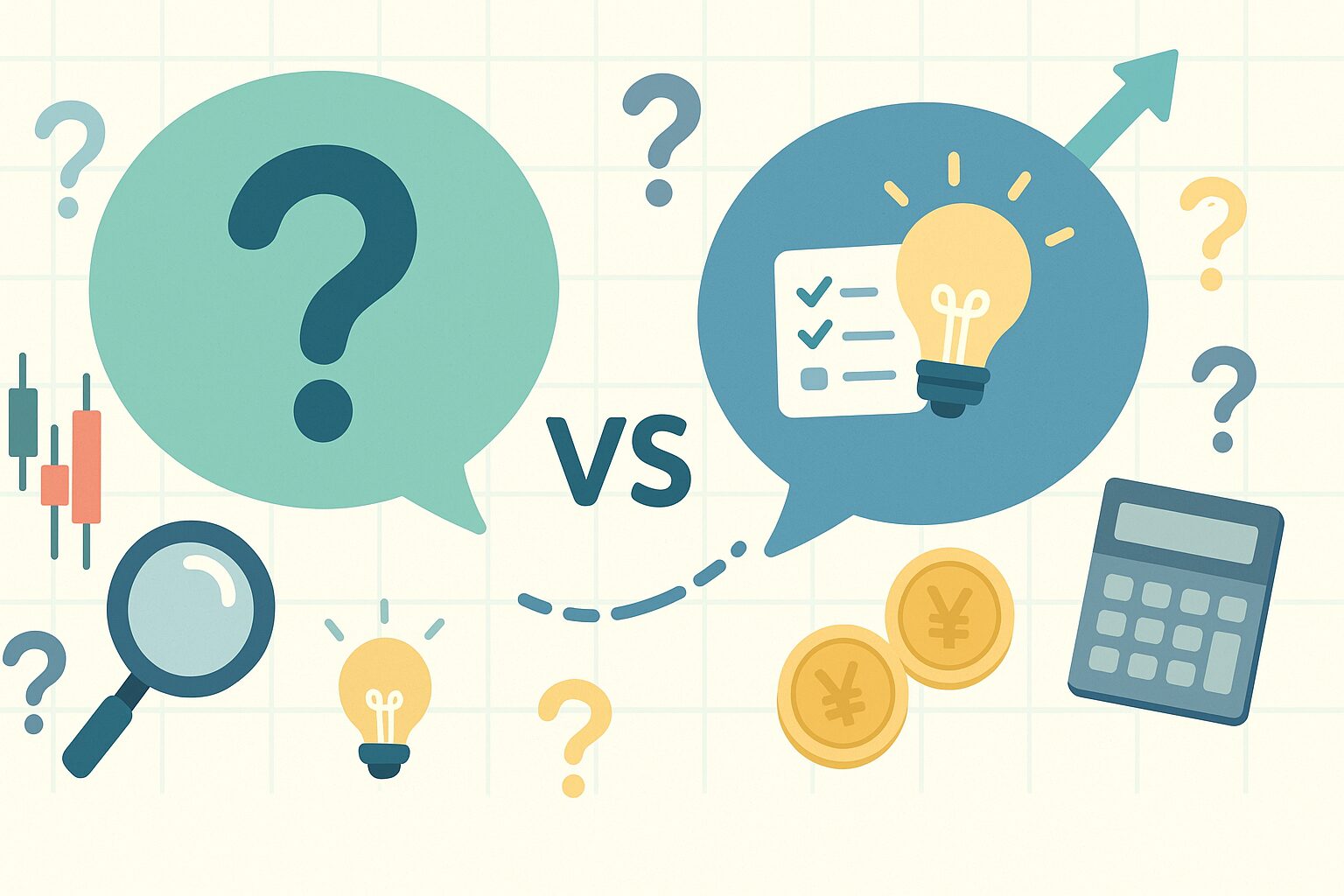
Q1. 片方だけNISAをやっても効果はありますか。
あります。
一人分でも非課税の効果は大きく、もう一方は時期を見て開始すればOKです。
Q2. 売却枠の再利用はいつできますか。
翌年以降です。
取得価額(簿価)ベースで枠が戻る点に注意してください。
Q3. 生活防衛資金はいくら確保すべきですか。
目安は3〜6か月分です。
詳しくは👉 生活防衛資金の目安と積み方
まとめ

ポイント
- NISAは個人口座。設計は合算、売買は各人で。
- クレカ積立・口座引落は原則名義一致。資金の出所は記録を残す。
- 売却枠は翌年以降に簿価ベースで再利用。海外ETF配当は現地税が残る。
- 年次メンテで±5%目安に配分を戻す。暴落時はルールで動く。


\夫婦それぞれで積立を設定/
👉 次のステップ:薬剤師のクレカ積立 vs 口座引落
👉 併せて読みたい:
