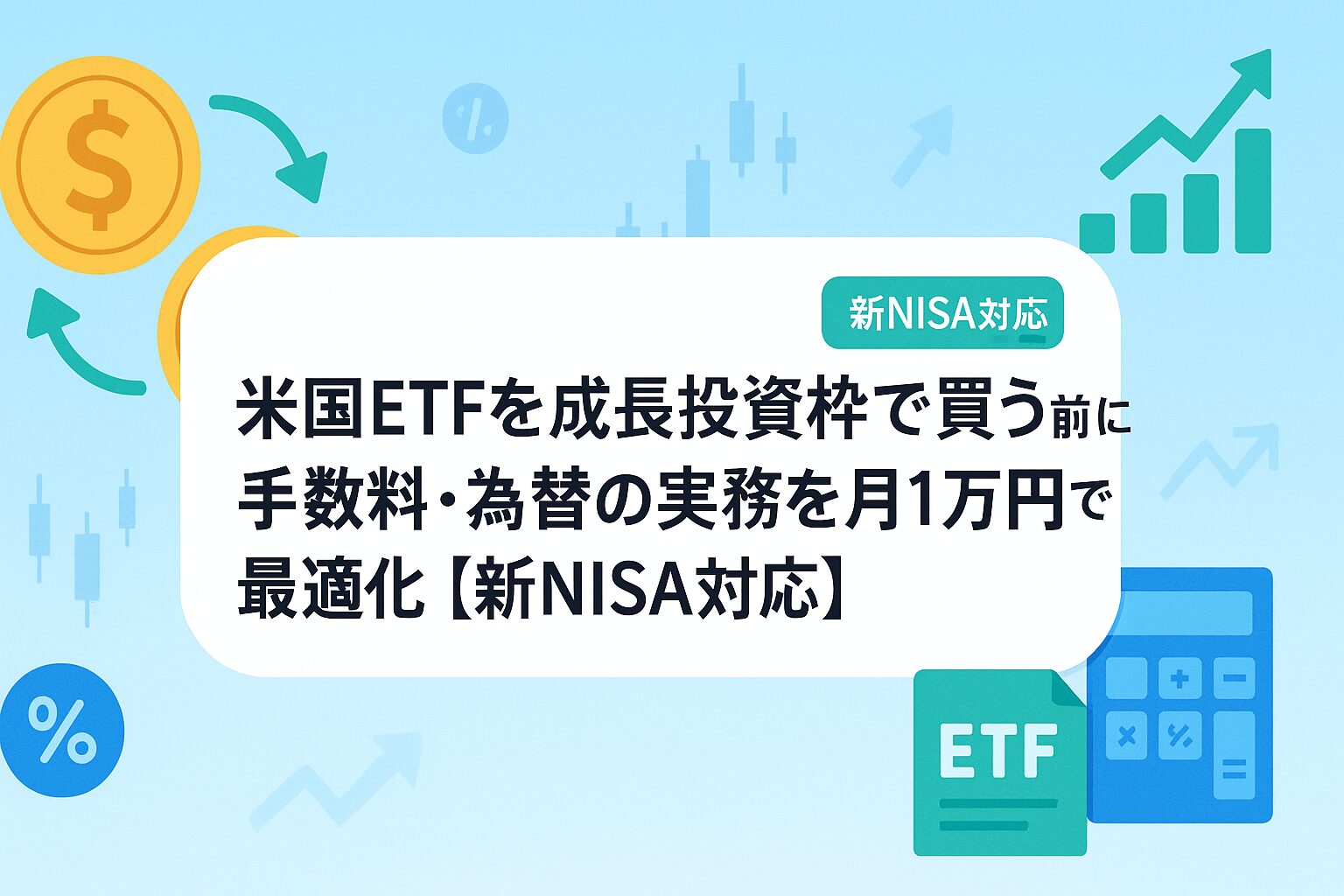この記事では、成長投資枠で米国ETFを買う前に押さえるべき実務を、初心者向けにわかりやすく解説します。
費用の内訳、円貨/外貨決済の選び方、買付頻度の最適化、配当と税・受取方法の注意点までカバーします。
ETFの基礎はETF編、制度の全体像はNISAの基礎知識を合わせてご覧ください。
\まずはNISA口座の準備から/
米国ETFは「成長投資枠」で買うのが基本



新NISAの非課税枠は、年間でつみたて120万円+成長240万円=合計360万円。
生涯投資枠は1,800万円(うち成長投資枠上限1,200万円)です。
売却すると売却した商品の簿価相当額が翌年以降に復活して再投資できます(年間投資枠に上乗せではありません)。
月1万円の現実的な買い方
米国ETFは1口あたりの価格が数千〜数万円相当になることが多いです。
毎月の少額で高頻度に買うより、隔月や四半期でまとめ買いにすると、売買手数料やスプレッドの影響を圧縮できます。
国内ETFで代替できる指数なら、売買単価や取引時間、為替コストの扱いも含めて比較しましょう。
自動積立(定期買付)への対応
SBI証券は「米株積立」で米国株・米国ETFの自動積立に対応しています。
買付頻度やボーナス月の増額など、続けやすいルールを先に決めておくと、運用が仕組み化できます。
国内ETFと迷うなら 👉 国内ETF vs 米国ETF
米国ETFのコスト構造(全体像)
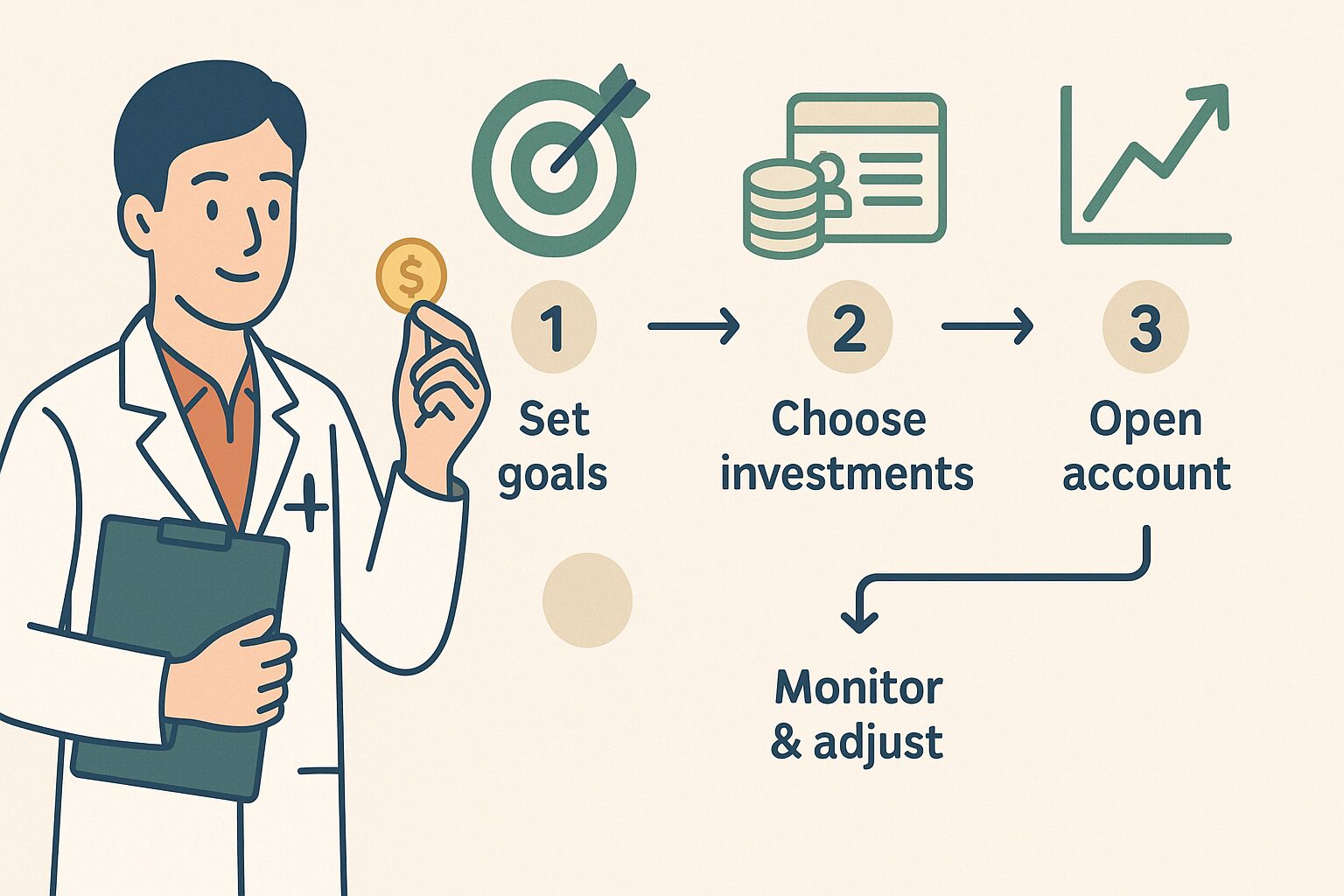


| コスト項目 | 発生タイミング | 最適化のコツ |
|---|---|---|
| 信託報酬(経費率) | 保有中に年率で目減り | 同カテゴリ最安級を選ぶ。目論見書・運用報告書で実質コストも確認。 |
| 売買手数料 | 約定時 | SBI証券は新NISA枠で米国株・海外ETFの売買手数料0円(対象・条件は公式参照)。高頻度発注は避ける。 |
| スプレッド | 約定時(気配差) | 出来高の多い銘柄・時間帯に指値で落ち着いて約定。 |
| 為替手数料/為替スプレッド | 円⇄ドルの両替時 | 円貨/外貨決済の総額で比較。外貨両替は銀行・証券の条件差を要チェック。 |
| 配当の源泉徴収 | 受取時 | NISAでも現地課税(例:米国10%)は残る。受取方法と再投資の動線を決める。 |
※スマホでは表が画面幅を超えます。横にスワイプしてご覧ください。
“費用の見方”を整理 👉 運用報告書・目論見書の読み方
約定のコツ(板・時間帯・指値)
米国市場は寄り付きと引け前に出来高が厚くなりやすい傾向があります。
板が厚い時間帯はスプレッドが狭くなりやすいため、基本は指値で落ち着いて約定を狙いましょう。
国内夜間で板が薄い時間帯の成行は、意図せぬスリッページに注意です。
\米国ETFの買付前にコスト設計/
為替の実務:円貨決済か外貨決済か



円貨決済のメリット・注意点
- 手間が少ないのが最大の利点。両替の事前手配が不要。
- 受取配当の円転や再投資の際、為替の往復コストが発生しうる。
- 内包スプレッドの水準は必ず確認しておく。
外貨決済のメリット・注意点
- 両替のコスト比較がしやすい。条件の良い両替手段を選べる。
- ドル受取の配当をそのまま再投資でき、再両替を避けられる。
- ドル残高の管理が必要。過度な円転は避けるルールを用意。
配当・税・受取方法(重要)
米国ETFの配当は、NISA口座でも米国での源泉徴収(例:10%)がかかります。
国内上場株式や国内ETFの配当をNISAで非課税受取にするには、証券会社で「株式数比例配分方式」の設定が必要です。
再投資の動線をシンプルにするなら、ドル受取→ドルで再投資の運用が効率的です。
やっぱり比較で判断 👉 国内ETF vs 米国ETF
国内配当は非課税で受け取る 👉 株式数比例配分方式の設定
月1万円でムダを減らす「買い方の型」



- 候補ETFを1〜2本に絞る(指数の王道性・経費率・出来高・純資産で選定)。
- 隔月または四半期でまとめ買いにして売買コストとスプレッドの影響を圧縮。
- 円貨/外貨決済は、為替コストの総額が小さいパターンを固定。
- 配当は原則再投資。キャッシュが欲しい場合は国内ETFや預金の別枠で確保。
銘柄選定の実務チェック



指数の王道性
長期の柱にするなら、S&P500や全世界株系など、広く使われる指数連動が無難です。
構成規則が明確で、継続投資の判断がブレにくくなります。
経費率と実質コスト
目先の差が僅かでも、長期の複利で効きます。
同カテゴリー内で最安級を選び、運用報告書で「その他費用」も確認しておきましょう。
出来高・スプレッド・純資産
出来高が薄いとスプレッドが広がり、不利約定のリスクが上がります。
板の厚い銘柄を選び、基本は指値。
純資産は右肩上がりが理想です。
分配と再投資動線
分配金はドル受取→同銘柄または近い指数に再投資する形がシンプルです。
円転を挟むほど為替コストが嵩む点に注意しましょう。
国内ETFで代替する視点



売買時間と板の厚み
国内ETFは東証の立会時間で取引します。
米国本国と時間差があるため、寄付き直後の成行はスプレッドが広がりやすい点に注意。
指値中心で落ち着いて約定させましょう。
売買単価と積立のしやすさ
国内ETFは売買単価が抑えられる銘柄も多く、少額での分散買いがしやすいケースがあります。
ただし経費率・分配方針は個別に要確認です。
為替コストの違い
国内ETFは円で売買できますが、対象が海外資産なら内部で為替が発生します。
外見上の両替が不要でも、総コストは目論見書で確認しておきましょう。
よくあるつまずきと回避策



- 高頻度の少額買付でコストが積み上がる。→回数を減らしてまとめ買い。
- 為替の往復コストを見落とす。→円貨/外貨決済の総額で比較して固定。
- 利回りだけで選ぶと流動性や指数の質を無視しがち。→出来高と指数の王道性を確認。
まとめ

ポイント
- 米国ETFは成長投資枠で買付(つみたて枠は投信中心)。
- 費用は「経費率+売買手数料+スプレッド+為替」の合計で最小化。
- 月1万円なら買付回数を減らすことでムダを圧縮。
- 配当は現地課税が残る。受取方法は株式数比例配分方式などを確認。


\読了ゴール:今のうちにNISA口座を準備/
👉 次はこちら:国内ETF vs 米国ETF