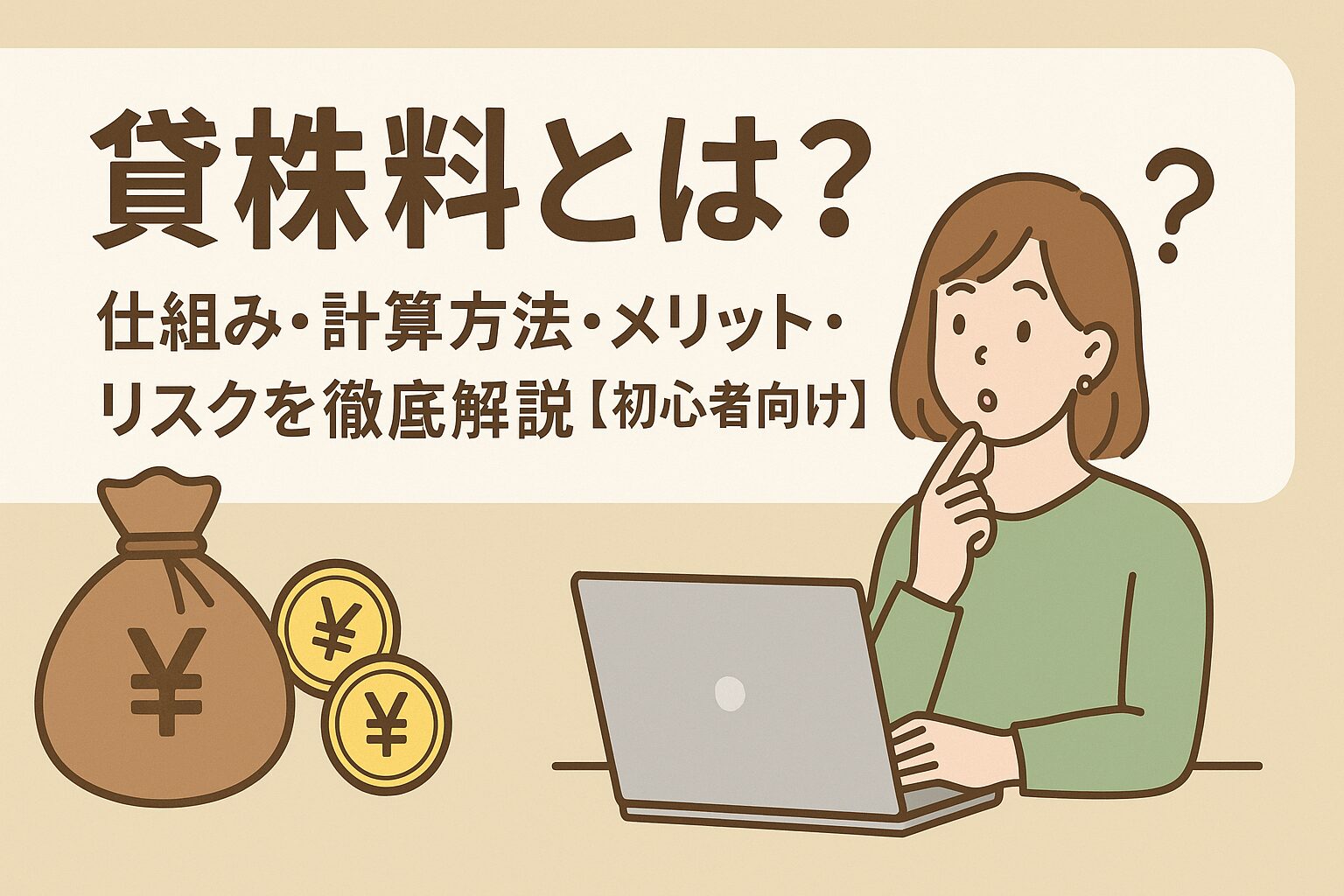貸株サービスは、保有している株式を活用して追加収入を得たい方に人気の資産運用方法です。
証券会社に株を貸し出すだけで「貸株料」という金利収入が得られるため、長期保有や売却予定のない株も有効活用できる点が特徴となります。

貸株料は年率で表示され、銘柄ごとに金利やサービス内容が異なります。
また、配当や株主優待も両立できる設定が増えており、ネット証券のマイページから簡単に申し込めるのもメリットです。
日割り計算で短期間でも収入が発生し、途中で売却したい場合も柔軟に対応できるため、資産運用の自由度が高いといえるでしょう。
ただし、配当や優待の権利、証券会社倒産時のリスクなど注意点も存在します。
貸株サービスの仕組みや計算方法、選び方のポイントを押さえて、眠っている株を賢く活用しましょう。

ポイント
- 貸株料は、株式を証券会社に貸し出すことで得られる金利収入である
- 貸株サービスはネット証券のマイページから簡単に申し込みできる仕組みである
- 貸株料は日割り計算となり、短期間でも収入を得ることができる
- 証券会社や銘柄によって金利やサービス内容が異なるため、比較検討が重要である
- 配当や株主優待も両立できる設定が増えており、初心者にも活用しやすいサービスとなる
\口座開設は無料/
貸株料とは?基本的な仕組みと特徴

この章では貸株料の基本的な仕組みと特徴について解説します。
貸株料の定義と役割
貸株料とは、証券会社を通じて自分が保有する株式を他の投資家に貸し出す際に受け取れる「金利収入」のことです。
このサービスを利用すると、株を持っているだけで追加の利益を得ることができます。
たとえば、長期保有している株や売却予定のない「塩漬け株」を有効活用できる点が魅力です。
貸株料は年率で表示され、銘柄ごとに0.1%から数%程度まで幅があります。
プレミアム銘柄ではさらに高い場合もあります。
証券会社によって金利やサービス内容が異なるため、比較して選ぶことが重要です。
株主優待や配当金を受け取りながら貸株できる設定も増えてきました。
投資初心者でもネット証券のマイページから簡単に申し込めるので、資産運用の一環として活用しやすい仕組みとなっています。
貸株料が発生する仕組み
貸株料が発生するのは、証券会社が個人投資家から株を借りて、それを必要とする他の投資家や機関に再貸し出すためです。
たとえば、信用取引で空売りをしたい人は市場で株を調達する必要がありますが、その際に証券会社が貸株サービスを通じて株を用意します。
このとき、株を貸し出した人には貸株料が日割りで支払われます。
計算式は「貸株数量×時価×貸株料率÷365」となり、1日単位で利益が発生。
期間が短くても、貸し出した分だけしっかり収入になるのが特徴です。
なお、銘柄によってはプレミアム金利が適用されることもあり、人気や需給によって金利が変動します。
貸株サービスの利用例
たとえば、100万円分の株を年率1%で1年間貸し出した場合、受け取れる貸株料は1万円になります。
もし高金利(例:5%)の銘柄なら、100万円分で5万円の収入が見込めます。
さらに、配当や株主優待も受け取りたい場合は「優待優先」や「配当優先」といった設定が可能な証券会社も多いです。
実際の利用手順は、証券会社のウェブサイトで貸株サービスに申し込み、貸し出す銘柄や数量を選ぶだけ。
途中で売却したい場合も、貸株中の株は自由に売却できます。
短期間だけ貸し出しても日割りで貸株料がもらえるため、忙しい人や投資初心者にも手軽に取り組めるサービスです。

貸株料の計算方法と金利の見方

この章では貸株料の計算方法と金利の見方について解説します。
貸株料の計算式と具体例
貸株料は、保有している株式を証券会社に貸し出すことで得られる収入です。
計算式は「株数 × 株価 × 貸株料率 ÷ 365 × 貸出日数」。
例えば、1,000株(株価1,000円、年率10%)を30日間貸し出した場合、1,000 × 1,000 × 10% ÷ 365 × 30=8,219円となります。
このように、貸株料は日割りで計算されるため、短期間でも収入が発生します。
日割り計算のポイント
貸株料は「両端入れ」で日数を計算します。
つまり、貸し出し開始日と返却日を含めて日数を数えます。
たとえば、5月1日から5月5日まで貸し出した場合、5日分の貸株料が発生。
休日も含めて計算される点に注意が必要です。
1日だけ貸し出しても、その分の収入がきちんと支払われる仕組みです。
銘柄ごとの金利差
貸株料率は銘柄ごとに大きく異なります。
一般的な銘柄は年率0.1~0.9%ですが、プレミアム銘柄は1%を超えることも。
10%以上の高金利銘柄も存在します。
人気や需給によって金利が変動するため、貸株サービスを利用する際は最新の金利情報を確認することが重要です。
証券会社のウェブサイトで一覧表示されていることが多いです。
金利情報の確認方法
貸株料率は証券会社ごとに異なり、同じ銘柄でも金利が違う場合があります。
最新の金利情報は、証券会社のマイページや「貸株金利一覧」画面で確認できます。
たとえば、SBI証券では「口座管理」→「貸株」→「貸株金利」から、楽天証券ではログイン後の「貸株サービス」ページで調べることが可能です。
金利は頻繁に見直されるため、定期的にチェックしましょう。
貸株料と他のコストの違い
貸株料は、株を貸し出すことで得られる「報酬」ですが、信用取引の「金利」や「品貸料(逆日歩)」など、他にもさまざまなコストが存在します。
信用買いの場合は借りた資金に対して金利が発生し、信用売りでは貸株料が必要です。
さらに、品貸料(逆日歩)は株不足時に発生する追加コストです。
管理費や名義書換料も条件によっては発生するため、トータルのコストを把握しておくことが大切です。

\口座開設は無料/
貸株料のメリット・デメリット

この章では貸株料のメリット・デメリットについて解説します。
貸株料収入のメリット
追加収入の可能性
貸株サービスを使うと、保有している株を証券会社に貸し出すだけで「貸株料」という金利収入が得られます。
たとえば、100万円分の株を年利1%で1年間貸し出すと、1万円の貸株料が手に入ります。
高金利銘柄なら10万円以上になるケースも。
銀行預金の金利と比べると、貸株料の利率は圧倒的に高い水準です。
株を売却せずに持ち続けているだけで副収入が生まれるため、長期保有や塩漬けになっている株を有効活用できます。
資産運用の効率化
貸株サービスは、普段使っていない株式資産を効率的に活用できる点も魅力です。
貸株の設定はネット証券のマイページから簡単にでき、途中で株を売却したい場合も自動で貸株が解除されるので、流動性が損なわれません。
また、貸株料は日割りで計算されるため、短期間だけ貸し出しても収入が発生します。
忙しい人や初心者でも、ほぼ手間なく資産運用の効率を高められる仕組みです。
貸株サービスのデメリットとリスク
株主優待や配当の権利への影響
貸株中は、株主優待や配当金の受け取りに制約が生じる場合があります。
たとえば、「金利優先」で貸株を続けると、配当金は「配当金相当額」として受け取ることになり、税区分が雑所得に変わります。
この場合、配当控除や譲渡損との損益通算ができなくなり、確定申告が必要になることも。
株主優待も、設定によっては受け取れないケースがあるため注意が必要です。
ただし、「株主優待優先」や「配当優先」などの設定を選べば、権利確定日に自動で貸株が解除され、優待や配当も受け取れる仕組みが用意されています。
証券会社倒産リスク
貸株サービスには、証券会社が倒産した場合のリスクも存在します。
貸株契約は「消費貸借契約」となり、株式は証券会社の資産に組み込まれるため、万一倒産が起きると投資家は一般債権者として扱われ、株が返却されない可能性があるのです。
このリスクは全ての証券会社に共通しており、貸株料という「おまけの利益」と資産喪失リスクを天秤にかけて判断する必要があります。
もし市場や証券会社の不安が高まった場合は、貸株を一時的に解除するなど、柔軟に対応することが大切です。

貸株料サービスの選び方と注意点

この章では貸株料サービスの選び方と注意点について解説します。
証券会社ごとのサービス比較
貸株料サービスを選ぶ際は、まず証券会社ごとのサービス内容を比較することが重要です。
代表的なネット証券では、SBI証券、楽天証券、DMM.com証券などが人気で、貸株料の金利や手数料、取り扱い銘柄数に差があります。
SBI証券・楽天証券の貸株料は銘柄や取引形態により異なり、0.1%~1.10%程度が中心です。
売買手数料は無料のことが多いです。
一方、DMM株は売買手数料が無料で、初心者でも使いやすい取引ツールを提供しています。
また、貸株サービスに加え、信用取引のサポートやPTS取引(夜間取引)対応など、取引環境の充実度も比較ポイントです。
各社の特徴を理解し、自分の投資スタイルに合った証券会社を選ぶことが、満足度の高い貸株サービス利用につながります。
選ぶ際のチェックポイント
金利・手数料の違い
貸株料の金利は証券会社や銘柄によって異なり、0.1%~1.0%台が多く、プレミアム銘柄では1%を超えることもあります。
金利が高い銘柄は魅力的に見えますが、株価変動リスクも高い場合があるため注意が必要です。
また、貸株サービス自体の手数料は無料のケースが多いですが、取引手数料や信用取引の金利・貸株料には差があるため、総合的なコストを把握しましょう。
たとえば、楽天証券やSBI証券は売買手数料が無料で、貸株料も比較的低水準に設定されています。
コストを抑えつつ安定した収益を狙うなら、これらの証券会社が選択肢に入ります。
サポート体制や補償内容
貸株サービス利用時のトラブルに備え、証券会社のサポート体制や補償内容を確認することも大切です。
貸株契約は消費貸借契約となるため、証券会社倒産時は株券返却保証がない場合も多いです。
問い合わせ対応の迅速さは重要な評価ポイント。
SBI証券や楽天証券は信用リスク管理や代替株券調達の仕組みを持つが、倒産時の全額返却保証があるわけではありません。
また、オンラインチャットや電話サポートが充実しているかも、初心者には安心材料です。
補償やサポートの有無は契約書や公式サイトで必ず確認してください。
利用時の注意点とトラブル事例
貸株サービスを利用する際は、いくつかの注意点があります。
まず、貸株中は株主優待や株主総会の参加権が制限される場合があるため、優待狙いの株は設定に注意が必要です。
また、貸株料が高い銘柄は株価の変動リスクも高く、損失リスクを伴うことを理解しましょう。
トラブル事例としては、貸株先の信用不安による株券返却遅延や、貸株設定の解除忘れによる売却タイミングのずれなどがあります。
こうしたリスクを避けるために、貸株サービスの契約内容をよく読み、定期的に貸株状況を確認する習慣をつけることが大切です。
また、貸株料は日割り計算されるため、短期間の貸出でも収益が得られますが、貸株解除のタイミングにも注意しましょう。

貸株料と配当・株主優待の両立方法

この章では貸株料と配当・株主優待の両立方法について解説します。
配当・優待を受け取りながら貸株する方法
貸株サービスを利用しつつ、配当や株主優待も受け取りたい方は「配当優先」や「優待優先」などの設定がポイントです。
たとえば、SBI証券や楽天証券では、配当金や株主優待の権利確定日だけ自動的に貸株を解除する機能が用意されています。
これにより、通常は貸株料を受け取りつつ、権利確定日には自分名義で株を保有し、配当や優待も逃しません。
初心者でも証券会社のマイページから簡単に設定できるため、手軽に両立を目指せます。
設定のコツと証券会社の対応例
両立を実現するためのコツは、証券会社ごとの設定方法をしっかり確認することです。
たとえば、SBI証券では「配当・優待優先」「優待優先」などの選択肢があり、楽天証券も「権利取得優先設定」が用意されています。
設定画面で「自動解除」を選ぶだけで、権利確定日に自動的に貸株が解除される仕組みです。
マネックス証券や三菱UFJ eスマート証券
も同様のサービスを展開しています。
証券会社によっては、優待銘柄リストや権利確定日のカレンダー機能があり、スケジュール管理も簡単です。
事前に公式サイトの案内やFAQをチェックしておくと安心です。
両立時の注意点とよくある疑問
配当や株主優待と貸株料の両立には注意点もあります。
たとえば、貸株中は「配当金相当額」として受け取る場合があり、通常の配当金と税制が異なるケースがあります。
また、株主名簿に名前が載らない場合、優待がもらえないこともあるため、必ず「優待優先」設定を確認しましょう。
権利確定日直前の設定変更は間に合わないことがあるので、余裕を持って手続きするのがコツです。
さらに、証券会社によっては一部の銘柄で自動解除が適用されない場合もあります。
疑問があればカスタマーサポートに問い合わせることで、具体的な対応策を教えてもらえます。

まとめ

ポイント
- 貸株料は、株式を証券会社に貸し出すことで得られる金利収入である
- 貸株サービスはネット証券のマイページから簡単に申し込みできる仕組みである
- 貸株料は日割り計算となり、短期間でも収入を得ることができる
- 証券会社や銘柄によって金利やサービス内容が異なるため、比較検討が重要である
- 配当や株主優待も両立できる設定が増えており、初心者にも活用しやすいサービスとなる
今回は貸株料について説明してきました。
最後にもう一度まとめます。
貸株サービスは、保有している株式を証券会社に貸し出すことで金利収入を得られる便利な仕組みです。
長期保有株や売却予定のない株を有効活用でき、ネット証券のマイページから簡単に申し込めます。
貸株料は日割り計算で、短期間でも収入が発生しますが、証券会社や銘柄ごとに金利やサービス内容が異なるため、しっかり比較検討することが大切です。
配当や株主優待と両立できる設定も増えていますが、税制やリスクにも注意が必要です。
自分の投資スタイルや目的に合った運用方法を選び、契約内容や注意点をよく確認して、賢く資産運用を進めましょう。


\口座開設は無料/
続きを見る 続きを見る 続きを見る

証券会社ランキング|おすすめネット証券を徹底比較【2025年最新】

SBI証券口座開設のやり方・申し込み方法を徹底解説【初心者向け】

楽天証券の口座開設方法|スマホで最短申込、翌営業日スタート
参考: