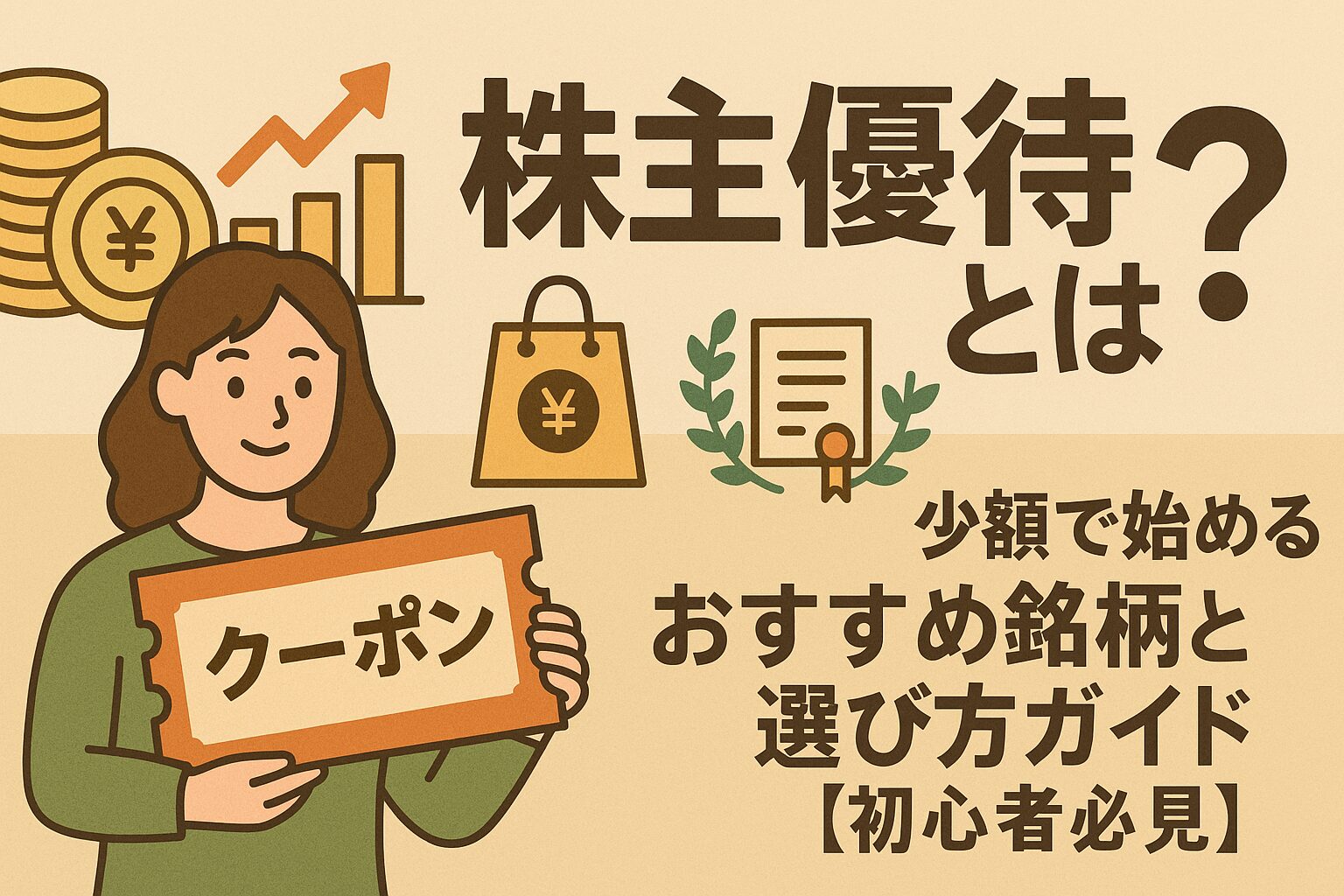株主優待は、企業が自社株を保有する株主に対して自社製品やサービス、金券などを贈る仕組みです。
配当金との違いは、現金ではなく商品やサービスで還元される点にあります。

優待を受け取るには証券会社で口座を開設し、権利付き最終日までに必要株数を保有する必要があるため、スケジュール管理が大切となります。
優待内容や必要株数、権利確定日は企業ごとに異なり、突然の変更や廃止リスクもあるため、常に最新情報を確認する姿勢が求められます。
少額投資でも始めやすく、生活に役立つ優待も多い一方で、リスク管理や分散投資も忘れずに行うことが大切です。

ポイント
- 株主優待は、企業が一定数の株式を保有する株主に自社製品やサービス、金券などを提供する制度である。
- 配当金は現金で自由に使えるが、株主優待は商品やサービスなど現金以外で提供される点が特徴である。
- 株主優待を受け取るには、証券会社で口座開設し、権利付き最終日までに必要株数を保有する必要がある。
- 優待内容や必要株数、権利確定日は企業ごとに異なり、突然の変更や廃止リスクもあるため注意が必要である。
- 少額投資でも始めやすく、生活に役立つ優待も多いが、リスク管理や最新情報の確認が重要となる。
株主優待初心者が知っておきたい基本知識

この章では株主優待初心者が知っておきたい基本知識について解説します。
株主優待とは?仕組みとメリット
株主優待とは、企業が自社の株式を一定数以上保有している株主に対して、商品やサービス、金券などを贈る制度です。
たとえば、食品会社なら自社製品の詰め合わせ、外食チェーンなら食事券、鉄道会社なら乗車券など、内容は企業ごとにさまざま。
優待品にはカタログギフトやQUOカードなど現金に近いものも含まれます。
この制度は、個人投資家にとって投資の楽しみやメリットの一つになっています。
実際に優待品が届くと、投資のモチベーションが上がる人も多いです。
また、企業の商品やサービスを実際に体験できるため、投資先への理解が深まるという利点もあります。
一方で、優待内容や実施の有無は企業ごとに異なり、突然の変更や廃止もあるため、最新情報のチェックが欠かせません。
たとえば、吉野家ホールディングスの株を持つとグループ店舗で使える優待券がもらえる、カゴメならトマトジュースなどの詰め合わせが届くなど、生活に役立つ優待も多いです。
株主優待と配当金の違い
株主優待と配当金は、どちらも株主に対する企業からのリターンですが、内容が大きく異なります。
配当金は企業の利益の一部を現金で還元するもの。
受け取ったお金は自由に使えます。
たとえば、再投資に回したり、生活費に充てたりと用途を選びません。
一方、株主優待は現金ではなく、企業が指定する商品やサービス、金券などが提供される点が特徴です。
たとえば、飲食店の株主なら食事券、家電メーカーなら自社製品の割引券など、使い道が限定されることもあります。
税制面でも違いがあります。
配当金は所得税および住民税の課税対象です。
また、株主優待も原則として雑所得に該当し課税対象となります。
ただし、株主優待による雑所得が年間20万円以下の場合は所得税の確定申告が不要とされていますが、住民税については申告が必要です。
実際には、株主優待の申告が行われていない場合も多く、実態として非課税になっているケースも見受けられます。
また、配当金は企業の業績次第で増減しやすい一方、優待は企業の方針で突然廃止や変更されることもあります。
どちらもメリット・デメリットがあるため、自分の目的に合わせて選ぶのがポイントです。
株主優待のもらい方(権利確定日・必要株数)
株主優待を受け取るには、まず証券会社で口座を開設し、優待を実施している企業の株式を購入する必要があります。
ただ株を買えばいいというわけではなく、「権利付き最終日」までに必要な株数を保有していることが条件です。
権利付き最終日とは、企業が定める「権利確定日」の2営業日前のこと。
この日までに株を買っておけば、権利確定日に株主名簿へ記載され、優待を受け取る権利が発生します。
たとえば、3月末が権利確定日の企業なら、3月27日が権利付き最終日(平日の場合)となり、この日までに株を購入していればOK。
翌日の「権利落ち日」には株を売っても優待はもらえます。
必要な株数は企業ごとに異なり、100株や500株など区切りが設定されていることが多いです。
保有株数が多いほど優待の内容がグレードアップする場合もあります。
優待品は権利確定月の2~3カ月後に自宅へ郵送されるのが一般的。
待ちきれない場合は企業の公式サイトで発送時期を確認できます。
証券会社の口座開設は無料で、ネット証券なら手数料も安く、初心者にも使いやすいサービスが充実しています。
このように、株主優待は「いつまでに」「何株」保有するかがポイント。
スケジュールと必要株数をしっかり確認して、計画的にチャレンジしましょう。
>>SBI証券で口座開設をする
>>楽天証券で口座開設をする

▼口座開設について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
株主優待初心者におすすめの少額銘柄ランキング

この章では株主優待初心者におすすめの少額銘柄ランキングについて解説します。
10万円以下で買える株主優待銘柄
株主優待は「お金持ちだけの特権」と思い込んでいませんか。
実際は、10万円以下の少額資金でも株主優待を受け取れる銘柄が多数存在します。
例えば、山喜(3598)は2万円台で買えるうえ、買物券がもらえる点が魅力。
ヤマダホールディングス(9831)は5万円以下で家電割引券が年2回届きます。
ストリーム(3071)は1万円台で自社ECサイトの割引券が手に入るため、ネットショッピング好きにもおすすめ。
こうした低価格帯の銘柄は、リスクを抑えつつ優待デビューしたい人にぴったりです。
証券会社によっては売買手数料が安く、ポイント還元も受けられるサービスがあるので、コスト面でも安心できます。
人気の株主優待ジャンル別おすすめ
株主優待の魅力は、もらえる品のバリエーションが豊富なこと。
特に人気のジャンルを「食品・日用品」「外食・レジャー」「ギフト・金券」に分けて紹介します。
ジャンルごとに自分や家族の生活スタイルに合った優待を選ぶことで、満足度がぐっと高まります。
以下で具体的な銘柄例を見ていきましょう。
食品・日用品
日々の生活で役立つ食品や日用品は、家計の節約にも直結するジャンルです。
たとえば、ライオン(4912)は自社の洗剤や歯磨き粉など日用品セットが届きます。
旭松食品(2911)は味噌汁や乾物などの詰め合わせが株主優待品。
ヤマダホールディングス(9831)は家電量販店の割引券がもらえるため、家電や日用品の購入に活用できます。
アスクル(2678)はLOHACOで使えるクーポンがもらえるので、ネットでまとめ買いしたい人にもおすすめです。
外食・レジャー
外食チェーンやレジャー施設の優待は、家族や友人と楽しみたい人に人気です。
すかいらーくホールディングス(3197)は2,000円分の食事券がもらえ、全国のグループ店舗で利用可能。
アトム(7412)は優待ポイントが付与され、系列レストランで食事ができます。
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)も、和食やカフェなど多彩な店舗で使える食事券が届きます。
こうした優待は、外食費の節約やちょっとしたご褒美に最適です。
ギフト・金券
使い道の自由度が高い金券やギフトカードも根強い人気があります。
たとえば、キューブシステム(2335)は1,000円分のJCBギフトカード、OCCHIホールディングス(3166)は2,000円分のQUOカードがもらえます。
QUOカードはコンビニや書店など幅広い店舗で利用できるため、現金感覚で使えるのが魅力です。
高千穂交易(2676)はお米ギフト券を提供しており、食費の節約にも役立ちます。
こうした金券系優待は、初心者でも使い勝手が良く、満足感が高いジャンルといえるでしょう。
このように、少額投資でも楽しめる株主優待は多彩です。
自分の生活スタイルや目的に合わせて銘柄を選ぶことで、投資の楽しみが広がります。
最新の優待内容や株価は、証券会社の公式サイトや優待情報サイトで必ず確認してから購入しましょう。

株主優待初心者が失敗しないための選び方と注意点

この章では株主優待初心者が失敗しないための選び方と注意点について解説します。
株主優待銘柄の選び方ポイント
株主優待銘柄を選ぶ際は「自分が本当に欲しい優待か」を最優先にしましょう。
たとえば、外食の優待券でも生活圏内で使えないと意味がありません。
家族構成やライフスタイルに合った優待内容かどうかも大切な視点です。
次に、少額から投資できる銘柄を選ぶと失敗しにくくなります。
10万円以下で手に入る優待株も多く、初心者はまず小さな金額から始めるのが安心です。
また、企業の業績や配当の有無も必ず確認しましょう。
赤字企業や配当のない会社は優待廃止リスクが高まります。
業績が安定しているか、配当も出しているか、過去数年の決算やIR情報をチェックしてください。
さらに、優待の権利確定月や保有期間の条件も調べておくと、無駄な待ち時間や思わぬ条件違いを防げます。
複数銘柄を組み合わせて、優待が届く時期を分散させると一年を通じて楽しめます。
優待利回りの計算方法
優待利回りは「投資金額に対してどれだけ優待の価値があるか」を示す指標です。
計算式はとてもシンプルです。
優待利回り(%)= 優待の価値(円) ÷ 優待取得にかかった金額(円) × 100
たとえば、年間3,000円分の優待がもらえる銘柄で、株価が1株500円、100株必要なら投資金額は5万円。
この場合、3,000 ÷ 50,000 × 100 = 6%となります。
配当もある場合は、配当利回りと合算して「総合利回り」として比較するのが一般的です。
ただし、利回りが高いからといって飛びつくのは危険です。
株価が大きく下がって利回りが上がっているケースもあるため、企業の業績や財務内容を必ずチェックしましょう。
株主優待のリスクと注意点
株主優待は魅力的な制度ですが、リスクや注意点も存在します。
まず、優待内容や実施自体が突然変更・廃止される可能性があります。
企業の業績悪化や経営方針の転換が理由になることが多いです。
また、優待をもらうために株を保有している間、株価が下落するリスクも無視できません。
優待の価値以上に株価が下がると、結果的に損失が大きくなります。
信用取引では優待がもらえない点にも注意が必要です。
現物株で保有することが条件となります。
リスクを抑えるには、複数銘柄に分散投資する、業績や財務が安定している企業を選ぶ、配当も出している会社を選ぶなどの工夫が有効です。
優待廃止・改悪リスク
株主優待は企業の裁量で実施されているため、廃止や改悪はいつでも起こり得ます。
近年はコスト削減や株主間の公平性を理由に、人気銘柄でも廃止が相次いでいるのです。
優待廃止が発表されると、多くの投資家が株を売却し、株価が急落するケースが目立ちます。
優待がもらえなくなるだけでなく、株価下落のダブルパンチを受けるリスクがあるため、業績や財務の健全性を重視しましょう。
株価変動の影響
株主優待を狙って株を保有している間、株価が大きく変動することがあります。
権利確定日直前は買いが集まりやすく、確定日後は売りが集中しやすい傾向です。
また、業績悪化や市場全体の下落で株価が大きく下がると、優待の価値を上回る損失を被ることも。
リスクを減らすには、1つの銘柄に資金を集中させず、分散投資を心がけることが重要です。
株主優待は「おまけ」として楽しみつつ、投資の基本であるリスク管理を忘れないようにしましょう。

株主優待初心者が活用したい証券会社と便利サービス

この章では株主優待初心者が活用したい証券会社と便利サービスについて解説します。
初心者におすすめの証券会社比較
株主優待を始めたい初心者には、手数料の安さや使いやすさ、情報の豊富さが重要です。
2025年現在、楽天証券とSBI証券が特に人気を集めています。
楽天証券は売買手数料が0円、スマホやPCでの操作性も高く、楽天ポイントを使った投資も可能。
SBI証券も手数料0円を実現しており、IPOや投資信託など取扱商品が豊富です。
どちらも口座開設数が600万を超え、初心者からベテランまで幅広い層に選ばれています。
松井証券や三菱UFJ eスマート証券も、定額手数料やシンプルな取引画面で評価されています。
ネット証券は実店舗を持たない分、コストを抑えられるのが特徴。
長期運用や少額投資を目指す人にも向いています。
関連記事
株主優待検索・シミュレーション機能の活用法
「どの銘柄を選べばいいか分からない」という初心者の悩みを解決するのが、証券会社の株主優待検索機能です。
楽天証券やSBI証券では、優待内容や必要投資金額、権利確定月など細かい条件を指定して、該当する銘柄を簡単に絞り込めます。
検索結果はリアルタイムで表示され、気になる銘柄の詳細もワンタッチで確認可能。
さらに、三菱UFJ eスマート証券などでは「優待クロスシミュレーター」も提供。
クロス取引*にかかるコストや優待価値を自動計算できるため、コストパフォーマンスを事前にチェックできます。
こうしたツールを使いこなせば、効率よく自分に合った優待銘柄を見つけられます。
クロス取引*:同じ銘柄に対して同じ数量・同じ価格で「買い」と「売り」の注文を同時に出し、約定させる取引手法
サポートや情報収集に役立つサービス
初心者が安心して株主優待投資を始めるには、サポート体制や情報提供も大切です。
楽天証券やSBI証券では、株主優待に特化したニュースやコラム、プロやブロガーによる解説記事が充実しています。
松井証券は「マーケットラボ」やQ&A、チャットサポートで疑問をすぐに解決できる仕組みを用意。
スマホアプリも進化しており、銘柄検索や情報収集、取引まで一括で行えるのが強みです。
困ったときは公式サイトのヘルプやチャット、電話サポートを活用しましょう。
証券会社の便利な機能やサポートを活用すれば、株主優待デビューもスムーズに進められます。

まとめ

ポイント
- 株主優待は、企業が一定数の株式を保有する株主に自社製品やサービス、金券などを提供する制度である。
- 配当金は現金で自由に使えるが、株主優待は商品やサービスなど現金以外で提供される点が特徴である。
- 株主優待を受け取るには、証券会社で口座開設し、権利付き最終日までに必要株数を保有する必要がある。
- 優待内容や必要株数、権利確定日は企業ごとに異なり、突然の変更や廃止リスクもあるため注意が必要である。
- 少額投資でも始めやすく、生活に役立つ優待も多いが、リスク管理や最新情報の確認が重要となる。
今回は株主優待について説明してきました。
株主優待は持っているだけでもらえるので、初心者でも簡単に手を出せます。
「株式投資で稼ぎたい、利益を上げたい」というのであれば勉強が必要ですが、株主優待をもらうだけであればそこまで難しい勉強は必要ありません。
株式投資をするかどうか迷っている人は、とりあえず株主優待目的から始め、興味が出てきたら少しずつ投資の勉強をするのはいかがでしょうか?


\口座開設は無料/
参考: