

「セルインメイ」とは、5月に株を売却し、夏場の低迷しやすい市場を回避するという投資戦略を指します。
この格言は欧米市場で広く知られ、特に5月から9月にかけて株価が停滞する傾向があることから生まれました。
一方で、日本市場ではこのアノマリーが必ずしも当てはまるわけではありません。
例えば、過去のデータを見ると5月の勝率は高く、直近5年間でも勝率が非常に高いという結果が出ています。
これは日本特有の要因が影響しており、3月決算後の業績発表や配当金支払いなどが株価を支えるケースが多いからです。

また、日本の投資家行動や季節性も異なり、夏場でも株価が上昇する年が少なくありません。
そのため、日本株においては「セルインメイ」に固執せず、長期的なトレンドや配当利回りを重視した柔軟な戦略が推奨されます。
さらに、夏場に強い銘柄やセクターに注目することで、より安定的な投資成果を目指すことも可能です。

▼夏枯れ相場について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-
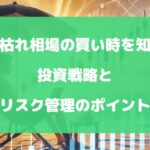
-
夏枯れ相場の買い時を知る:投資戦略とリスク管理のポイント
続きを見る
ポイント
- 「セルインメイ」は、5月に株を売り夏場の低調な市場を避ける投資戦略である。
- 日本市場では、「セルインメイ」の効果が米国ほど顕著ではなく、5月以降も上昇する年が多い。
- 日本特有の要因として、3月決算後の業績発表やお盆休みなどが株価に影響を与える。
- 過去データでは、5月の勝率は高く、直近5年間は好調。
- トレードスタイルが長期では、「セルインメイ」に頼るより、長期的なトレンドや配当利回り重視の戦略が有効となる。
セルインメイとは?日本株への影響を解説

この章ではセルインメイの日本株への影響について解説します。
セルインメイの由来と欧米市場での背景
「セルインメイ」の格言が生まれた理由
「セルインメイ」とは、5月に株式を売却し、夏場の低調な市場を避けることでリスクを軽減するという投資戦略です。
この格言は、特に欧米市場での季節性に基づいており、過去のデータから夏場の株価が軟調になる傾向が見られることが背景にあります。
例えば、1929年のウォール街の大暴落や1987年のブラックマンデーなど、歴史的な株価下落が5月から10月の間に集中していたことが、この戦略を支持する要因となっているのです。
また、投資家が夏休みを取ることで市場活動が減少し、流動性が低下することも理由として挙げられます。
欧米市場での季節性と投資行動の関係
欧米市場では、11月から4月までの期間に株式市場が好調になる「ハロウィン指標」が知られています。
この期間は企業業績発表や年末調整によるポジティブな材料が多く、市場全体が活気づく傾向があるのです。
一方で、5月以降は経済活動や企業ニュースが減少し、株価が停滞することがあります。
日本株市場での「セルインメイ」の認知度と適用状況
日本市場特有の季節性要因
日本市場では「セルインメイ」の影響は欧米ほど顕著ではありません。
日経平均株価やTOPIXを分析すると、6月から9月までの期間でも上昇する年が多く、必ずしもこのアノマリーが機能しているとは言えません。
例えば、日本企業は3月決算が多いため、その後の業績発表や配当金支払いなどが株価を支える要因となります。
さらに、日本特有の「お盆休み」や円高ドル安傾向が夏場の株価動向に影響を与えることもあります。
外国人投資家の動向が与える影響
日本株市場では外国人投資家の売買動向が重要な役割を果たします。
海外投資家は日本株取引量の約70%を占めており、その動向によって市場全体が左右されることがあります。
例えば、夏場には外国人投資家が長期休暇を取るため売買活動が減少し、市場流動性が低下する傾向があります。
また、円高ドル安による為替影響も海外投資家にとって重要な要素であり、それによって売買判断が変化します。
これらを踏まえると、日本市場では「セルインメイ」をそのまま適用するよりも、日本独自の季節性要因や外国人投資家動向を考慮した戦略を立てることが重要です。

セルインメイは日本株で機能するのか?過去データを検証

この章では過去のデータについて解説します。
2005~2024年:各月の勝ち数・勝率
| 勝ち数 | 年数 | 勝率 | 騰落率 | |
| 1月 | 11 | 20 | 55.0% | -0.7% |
| 2月 | 12 | 20 | 60.0% | 0.6% |
| 3月 | 11 | 20 | 55.0% | 0.8% |
| 4月 | 11 | 20 | 55.0% | 1.5% |
| 5月 | 13 | 20 | 65.0% | 0.3% |
| 6月 | 13 | 20 | 65.0% | 0.6% |
| 7月 | 10 | 20 | 50.0% | 0.4% |
| 8月 | 9 | 20 | 45.0% | -0.8% |
| 9月 | 11 | 20 | 55.0% | 0.3% |
| 10月 | 11 | 20 | 55.0% | 0.2% |
| 11月 | 13 | 19 | 68.4% | 2.9% |
| 12月 | 13 | 19 | 68.4% | 2.0% |
※2024年11月現在
ポイント
- 最も勝ちやすい月:11月と12月で68.4%(13勝6敗)
- 騰落率トップ:11月で2.9%
- 最も負けやすい月:8月で45.0%(9勝11敗)
- 騰落率ワースト:8月で-0.8%
- 5月が負けやすい、下がりやすいというわけではない

2020~2024年:各月の勝ち数・勝率
| 勝ち数 | 年数 | 勝率 | 騰落率 | |
| 1月 | 3 | 5 | 60.0% | 1.2% |
| 2月 | 3 | 5 | 60.0% | 0.5% |
| 3月 | 4 | 5 | 80.0% | 0.1% |
| 4月 | 2 | 5 | 40.0% | 0.0% |
| 5月 | 5 | 5 | 100.0% | 3.5% |
| 6月 | 3 | 5 | 60.0% | 1.7% |
| 7月 | 1 | 5 | 20.0% | -0.8% |
| 8月 | 3 | 5 | 60.0% | 1.6% |
| 9月 | 2 | 5 | 40.0% | -1.4% |
| 10月 | 2 | 5 | 40.0% | 0.7% |
| 11月 | 3 | 4 | 75.0% | 5.3% |
| 12月 | 2 | 4 | 50.0% | 0.1% |
※2024年11月現在
ポイント
- 最も勝ちやすい月:5月で100%(5勝0敗)
- 騰落率トップ:11月が5.3%でトップ
- 最も負けやすい月:7月で20.0%(1勝4敗)
- 騰落率ワースト:9月が-1.4%でワースト
統計を取る範囲によって勝率が異なってくることがわかります。
過去20年では11月が一番成績が良かったですが、直近5年間では5月が勝率100%と一番高い結果となっています。
これらの結果から、セルインメイは必ずしも日経平均に当てはまるとは限らないとわかります。

月別の詳細なアノマリーを知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-

-
【日経平均株価】月ごとの動きとアノマリーを探る
続きを見る
-
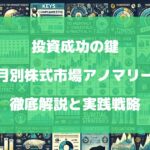
-
投資成功の鍵:月別株式市場アノマリーの徹底解説と実践戦略
続きを見る
セルインメイに基づく日本株の売買戦略とは

この章では売買戦略について解説します。
「セルインメイ」に基づく売却タイミングの考え方
短期投資家向けの戦略例
短期投資家にとって、「セルインメイ」は市場の季節性を活用するシンプルな戦略です。
具体的には、5月初旬に保有株を売却し、夏場の相場下落リスクを回避します。
長期投資家が取るべきアプローチ
長期投資家の場合、「セルインメイ」をそのまま適用するよりも柔軟な対応が求められます。
例えば、5月以降に業績が安定している銘柄や配当利回りが高い銘柄を保有し続けることで、安定した収益を確保できます。
また、夏場の円高リスクや景気動向を考慮しつつ、セクターごとのパフォーマンスを分析することも重要です。
特に、防御的なセクター(医薬品や食品関連)へのシフトは有効な戦略となるでしょう。
「セルインエイプリル」など代替戦略の提案
春先に売却するメリット・デメリット
「セルインエイプリル」(4月に売却)戦略は、5月相場のリスクをさらに早期に回避する方法です。
メリットとしては、新年度入りによる需給改善や海外投資家の買いが一巡したタイミングで利益確定が可能になる点があります。
一方で、4月末には多くの企業が決算発表を行うため、この情報を待たずに売却すると短期的な上昇機会を逃すリスクもあります。
夏場に注目すべき銘柄やセクター
夏場には「サマーストック」と呼ばれる猛暑関連銘柄が注目されます。
例えば、エアコン関連株や飲料メーカー(ビールや清涼飲料水)が挙げられます。
これらの銘柄は気温上昇による需要増加が期待されるため、市場全体が低迷していても比較的堅調な動きを見せることがあるのです。
また、防御的なセクターとして医薬品や生活必需品関連株も検討対象となります。
以上のように、「セルインメイ」だけでなく代替戦略も柔軟に取り入れることで、より効果的な投資判断が可能になります。

▼夏枯れ相場について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-
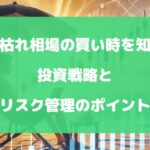
-
夏枯れ相場の買い時を知る:投資戦略とリスク管理のポイント
続きを見る
日本株市場で「セルインメイ」を活用する際の注意点

この章では「セルインメイ」を活用する際の注意点について解説します。
「セルインメイ」に頼りすぎるリスクとは?
アノマリーが機能しない場合の損失リスク
「セルインメイ」は過去の経験則に基づくアノマリーですが、必ずしも毎年機能するわけではありません。
例えば、2024年の日経平均株価は5月以降も堅調に推移し、「セルインメイ」を信じて売却した投資家はその後の上昇を逃す結果となりました。
また、アノマリーに頼りすぎると、他の重要な市場要因を見落とすリスクがあります。
実際には、企業業績や経済指標などが株価に与える影響が大きく、これらを無視して売買することは損失につながる可能性があります。
市場環境やファンダメンタルズを無視する危険性
市場環境は年によって異なり、「セルインメイ」が成立しない状況もあります。
例えば、円安や海外投資家の買い越しが続いている場合、日本株は5月以降も上昇する可能性があるのです。
さらに、ファンダメンタルズ分析を怠ると、割安な銘柄を手放してしまうことがあります。
株価収益率(PER)や自己資本利益率(ROE)などの指標を活用し、企業の収益性や成長性を見極めることが重要です。
「セルインメイ」を活用する際に考慮すべきポイント
経済指標や企業業績との併用分析方法
「セルインメイ」を利用する場合でも、経済指標や企業業績を併せて分析することが必要です。
例えば、消費者物価指数(CPI)やGDP成長率などのマクロ指標は市場全体の動向を把握する際に役立ちます。
また、企業業績では売上高営業利益率や総資産利益率(ROA)などを確認すると、収益性の高い銘柄を見極められます。
これらの情報を組み合わせることで、「セルインメイ」の判断精度が向上します。
▼CPIについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-

-
CPIと日経平均の動向:インフレ予測と株価への影響
続きを見る
外国人投資家の動向を追う重要性
日本株市場では外国人投資家が大きな影響力を持っています。
特に5月以降の売買動向は、日本株全体の需給バランスに影響を与えるため注意が必要です。
過去には外国人投資家が大量に買い越したことで、日経平均株価が予想外に上昇したケースもあります。
外国人投資家の動向を把握することで、「セルインメイ」に基づく戦略の修正が可能になります。

セルインメイを無視すべき理由と代替戦略

この章ではセルインメイを無視すべき理由と代替戦略について解説します。
「セルインメイ」を無視しても良い理由とは?
「セルインメイ」は、5月に株を売るべきという相場格言です。
しかし、日本市場ではこのアノマリーを無視しても問題ありません。
その理由を詳しく見ていきましょう。
日本市場ではアノマリーが機能しづらい背景
日本の株式市場では、「セルインメイ」効果が米国ほど顕著ではありません。
上記で示した通り、5月の勝率は高く、ここ最近は勝ちが続いています。
これは、日本特有の要因が影響しているのです。
例えば、日本の夏休みは米国に比べて短く、投資家の行動パターンが異なります。
また、日本企業の決算発表時期が5月から6月に集中することも、相場の動きに影響を与えています。
長期的なトレンドを重視した方が良い理由
短期的なアノマリーよりも、長期的な企業の成長性や市場動向に注目することが重要です。
企業のガバナンス改革や収益性の向上が進んでおり、これらの長期的なトレンドを捉えることが投資成功の鍵となるでしょう。
例えば、日本企業の株主還元策の強化や、デジタル化による生産性向上などが、今後の株価上昇を支える要因となります。
「セルインメイ」を無視した場合のおすすめ戦略
「セルインメイ」に囚われず、より効果的な投資戦略を考えてみましょう。
以下に、具体的な方法を紹介します。
配当利回り重視の銘柄選び
高配当株に注目することで、安定的なリターンを得られる可能性があります。
日本の株式市場では、配当利回りの高い銘柄が増えています。
夏場に強い業種への分散投資
季節性を考慮した業種別の投資も効果的です。
夏場に業績が好調な業種に注目しましょう。
具体的には以下のような業種が挙げられます:
-
飲料・食品業界:
暑い季節に需要が高まるアイスクリームや清涼飲料水関連の企業 -
電力・ガス業界:
エアコン使用増加による電力需要の高まりから恩恵を受ける企業 -
レジャー・旅行業界:
夏休みシーズンに需要が増加するホテルや旅行会社
これらの業種に分散投資することで、ポートフォリオの安定性を高めることができます。
さらに、長期的な視点で見ると、技術革新や人口動態の変化などのメガトレンドに注目することも重要です。
例えば、AI(人工知能)や脱炭素化関連の企業は、今後の成長が期待できる分野です。
以上の戦略を組み合わせることで、「セルインメイ」に囚われない、より効果的な投資アプローチが可能となります。

まとめ

ポイント
- 「セルインメイ」は、5月に株を売り夏場の低調な市場を避ける投資戦略である。
- 日本市場では、「セルインメイ」の効果が米国ほど顕著ではなく、5月以降も上昇する年が多い。
- 日本特有の要因として、3月決算後の業績発表やお盆休みなどが株価に影響を与える。
- 過去データでは、5月の勝率は高く、直近5年間は好調。
- トレードスタイルが長期では、「セルインメイ」に頼るより、長期的なトレンドや配当利回り重視の戦略が有効となる。
セルインメイについて説明してきました。
5月に株を売った方がいいという格言ですが、データで見てみると5月は上昇する確率が多高いという結果が出ました。
夏枯れ相場を回避するために5月に売ってしまっても問題ないですが、5月に株価が下がりやすいという認識は誤りでしょう。
あくまでもアノマリーの一つなので、その時の状況によって株価の動きは変わってきます。
アノマリー、経済状況、チャート、業績等、様々な材料を使って勝率を上げていきましょう。


参考:
