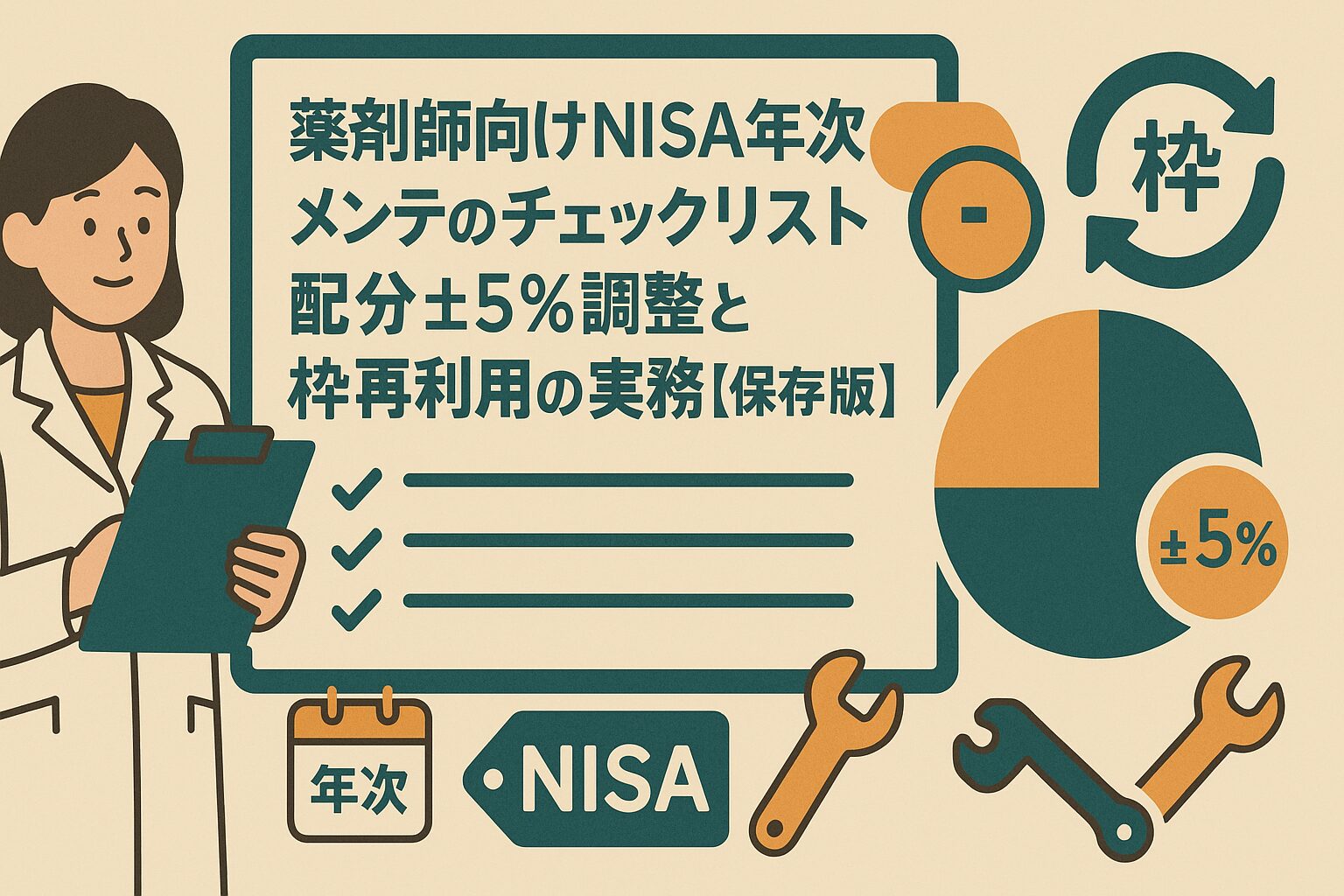この記事は、NISA運用の年次メンテ(棚卸し)を、薬剤師の働き方に合わせて最短で終わらせるための手順をまとめた「実務ガイド」です。
配分のズレを±5%で整えつつ、翌年の非課税枠(簿価ベース)再利用の考え方まで整理します。
基礎の復習は👉 ドルコスト平均法の基礎、商品選びは👉 薬剤師のNISA商品ガイド をどうぞ。
\まずは非課税×積立の「土台」を準備/
年次メンテは「年1回・30分」でOK



頻度とタイミングの決め方
- 頻度は年1回に固定(臨時は暴落プレイブックに従う)。
- タイミングは「給与やボーナスの直後」「年末調整の前後」など、家計の区切りと合わせる。
- 夜勤前後は避け、落ち着いて30分確保できる日に行う。
関連:配分の考え方は👉 リスク許容度×配分テンプレ
事前準備(必要なのはこの4つ)



チェックする書類・画面
- 証券口座の評価額と商品ごとの比率(スクショでOK)。
- 年間の積立設定(金額・日付・クレカ積立)。
- 自分の目標配分(例:全世界70%+S&P50030%)。
- 当年のNISA残枠と使用計画。
設定の見直し方法:👉 SBIで投信の自動積立(NISA)設定
配分チェック:±5%乖離で軽く整える



乖離の測り方と戻し方
| 項目 | 例(目標) | 現状 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 全世界株 | 70% | 66%(-4%) | 放置(許容範囲内) |
| S&P500 | 30% | 35%(+5%) | 来年の積立配分を全世界>S&P500に微調整 |
※スマホでは表が画面幅を超えます。横にスワイプしてご覧ください。
基本は「売って合わせる」より「将来の積立配分で戻す」。
課税も発生せず、手間も少ないです。
大きく崩れたときの動きは👉 薬剤師のNISA暴落プレイブック を参照。
NISA枠の使い切り&翌年再利用の考え方



当年の使い切りと翌年の復活
- 当年は「毎月の積立+ボーナス時の増額」で計画的に使い切る。
- 年間投資枠・非課税保有限度額はいずれも簿価(取得金額)ベースで管理。
- 当年に売却して空いた枠は、翌年以降に簿価相当額が復活。
- 同年の年間投資枠に上乗せは不可(当年中は増えない)。
【補足】NISA口座の金融機関変更は概ね「前年10/1〜変更年9/30」が手続き期間です。
その年にNISAで買付があると変更不可の取扱いが一般的です。
変更前口座での売却で空いた非課税保有限度額を再利用できるのは、変更後のNISA口座に限られます。
関連:使い分けは👉 iDeCo×NISAの戦略
\来年の配分と積立も、このタイミングで整える/
積立設定の見直しポイント



4チェック(最短版)
- 金額:生活を圧迫しない範囲で、来年も続く水準に。
- 日付:給与日直後に固定して資金繰りストレスを削減。
- 配分:±5%乖離を将来の積立で戻す設計に。
- コスト:同指数でより低コストが出ていないか確認(例:eMAXIS Slim/SBI・V)。
設定手順:👉 SBIの積立設定ガイド
売却のルール:原則は「最小限」



売却が必要な例だけ覚える
- 誤発注・重複商品の整理。
- 明確にコスト劣位な商品からの乗り換え(同指数・長期で差が出る場合)。
- リスク許容度の変更(結婚・出産・住宅など、大きなライフイベント時)。
注意:売却で枠が空いても同年内は上乗せ不可。
翌年の復活枠で再設計する。
関連:👉 初心者がやりがちな失敗と回避法
記録テンプレ:3行で終わる運用メモ



そのまま使える3行テンプレ
【年次メンテ:YYYY/MM/DD】 ・評価額:〇〇万円(全世界◯%/S&P500◯%/その他◯%) ・来年の積立:合計◯万円/月(全世界◯%・S&P500◯%・その他◯%) ・メモ:乖離△%→積立配分で戻す(売却なし)
よくある質問(Q&A)
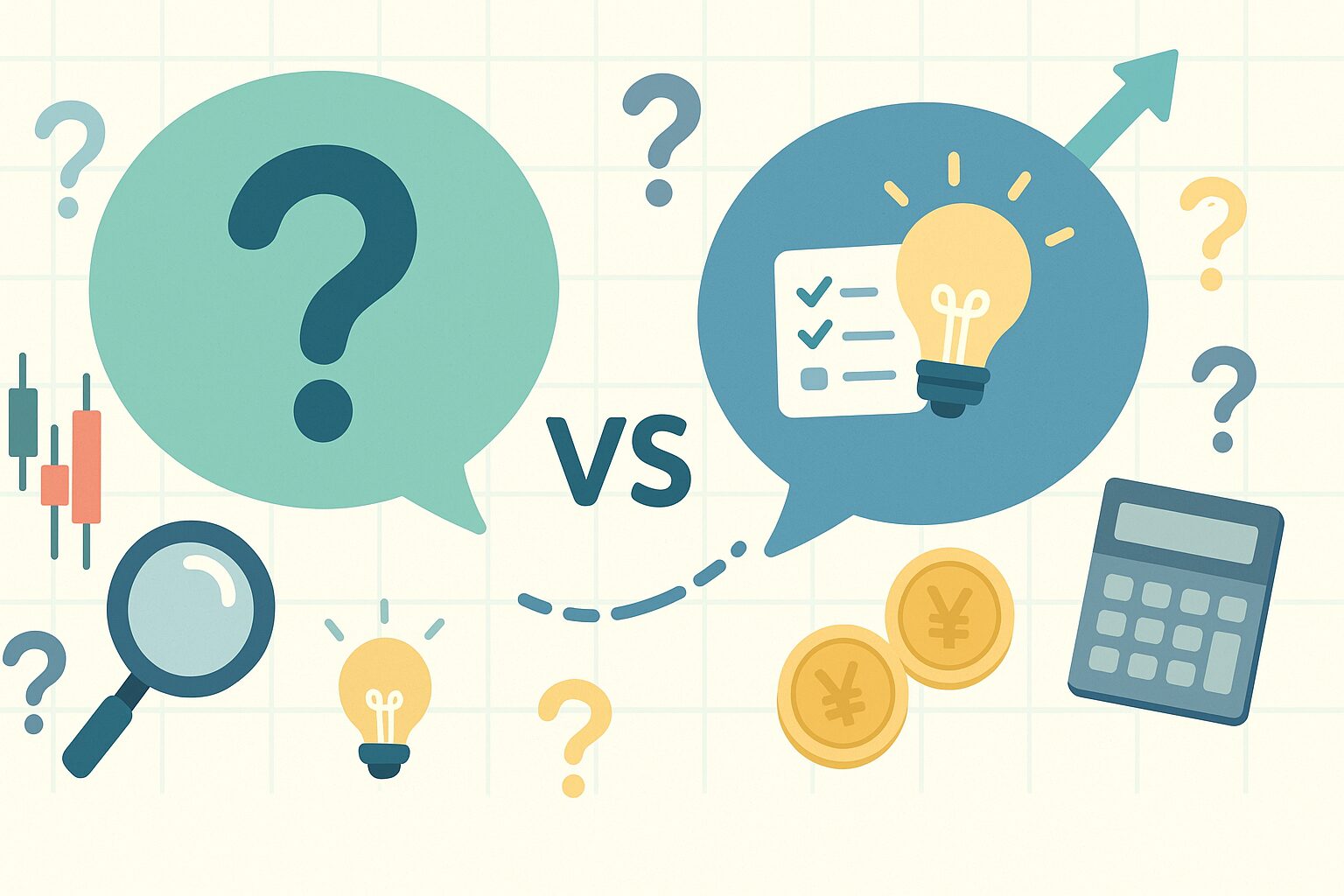
Q1. 年2回に増やしたほうが良い?


Q2. クレカ積立はどうする?
獲得上限や締切に合わせて金額を設定し直すだけでOK。
ポイントは再投資に回すと効率的。
Q3. 暴落時は別ルール?
年次メンテとは別で、“暴落プレイブック”の手順に従う(公開後リンク)。
当日の情報収集は15分上限、買い増しは金額固定が基本。
まとめ

ポイント
- 年1回・30分でOK。配分のズレは±5%目安で整える。
- 売却は最小限、将来の積立配分で戻す。
- 当年の枠は計画的に消化、売却枠は翌年(簿価)に復活する前提で設計。


\まずはNISA口座の準備から/
👉 次のステップ:下落相場の行動ルール
👉 併せて読みたい:
参考:
※「±5%でリバランス」は海外大手の解説でも示される一般的な閾値です(例:Fidelity、Schwab、Morningstar)。
なおVanguardの研究は「年1回リバランス」も合理的と示唆しており、頻度は年1回+乖離目安での併用が実務的です(Vanguard研究PDF)。