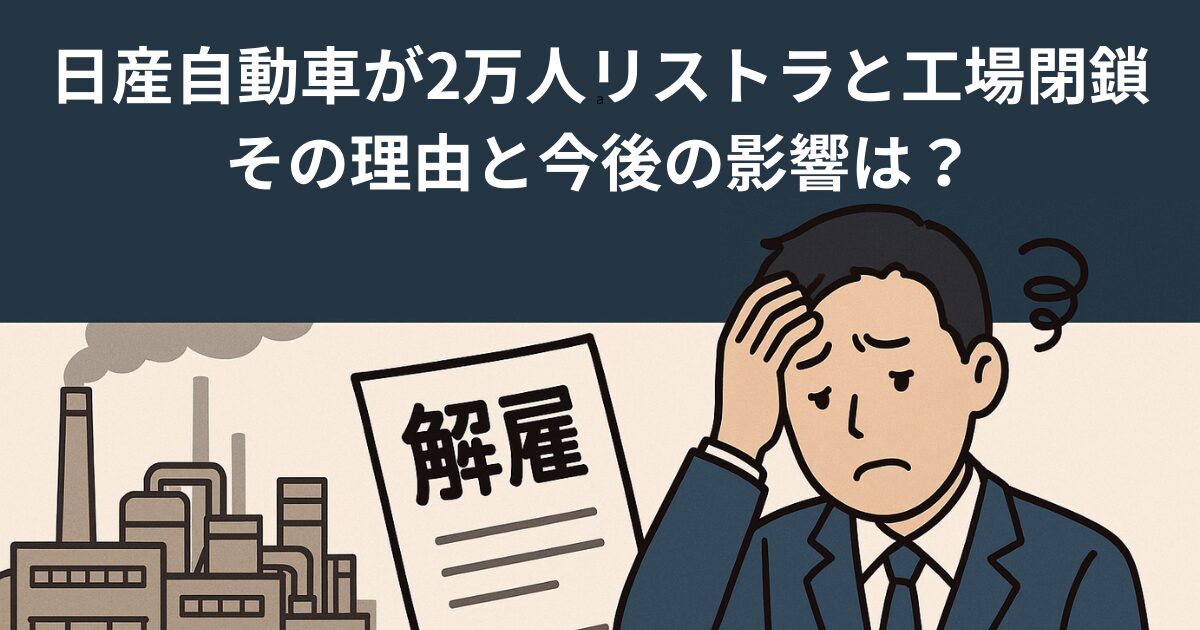日産自動車は2025年5月、世界で2万人の人員削減と7工場の閉鎖を発表しました。
この大規模リストラは、2027年度までに段階的に実施され、全17工場を10工場体制に再編する方針となっています。

背景には、北米や中国での販売不振や業績悪化があり、コスト削減と生産体制の見直しが急務となっている状況です。
国内では神奈川県の追浜工場と湘南工場が閉鎖候補となり、地域経済や雇用への影響が大きく懸念されています。
公式発表後、従業員や地域社会からは不安や戸惑いの声が広がり、今後の日産の再建策や日本の自動車産業全体への影響が注目されています。

ポイント
- 日産自動車は2025年5月、世界で2万人の人員削減と7工場閉鎖を発表する。
- 今回のリストラは2027年度まで段階的に実施し、全17工場を10工場体制に再編する方針である。
- 業績悪化や販売不振が背景にあり、コスト削減と生産体制の見直しが急務となる。
- 神奈川県の追浜・湘南工場などが閉鎖候補となり、地域経済や雇用への影響が懸念される。
- 公式発表後、従業員や地域社会から不安の声が広がり、今後の再建の行方が注目される。
日産自動車が発表した2万人リストラと7工場閉鎖の概要

この章では日産自動車が発表した2万人リストラと7工場閉鎖の概要について解説します。
リストラと工場閉鎖の発表内容まとめ
2025年5月、日産自動車は世界規模で2万人の人員削減と7工場の閉鎖を発表しました。
このリストラ策は、2027年度までに段階的に実施される計画です。
「Re:Nissan」と名付けられた経営再建プランの一環で、全17工場のうち7工場を閉じ、10工場体制に再編します。
赤字が続く中、コスト削減と生産体制の見直しが急務となりました。
日産は、サプライチェーンの効率化や取引先の再編も同時に進める方針です。
この発表は、国内外の自動車業界や関係者に大きな衝撃を与えています。
対象となる従業員と工場の規模
今回のリストラ対象は、日産グループ全体の従業員の約15%に相当する2万人です。
製造部門だけでなく、管理部門や研究開発部門も含まれます。
工場閉鎖は、国内外の主要拠点が対象となり、特に日本国内では神奈川・福岡・栃木などの工場が候補に挙がっています。
福岡県苅田町など、地域経済への影響も懸念。
日産は、工場の統廃合だけでなく、パワートレイン工場の縮小やシフト調整、設備投資の抑制も進める予定です。
従業員の再配置や退職支援策については、今後詳細が示される見通しです。
公式発表と報道の反応
日産の公式発表では、「業績悪化が想定以上に進み、従来の対応では不十分と判断した」と説明されています。
社長のイバン・エスピノーサ氏は、持続可能な経営体制への転換を強調しました。
国内外の報道では、今回のリストラ規模が過去25年で最大級である点や、1999年のゴーン改革以来の大転換との指摘が目立ちます。
一方、工場閉鎖の詳細が明かされていないため、従業員や取引先、地域社会からは不安や戸惑いの声が広がっているのが現状です。
今後の雇用や地域経済への影響、日産の再建が本当に実現するのかが注目されています。

日産リストラの背景と経営再建「Re:Nissan」計画の狙い

この章では日産リストラの背景と経営再建「Re:Nissan」計画の狙いについて解説します。
業績悪化と過剰生産能力の現状
日産自動車は2024年度決算で約6700億円という巨額赤字を計上し、経営危機に直面しています。
この背景には、北米や中国など主力市場での販売不振が大きく影響しています。
例えば、北米ではハイブリッド車やEVの需要拡大に十分対応できず、トヨタやホンダなどの競合にシェアを奪われました。
中国市場でも現地メーカーの台頭とEV市場の急成長に乗り遅れ、2024年度の販売台数は大きく落ち込んでいます。
こうした状況の中で、生産設備が過剰となり、世界で約500万台の生産能力を持ちながら実際の販売は大きく下回る状態が続いてきました。
過去にも1999年の「日産リバイバルプラン」時に大規模なリストラを経験しましたが、今回の規模はそれに匹敵するものです。
EV市場での競争力低下
かつて「リーフ」などでEV市場をリードした日産ですが、最近は競争力が大きく低下しています。
アメリカではハイブリッド車や新型EVのラインナップが不足し、テスラやBYD、トヨタなどの他社に大きく差をつけられています。
中国では新興EVメーカーの急成長と政府のEV普及策によって、日産の従来型ガソリン車や既存EVが苦戦。
新型車の投入遅れやモデルチェンジの間隔が長くなったことで、消費者から「売れるクルマがない」と指摘されることも増えました。
EV分野での遅れは、今後の成長戦略に大きな課題となっています。
「Re:Nissan」計画の主な施策
「Re:Nissan」計画は、2026年度までの黒字化を目指す大規模な経営再建策です。
その柱は「コスト削減」「戦略の再定義」「パートナーシップの強化」の3つに分かれています。
具体的には、2024年度比で5000億円のコスト削減を掲げ、変動費・固定費をそれぞれ2500億円ずつ削減する目標を立てました。
また、17あった工場を2027年度までに10に統合し、生産体制を大幅に見直します。
人員削減もグローバルで2万人規模となり、開発部門や管理部門も含めて抜本的な構造改革を進めています。
生産体制の見直し
生産体制の見直しでは、稼働率の低い工場や採算の合わない拠点を中心に、国内外で7工場を閉鎖します。
北九州市で予定されていたバッテリー工場の建設も中止となりました。
生産拠点の統合によって物流や設備投資の効率化を図り、無駄なコストを徹底的に削減。
また、プラットフォーム(車の基本構造)の種類も13から7に減らし、部品の共通化と生産のシンプル化を進めます。
これにより、開発期間の短縮や新型車投入のスピードアップも狙っています。
サプライチェーン改革
サプライチェーン改革では、部品調達から製品出荷までのプロセスをデジタル化し、在庫や物流の最適化を進めます。
サプライヤー(部品供給会社)を厳選し、より少数の取引先と大量発注することでコストを抑える方針です。
また、需要予測の精度を高めるために先進的なシステムを導入し、サプライヤーとリアルタイムで情報共有できる仕組みを構築します。
これにより、部品の過剰在庫や納期遅延などのリスクを減らし、グローバルで安定した生産体制を目指しています。
サプライチェーン全体の効率化は、今後の収益力強化に直結する重要なテーマです。

国内工場閉鎖の具体的対象と地域への影響

この章では国内工場閉鎖の具体的対象と地域への影響について解説します。
閉鎖・縮小が予定される工場一覧
日産自動車は、神奈川県横須賀市の追浜工場と、平塚市にある子会社・日産車体の湘南工場の閉鎖を検討しています。
追浜工場は1961年に操業を開始し、現在は主にコンパクトカー「ノート」などを生産しています。
従業員は約3,900人で、生産能力は年間24万台。
湘南工場では商用バン「AD」や「NV200バネット」などが製造されてきましたが、すでに「ADバン」の生産終了が決定し、従業員は約1,200~1,800人となっています。
この2工場は、日産の国内生産能力の約30%を占めており、閉鎖されれば神奈川県から完成車工場が消えることになります。
今後は、栃木工場や九州の工場が国内拠点として残る見通しです。
地域経済・雇用への影響
追浜工場と湘南工場の閉鎖が実現した場合、直接雇用されている5,000人以上の従業員だけでなく、部品メーカーや運送会社など多くの関連企業にも影響が及びます。
例えば、工場周辺の飲食店や小売店は、従業員やその家族を主な顧客としてきたため、売上減少が懸念されます。
また、サプライチェーン全体に波及し、地域の経済活動が縮小する可能性も否定できません。
一方で、日産としては経営再建のために避けられない改革と位置付けており、痛みを伴う決断であることが強調されています。
地元住民や自治体からは「雇用や生活への影響が心配」という声が多く上がっています。
自治体や地域企業の対応策
神奈川県や横須賀市、平塚市などの自治体は、日産の発表を受けて状況を注視しつつ、相談窓口の設置や影響を受ける中小企業への支援策を検討しています。
小泉進次郎元環境相は「国を挙げて万全のサポート体制を敷く必要がある」と発言し、国・自治体・経済団体が連携して雇用や地域経済の下支えを進める意向を示しました。
また、福岡県苅田町や北九州市など、他の工場を抱える自治体も「恐れるより備える」という姿勢で、未来産業への転換や相談体制の強化を図っています。
今後は、再就職支援や事業転換のサポートなど、具体的な対策が求められる局面に入っています。

日産の今後の成長戦略と自動車業界への波及効果

この章では日産の今後の成長戦略と自動車業界への波及効果について解説します。
EV・次世代車戦略の方向性
日産は今後の成長戦略として、電気自動車(EV)と次世代車の開発・販売強化に大きく舵を切っています。
2025年度から2026年度にかけて、3代目となる新型リーフを筆頭に、コンパクトEV「マイクラ」や新型「ジュークEV」など、複数の新型電動車を世界各地で投入する予定です。
新型リーフは従来のハッチバック型からクロスオーバーSUVへと刷新され、航続距離の大幅な向上や、テスラスーパーチャージャーへの対応など、最新のEV技術を搭載します。
また、第3世代e-POWERやプラグインハイブリッド(PHEV)も投入し、消費者の多様なニーズに応えるラインナップを拡充する方針です。
北米や欧州では現地の規制や市場ニーズに合わせたモデル展開を進め、EV市場での競争力回復を目指しています。
こうした動きは、「売れるクルマが無い」という現状打破を狙ったものです。
グローバル提携の動向(ルノーなど)
日産は経営再建の柱として、グローバルパートナーシップの強化にも注力しています。
2025年3月にはルノーと新たなアライアンス契約を締結し、インド事業の再編や小型EVのOEM供給など、協業領域を拡大しました。
自動車業界全体への影響
日産の大規模リストラと成長戦略の転換は、日本の自動車業界全体に大きな波紋を広げています。
EVや自動運転などの次世代技術へのシフトが加速し、トヨタやホンダなど他の大手メーカーも競争戦略の見直しを迫られる状況です。
一方で、工場閉鎖や人員削減による地域経済への影響、サプライチェーンの再編による取引先企業への負担増など、課題も山積みです。
今後は、業界全体での協業や再編が進む一方、消費者のニーズに応える新たな価値創造が求められる局面に入っています。

従業員・取引先への影響と支援策の展望

この章では従業員・取引先への影響と支援策の展望について解説します。
従業員の再就職支援と退職金制度
今回の日産自動車による2万人規模の人員削減では、再就職支援や早期退職優遇策がセットで用意されています。
日本国内でも、早期退職募集や再就職支援が実施され、退職金制度は確定給付企業年金と確定拠出年金を組み合わせた仕組みへと移行しています。
従業員が新しいキャリアに踏み出しやすいよう、個別相談や職業訓練も提供される見込みです。
取引先企業への支援と再編
日産の大規模リストラは、約2,000社にのぼる取引先企業にも大きな影響を与えます。
2025年には、原材料高騰などで苦しむサプライヤーに対し、日産が1,000億円規模の支援策を公表しました。
この支援は、仕入れ価格の一部を日産が負担することで、下請け企業の経営負担を軽減する内容です。
日産は、サプライヤーとの信頼関係を維持しつつ、持続可能な成長を目指すと表明しています。
一方で、取引の見直しや淘汰が進むため、サプライヤー側も新たなビジネス機会を模索する必要があります。
今後の雇用・ビジネスチャンス
大量リストラにより、雇用不安が広がる一方で、新たなビジネスチャンスも生まれています。
日産はEV(電気自動車)や自動運転技術など、成長分野への投資を強化しているのです。
今後は、EV関連部品やソフトウェア開発、再生可能エネルギー事業などで新規雇用が期待されます。
また、グローバルなサプライチェーン再編により、海外市場での人材需要も拡大する見通しです。
サプライヤーや地域企業は、日産以外の自動車メーカーや異業種との連携を深めることで、新たな取引先を開拓できる可能性があります。
従業員や取引先が変化をチャンスと捉え、スキルアップや事業転換に積極的に取り組むことが、今後の安定につながります。

まとめ

ポイント
- 日産自動車は2025年5月、世界で2万人の人員削減と7工場閉鎖を発表する。
- 今回のリストラは2027年度まで段階的に実施し、全17工場を10工場体制に再編する方針である。
- 業績悪化や販売不振が背景にあり、コスト削減と生産体制の見直しが急務となる。
- 神奈川県の追浜・湘南工場などが閉鎖候補となり、地域経済や雇用への影響が懸念される。
- 公式発表後、従業員や地域社会から不安の声が広がり、今後の再建の行方が注目される。
今回は日産自動車の2万人リストラと工場閉鎖について説明してきました。
このニュースは日産自動車だけでなく、日産に関わる企業や人々にもとてつもない影響があるものです。
投資家目線でも日産単体ではなく、自動車業界や自動車関連の企業に大きな影響があるので、注視しなければならない内容でしょう。
ここから日産自動車がどの方向に行くのかはわかりませんが、何とか立て直し、強い日産を取り戻してほしいものです。


参考: