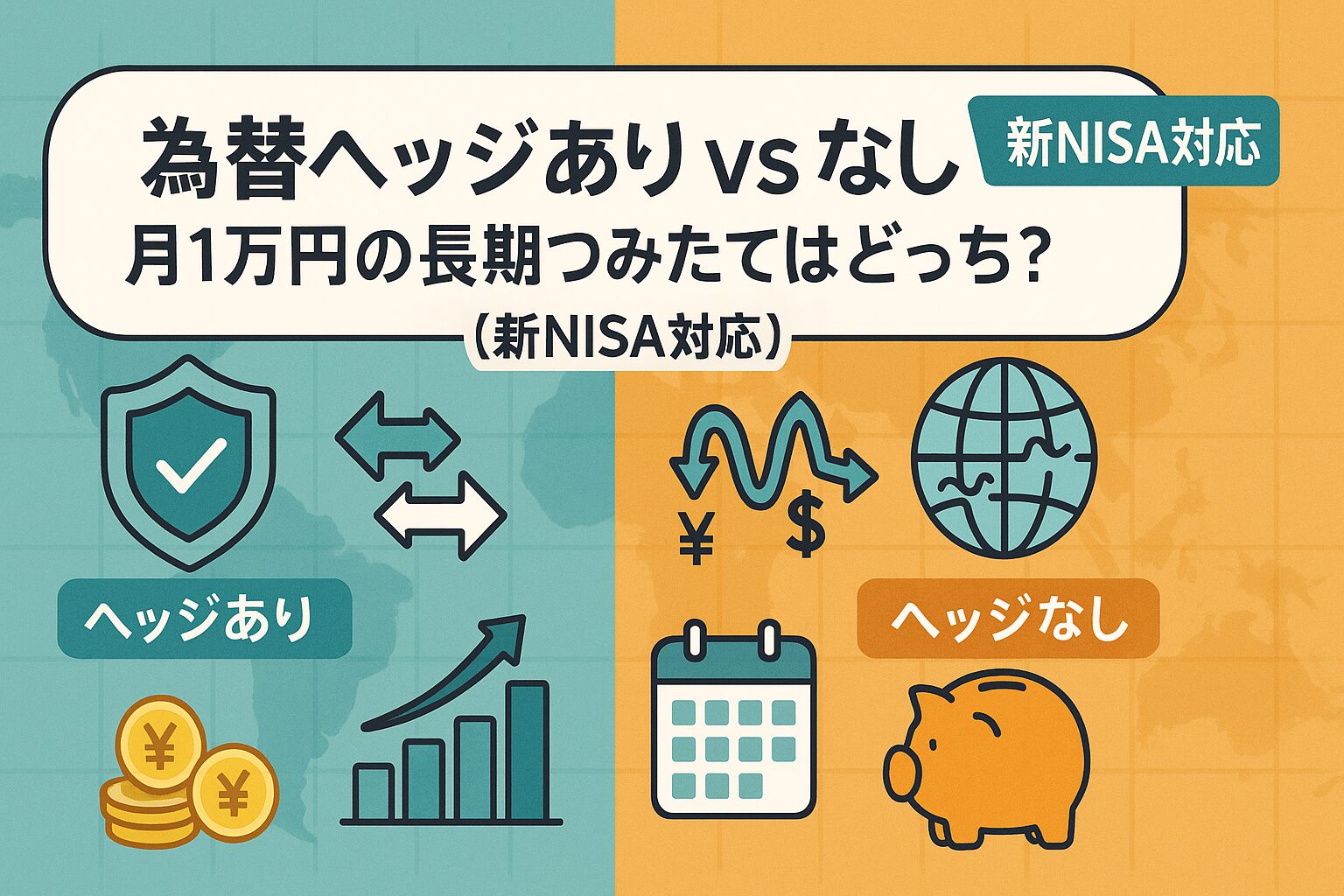この記事では、為替ヘッジ「あり」vs「なし」の選び方を初心者向けに整理します。
違いの早見表、月1万円の実務フロー、ケース別の最適解、よくある誤解Q&A、つまずきと処方箋までを新NISA前提で解説。
基礎は全世界 vs S&P500、選び方の要件はつみたて枠の基準も参照してください。
\まずはNISA口座の準備から/
ヘッジの基本と結論|なぜ株式は「なし」が基本か



- ヘッジなし:為替も含めて世界の成長を取りに行く。
長期の株式つみたての王道。 - ヘッジあり:円評価のブレは抑えやすい。
ただしヘッジコストと再平衡の手間を考慮。
短中期目標や心理安定を優先するときに部分的に。
※為替ヘッジは短期の通貨変動を中立化する一方、金利差由来のコスト(/収益)が発生します。
コスト水準は金利環境で変動します。
違いの早見表



| 項目 | ヘッジなし | ヘッジあり |
|---|---|---|
| リターンの源泉 | 株価上昇+為替変動。 | 株価上昇(為替影響を中立化)。 |
| 価格のブレ | 為替でブレやすいが、長期では寄与が相対的に縮小。 | 円評価は安定しやすい。 |
| コスト | 信託報酬のみ(相対的に低い)。 | 信託報酬+ヘッジコスト(相対的に高い)。 |
| 向いている人 | 長期(10年以上)で世界の成長を取りたい人。 | 数年内の目標や円評価の安定を重視する人。 |
| 組み合わせ | メインに据えやすい。 | 部分的に混ぜる(目安20〜40%)。 |
※スマホでは表が画面幅を超えます。
横にスワイプしてご覧ください。
👉 国内ETF vs 米国ETFの比較
👉 米国ETFの手数料・為替の実務
月1万円の実務フロー|迷ったら“なし”で仕組み化
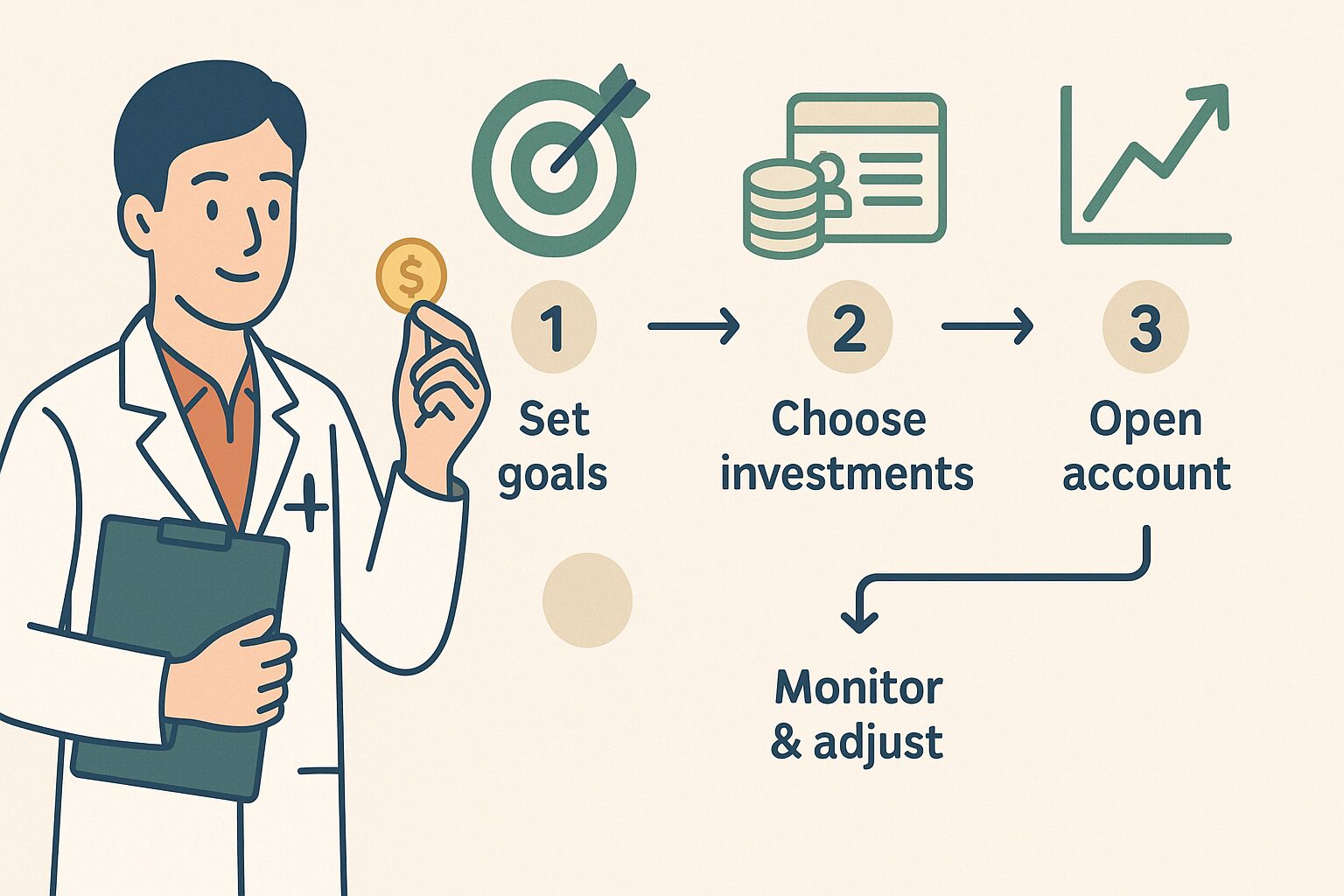


- つみたて投資枠で、低コストの全世界 or 米国株インデックス「ヘッジなし」を1本選ぶ。
- 毎月1万円(最初は100円で動作確認 → 即1万円へ)に設定。
- 価格や為替を見ないため、積立日は給料日翌営業日に固定。
- どうしても為替が不安なら、“ヘッジあり”を20〜40%だけトッピング。
- 半年ごとに「信託報酬・実質コスト・トラッキング誤差・資金流入」を点検。ズレは買い増しで戻す。
※ヘッジコストは主に金利差で決まり、相場環境で増減します。
直近の円⇄米ドル環境では年率数%規模の負担との推計もあります(将来は変動)。
\つみたては仕組み化が9割/
最短で仕組み化へ 👉 SBI証券の口座開設と初期設定
ケース別の選び方(目的・性格で決める)



老後資金・教育資金など長期(10年以上)
ヘッジなしを主軸(〜100%)。
世界の成長を取りに行き、コストを最小化。
3〜5年以内に使う留学・住宅頭金など
“ヘッジあり”を20〜50%混ぜて円評価を安定化。
残りはヘッジなし+円預金(安全資産)でバランスを取る。
心理的に為替が気になってしまう人
“ヘッジあり 20〜30%”の安心料を払いつつ、習慣化を優先。
慣れてきたら比率を段階的に下げる。
👉 日本株 vs 米国株の配分
👉 全世界 vs S&P500
👉 インデックス vs アクティブ
よくある誤解Q&A

Q1.今は円高/円安だから“あり”or“なし”が得ですよね?
A.短期の為替当てはプロでも難しいです。
つみたては時間分散(DCA)で“当てに行かない”設計が合理的です。
Q2.“あり”の方が必ず安全ですか?
A.円評価のブレは抑えられますが、ヘッジコストが発生します。
長期の株式では、その分だけ期待リターンを押し下げ得ます。
Q3.債券は“あり”、株式は“なし”が良いって本当?
A.一般論として、先進国の高格付け外債は“ヘッジあり”が主流(主要リスクは金利で、通貨ボラは抑える設計)。
株式は成長を取りに行く資産なので、“なし”が基本という役割分担です。
※DCAはタイミング誤りのリスクを減らす一方、期待値だけ見れば一括投資が優位な期間も確認されています。
継続しやすい方法を最優先に。
つまずきと処方箋



- 積立と配分は固定。
ぶれた配分は買い増しで戻す(売却は年1回の点検で十分)。 - “ヘッジあり”を入れるなら、比率の上限を先に決める(例:最大30%)。
- 四半期ごとに「コスト・乖離・資金流入・ヘッジ比率」を記録する。
記録=継続のスイッチ。
まとめ

ポイント
- 長期の株式つみたては「ヘッジなし」が基本。
不安が強い・目標が近いなら“あり”を20〜40%だけ。 - 自動積立×配分固定×買い増しで戻すで“やめない”。
- 債券はヘッジありが主流。
役割で使い分ける。


\今日から一歩。つみたて設定まで一気に/
👉 次はこちら:リバランス完全ガイド