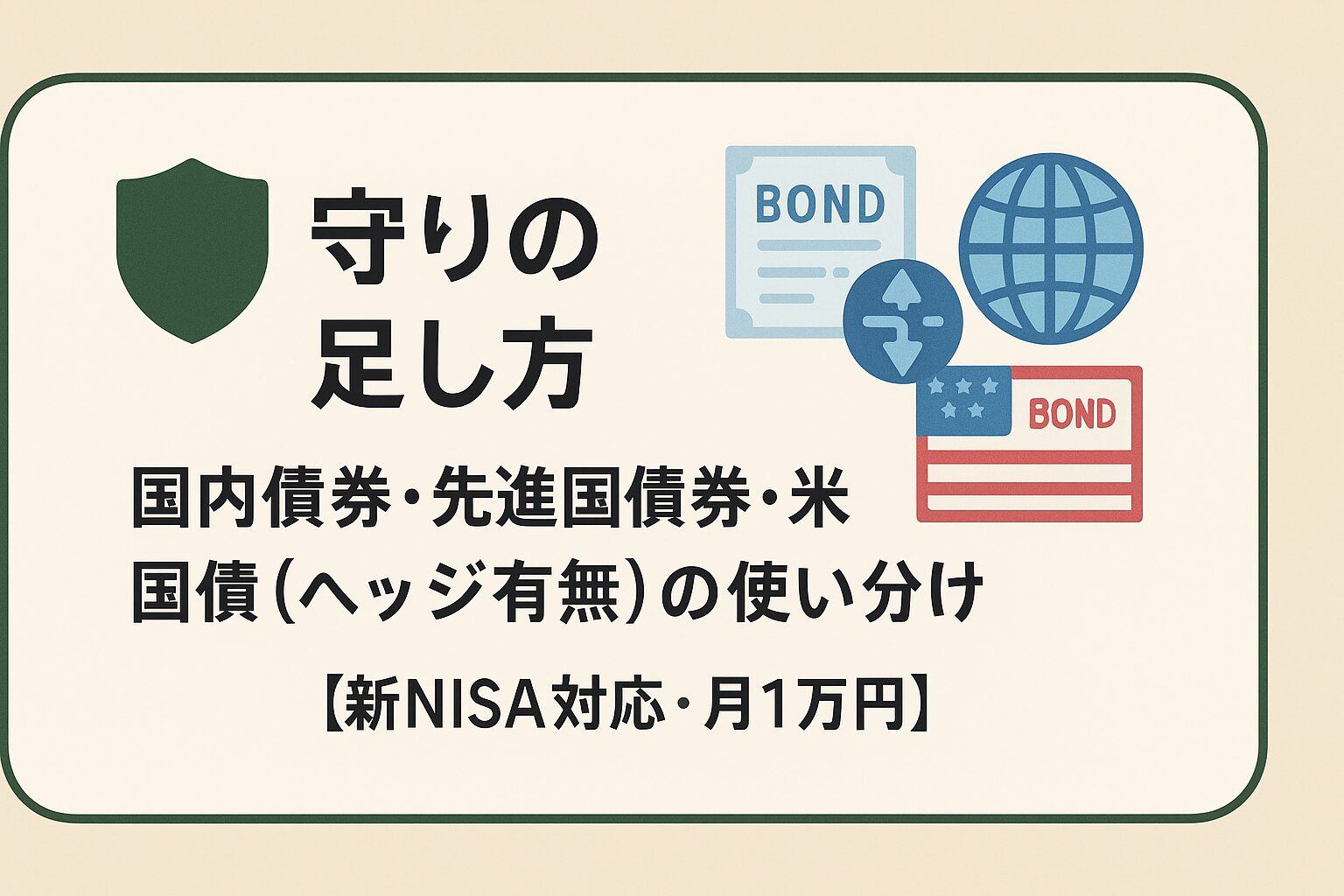この記事では、月1万円×新NISAを前提に、国内債券・先進国債券・米国債(ヘッジ有無)の使い分けを実務ベースで整理します。
各カテゴリの特徴とメリデメ、月1万円での配分テンプレ、つみたて投資枠・成長投資枠での買い方(対象商品の注意点)、やりがちなNGまでまとめました。
前提の積立設計はつみたて投資枠で買える投信の選び方、為替の考え方はヘッジあり・なしの比較も合わせてどうぞ。
\まずはNISA口座の準備から/
まず結論:迷ったらこの順で選ぶ



- ① 国内債券(円建て):為替リスクなしで値動きマイルド。最初の守りに最適。
- ② 先進国債券(為替ヘッジあり):海外金利を取り込みつつ、為替のブレを抑える中庸案。ヘッジコストは(金利差に応じて)発生。
- ③ 米国債(為替ヘッジなし):長期の通貨分散まで狙う攻守バランス。短期は為替の上下に揺れやすい。
👉 為替リスクの基礎はヘッジあり・なしで復習。
👉 総合設計はオルカン vs バランスも確認。
特徴を一枚で把握(比較表)

| カテゴリ | 通貨・為替 | 想定リスク | 期待リターン感 | 相場下落時の働き | 相性が良い人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内債券(円建て) | 円。為替リスクなし | 小さめ(デュレーション次第) | 控えめ | 下落時のクッションになりやすい | まずブレを抑えたい初心者 |
| 先進国債券(ヘッジあり) | 海外金利を円で受ける。為替は抑制(ヘッジコスト発生) | 小〜中 | 国内債券よりやや上も | 株と逆相関が効く局面もある | 為替は抑えつつリターンも少し欲しい |
| 米国債(ヘッジなし) | ドル。為替リスクあり | 中(金利+為替の二重ブレ) | 通貨ドリフトで上振れ余地も | 分散寄与は大きいが短期は荒れやすい | 通貨分散も長期で取りたい人 |
※本表は一般的性質の整理です。実際のリスク・リターン・コストは商品や期間で異なります。購入前に目論見書・運用報告書をご確認ください。
👉 「どれくらい入れるか」は次章のテンプレが目安。
👉 リスク調整はリバランスで“買い増しで戻す”が基本です。
月1万円の配分テンプレ(最初の6〜12か月)



| 型 | 配分(例) | 月1万円の目安 | こんな人に | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| A:守り0% | 株式100(オルカン等) | 株式 10,000円 | 成長を取り切りたい | ブレは大きい。生活防衛資金を厚めに。 |
| B:守り20% | 株式80+債券20(国内債券 or 先進国ヘッジ) | 株式 8,000円/債券 2,000円 | 最初の継続を重視 | 迷ったらここから。半年後に体感を評価。 |
| C:守り40% | 株式60+債券40(国内+先進国ヘッジを半々など) | 株式 6,000円/債券 4,000円 | 値動きに弱い・睡眠第一 | リターンは控えめになりやすい点は理解。 |
※債券部分を「国内:先進国ヘッジ=1:1」などに分けると偏りにくくなります。米国債ヘッジなしは為替ブレを受け入れられる人向け。
ポイント(配分の動かし方)
- 初期は守り20%から。半年運用して“眠れるか”で増減。
- ズレは原則買い増しで戻す(売却リバランスは最小限)。
- 増額設定(毎年+1〜3%など)と併用すると複利が効く。
実務フロー:つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け
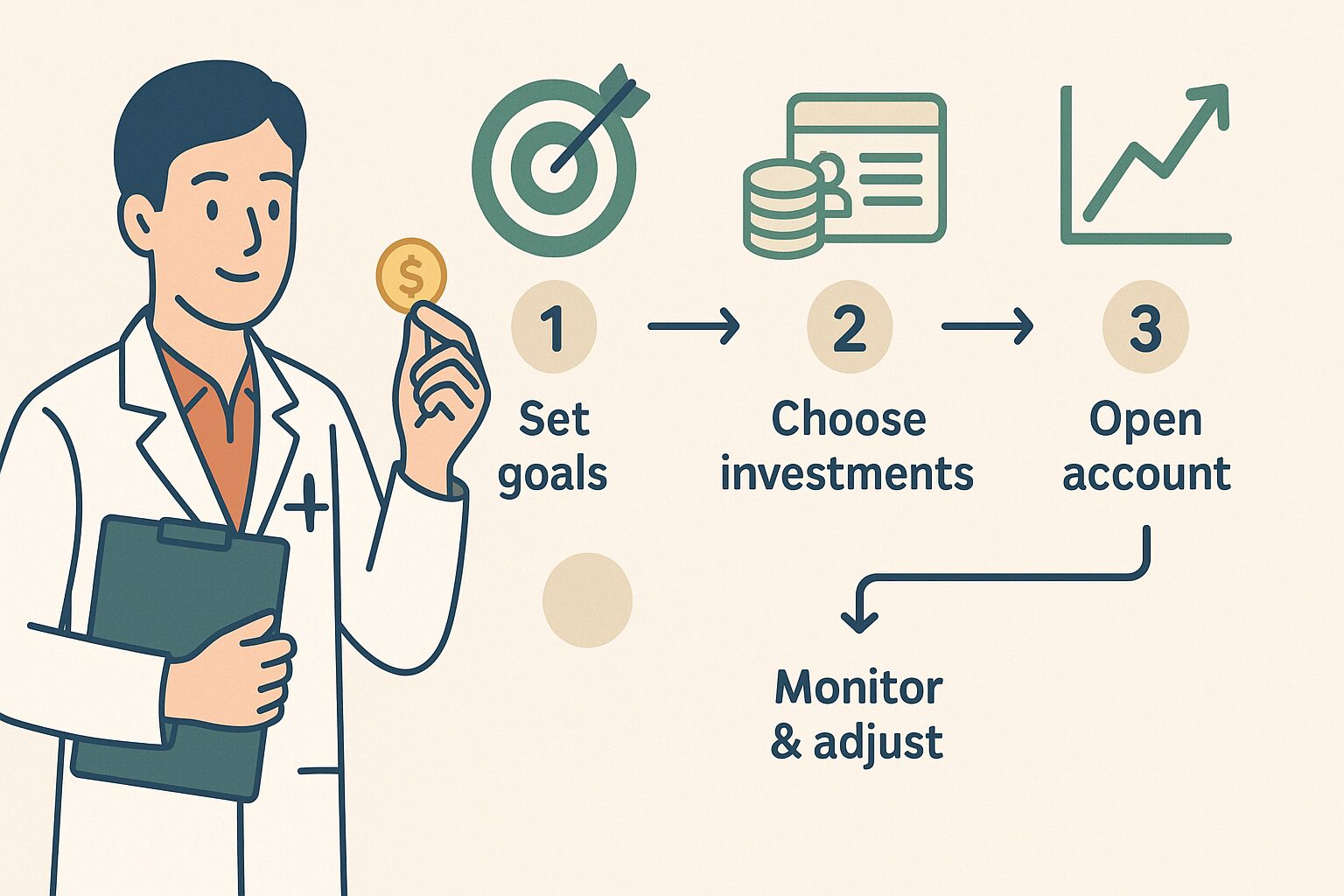


ステップ(5分で設定)
- 債券の役割を決める(国内でブレ抑制/海外金利を円で/通貨分散も狙う)。
- つみたて枠で信託報酬の低い投信を1本選定(国内 or 先進国ヘッジ)。
- 月1万円のうち守り分を設定(例:2,000円)。残りは株式へ。
- 成長枠を使うなら、米国債ETFや先進国債券ETFを少額スポットで補完(為替・スプレッド・売買手数料に留意)。
- 点検は年1回、乖離が大きければ“買い増しで戻す”。
※為替ヘッジは一般に二国間の短期金利差に相当するコスト(またはプレミアム)が乗ります。期間(デュレーション)が長い債券ほど金利変動に対する価格感応度は大きくなります。
年1回の点検と戻し方 👉 リバランス完全ガイド
\設定は数分で完了/
やりがちなNGと回避策

NG1:短期の為替で一喜一憂して頻繁に入れ替え
為替は読めません。
役割で持つと決めたら点検は年1回に固定。“買い増しで戻す”だけで十分です。
NG2:債券=“価格が動かない”と誤解
金利上昇局面では債券価格は下がり得ます。
デュレーション(期間)が長いほど価格感応度は高い点に注意。
目論見書で期間を確認しましょう。
NG3:毎月分配型や高コストのファンドを選ぶ
つみたて投資枠の趣旨は長期・積立・分散×低コスト×再投資。
毎月分配型やコスト高は原則外します。実質コスト(TER)は運用報告書で確認。
ポイント(NG回避のチェックリスト)
- 役割を明確化(ブレ抑制/海外金利/通貨分散)。
- つみたて枠=低コスト投信中心。一部ETFも対象だが、要件を確認。
- 成長枠は上場株式・ETF・REIT+一部投信。毎月分配型・一定のデリバ活用投信は除外。
よくある質問Q&A
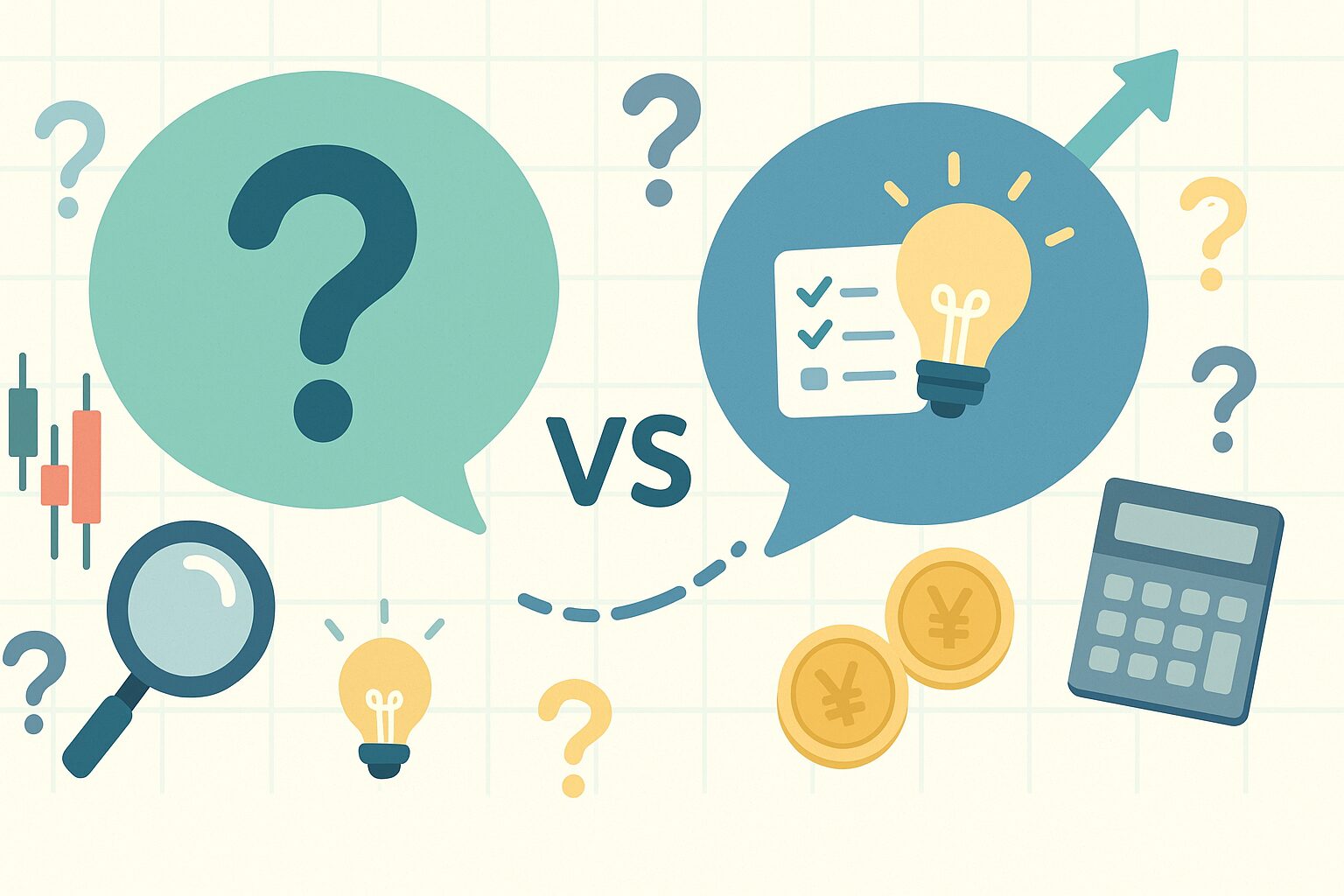
Q1.国内債券と先進国債券(ヘッジあり)、どちらが“より安全”ですか?
どちらも為替ブレを抑えられます。
国内は円金利、先進国ヘッジありは海外金利を円で受ける違い。
まずは国内→様子見→先進国ヘッジありを部分追加が無難。
Q2.米国債(ヘッジなし)は長期だと有利ですか?
長期の通貨分散には寄与する一方、短中期のブレは大きくなります。
守り目的の比率は控えめにし、体感リスクと相談しましょう。
Q3.リスク許容度が低い家族にはどの比率を勧める?
最初は守り20%(国内債券または先進国ヘッジあり)から。
半年続けて“続けられるか”で25〜30%へ微調整でもOK。
ポイント(今日からの実装)
- 守りは国内→先進国ヘッジ→米国債ヘッジなしの順で検討。
- 始めは守り20%、半年後に再評価。
- “止めない仕組み”は毎月×給料日翌営業日固定。増額設定も検討。
まとめ

ポイント(総まとめ)
- 迷ったら国内債券→先進国ヘッジ→米国債ヘッジなしの順で検討。
- 守り20%から開始、半年〜1年で体感を見て調整。
- 点検は年1回。ズレは買い増しで戻す。毎月分配型・高コストは回避。


\今日から一歩。役割で“守り”を足して続ける/
👉 次はこちら:リバランス完全ガイド