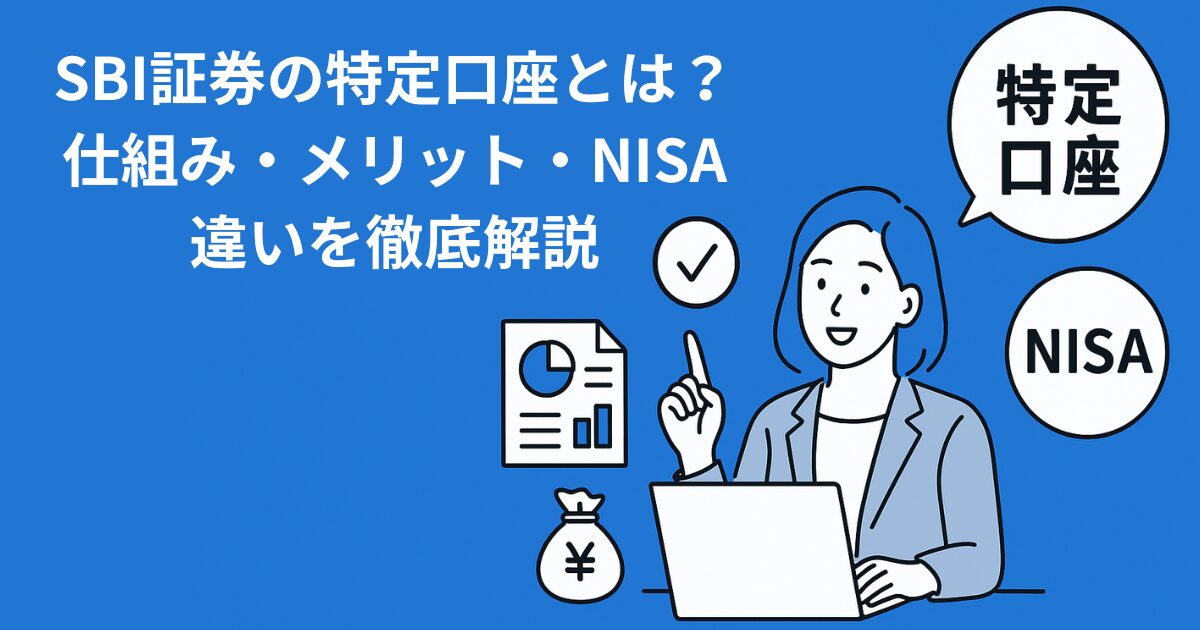投資を始める際、多くの人が悩むのが証券口座の種類です。
SBI証券の「特定口座」は、株式や投資信託などの取引で発生した損益を自動で計算し、年間取引報告書を作成してくれる便利な仕組みとなっています。
特に「源泉徴収あり」を選択すれば、税金が自動で差し引かれ、原則として確定申告を自分で行う必要がありません。
一方、「源泉徴収なし」を選ぶと、年間取引報告書をもとに自分で確定申告を行うことになります。

一般口座との最大の違いは、損益計算や税金の処理を証券会社が代行してくれるかどうかにあります。
取引できる商品は国内外の株式や投資信託など幅広いですが、FXや先物などは対象外となるため注意が必要です。
NISA口座は非課税枠がある一方、特定口座は課税口座である点も押さえておきたいポイントです。
初心者は「特定口座・源泉徴収あり」を選択することで、税金や申告の手間を大幅に減らすことができ、安心して投資を始められます。

ポイント
- 特定口座はSBI証券が損益計算や年間取引報告書の作成を代行する仕組みである
- 「源泉徴収あり」を選ぶと税金が自動で引かれ、原則として確定申告が不要となる
- 取引できる商品は国内外の株式や投資信託など幅広いが、FXや先物などは対象外である
- 一般口座やNISA口座との違いは、税金計算や申告の手間、非課税枠の有無にある
- 初心者は「特定口座・源泉徴収あり」を選択することで手続きが簡単となる
\口座開設は無料/
SBI証券 特定口座とは何か
最短ルートは、全体フローで道筋を確認してから必要な設定へ進むことです。
特定口座の基本的な仕組み
SBI証券の特定口座は、投資で発生した利益や損失を自動で計算し、年間取引報告書を作成してくれる便利な口座タイプです。
この年間取引報告書を使えば、確定申告の手間が大幅に減ります。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、源泉徴収ありを選ぶとSBI証券が税金を自動で差し引いて納付してくれるため、基本的に自分で確定申告をする必要がありません。
一方、源泉徴収なしの場合は、年間取引報告書をもとに自分で確定申告を行う必要があります。
一般口座との違いは、損益計算や税金の処理を証券会社が代行するかどうかにあります。
投資初心者にとって、税金の計算や申告の煩雑さを避けられる点が大きなメリットです。
SBI証券で特定口座を開設する方法
SBI証券で特定口座を開設するには、まず総合口座の申し込みが必要です。
新規で総合口座を申し込む際、同時に特定口座の開設も選択できます。
すでにSBI証券の総合口座を持っている場合は、WEBサイトの「口座管理」から「特定口座」の資料請求を行い、申込書と本人確認書類を返送する流れです。
手続きが完了すると、SBI証券のマイページに通知が届きます。
開設は無料で、難しい専門知識は不要です。
申し込み時は「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」「一般口座」から選択することになりますが、初心者は「源泉徴収あり」を選ぶと納税の手間が減り安心です。
手続きの途中で迷った場合でも、画面の案内やサポートがあるため、落ち着いて進めれば問題ありません。
特定口座で取引できる金融商品
SBI証券の特定口座では、幅広い金融商品を取り扱えます。
国内株式(現物・信用取引)、ETF、REIT、外国株式、投資信託、SBIラップ、国内債券、外貨建債券などが対象です。
例えば、日本株や米国株、人気の投資信託もすべて特定口座で管理できます。
一方、FX(外国為替証拠金取引)や先物オプション、CFD、金・銀・プラチナなどの商品は特定口座の対象外です。
これらの商品を取引したい場合は、別途一般口座や専用口座が必要となります。
投資初心者は、まず特定口座で株や投資信託など基本的な商品から始めるのが安心です。

SBI証券 特定口座のメリット・デメリット
この章では特定口座のメリット・デメリットについて解説します。
特定口座の主なメリット
SBI証券の特定口座は、投資初心者にとって非常に使いやすい仕組みが整っています。
最大のメリットは、税金の計算や納付を証券会社が自動で行ってくれる点です。
「源泉徴収あり」を選ぶと、取引ごとに税金が差し引かれるため、自分で計算や納税手続きをする必要がありません。
また、年間取引報告書が自動で発行されるので、確定申告が必要な場合も書類をそのまま使うだけで済みます。
配偶者控除や扶養控除の判定にも有利な場合があり、家族の扶養範囲で投資をしたい人にも適しています。
さらに、特定口座内で配当金や分配金の損益通算が可能な点も見逃せません。
確定申告が不要になる場合
「源泉徴収あり」の特定口座を選択すると、基本的に確定申告をしなくても問題ありません。
SBI証券が利益に対して20.315%の税金を自動で差し引き、納税まで完了します。
例えば、会社員で年収2,000万円以下かつ他の所得が20万円以下の場合、株の利益がいくらあっても追加の申告は不要です。
ただし、医療費控除やふるさと納税など、ほかの理由で確定申告をする場合は、年間取引報告書を使って簡単に申告できます。
この仕組みのおかげで、投資初心者でも税金の心配をせずに取引を始められます。
損益通算や損失繰越が可能
特定口座では、同一年内に発生した利益と損失を自動で相殺(損益通算)できます。
たとえば、A銘柄で利益が出てB銘柄で損失が出た場合、その差額だけが課税対象です。
さらに、損失が利益を上回った場合は、確定申告を行うことで最大3年間まで損失を繰り越せます。
この制度を活用すれば、翌年以降の利益と相殺できるため、税金を抑えることが可能です。
ただし、繰越控除を利用するには毎年確定申告が必要になるため、忘れずに手続きしましょう。
特定口座のデメリット
特定口座にも注意点があります。
まず、NISA口座と違い、利益には必ず税金がかかります。
また、複数の証券会社で特定口座を開設している場合、損益通算や損失繰越をしたいときは自分で確定申告を行わなければなりません。
さらに、源泉徴収あり口座であっても、他の証券会社の損失と自動で相殺されないため、手続きが煩雑になることも。
NISAやiDeCoのような非課税制度と比べると、税制面での優遇は限定的です。
投資スタイルや目的によっては、NISAや他の制度も併用するのが賢い選択となります。
NISA口座との比較での注意点
NISA口座は、運用益や配当金が非課税になる点が最大の特徴です。
一方、特定口座ではどんなに利益が出ても必ず課税されます。
また、NISA口座で発生した損失は、特定口座の利益と損益通算できません。
たとえば、NISAで損失が出ても、特定口座の利益から税金を差し引かれるため、税負担の軽減にはつながりません。
NISA口座は1人1口座までしか持てず、投資枠にも上限があるため、長期運用や分散投資を考える場合は特定口座との併用が一般的です。
複数証券会社利用時の制限
複数の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を開設することは可能です。
ただし、損益通算や損失繰越を自動で行うことはできません。
たとえば、A証券で利益、B証券で損失が出た場合、それぞれの証券会社で源泉徴収されるため、損益通算を希望するなら自分で確定申告を行う必要があります。
また、複数口座の資産や損益をまとめて管理するのは手間がかかります。
IDやパスワードの管理も煩雑になりがちなので、初心者はまず1社で運用を始め、必要に応じて口座を増やすのがおすすめです。

\口座開設は無料/
SBI証券 特定口座と一般口座・NISA口座の違い
この章では特定口座と一般口座・NISA口座の違いについて解説します。
一般口座との違い
SBI証券の特定口座と一般口座は、税金の計算や申告手続きの手間が大きく異なります。
特定口座では、SBI証券が1年間の取引損益を自動計算し、「年間取引報告書」を発行してくれる仕組みです。
この報告書を使えば、確定申告の作業が格段に楽になります。
一方、一般口座では、すべての損益計算や必要書類の作成を自分で行わなければなりません。
投資初心者にとっては、一般口座の手続きはややハードルが高いと感じることが多いでしょう。
特定口座の「源泉徴収あり」を選ぶと、税金の納付までSBI証券が代行するため、原則として確定申告が不要になります。
反対に、一般口座はすべて自己責任となるため、時間や手間がかかりやすい点に注意が必要です。
税金計算や申告手続きの違い
税金計算の手間は、特定口座と一般口座で大きく異なります。
特定口座(源泉徴収あり)なら、取引ごとに発生する税金をSBI証券が自動で計算し、納税まで済ませてくれます。
このため、給与所得者や副業で投資をしている人は、ほとんどの場合で確定申告が不要です。
一方、一般口座では、売買ごとの損益や必要経費を自分で集計し、確定申告書を作成する必要があります。
例えば、年間を通じて複数回取引した場合でも、すべて自分で記録しなければなりません。
また、損失が出た場合の損益通算も、一般口座では自分で計算して申告しなければならないため、手間がかかります。
この違いが、初心者に特定口座が選ばれる大きな理由となっています。
NISA口座との違い
NISA口座は、投資で得た利益が非課税になる特別な口座です。
SBI証券では、NISA口座を1人1口座しか持てず、一般口座や特定口座と併用できます。
NISA口座で購入できる商品は、SBI証券が指定する株式や投資信託などに限られます。
また、NISA口座で保有した商品は他の金融機関へ移管できず、金融機関の変更も制限があるのが特徴。
NISAの利用には年齢や取引上限額などの条件があり、制度の変更も多いため、最新情報を確認することが大切です。
特定口座や一般口座と違い、NISA口座で得た譲渡益や配当金は非課税となるため、節税効果が高いのが特徴です。
税制優遇の違い
NISA口座の最大の魅力は、投資で得た利益や配当が非課税になる点です。
例えば、通常の特定口座や一般口座では、利益に対して約20%の税金がかかります。
しかし、NISA口座ならこの税金がゼロになります。
一方、特定口座や一般口座では、利益や配当に対して自動的に税金が差し引かれます。
また、NISA口座は年間投資上限額が決まっており、非課税期間も制度ごとに異なります。
このような税制優遇の違いを理解し、自分の投資スタイルに合った口座を選ぶことが重要です。
使い分けのポイント
特定口座とNISA口座、一般口座の使い分けにはコツがあります。
まず、NISA口座は非課税枠を最大限活用したい人に最適です。
投資初心者や確定申告の手間を減らしたい場合は、特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと良いでしょう。
一方、損益通算や損失繰越を重視したい場合は、特定口座や一般口座の活用が有効です。
例えば、NISA枠を使い切ったあとは特定口座で取引する、という組み合わせもおすすめです。
自分の投資目的や年間の取引額、税金対策を考慮して、最適な口座を選びましょう。

SBI証券 特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違い

この章では特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いについて解説します。
「源泉徴収あり」の特徴
「源泉徴収あり」の特定口座は、SBI証券が株や投資信託の売買で発生した利益に対して、税金(所得税・住民税・復興特別所得税)を自動で差し引いて納付してくれる仕組みです。
このため、原則として自分で確定申告を行う必要がありません。
取引のたびに税金が天引きされるため、納税漏れの心配もなく、投資初心者でも安心して利用できます。
また、「配当金等を受け入れる」設定をしておくと、同じ特定口座内で配当金や分配金と売却損益の損益通算も可能です。
ただし、損失の繰越控除など特別な税制優遇を利用したい場合は、確定申告が必要になるケースもあります。
確定申告が不要なケース
「源泉徴収あり」を選択し、年間の譲渡益や配当金が発生しても、通常はSBI証券が全ての税金を納付してくれるため、確定申告は不要です。
ただし、損失の繰越控除や複数証券会社での損益通算など、特例を利用したい場合は例外として確定申告が必要となります。
「源泉徴収なし」の特徴
「源泉徴収なし」の特定口座では、利益が出てもSBI証券が税金を差し引くことはありません。
そのため、1年間の取引で利益が出た場合は、自分で確定申告をして納税する必要があります。
SBI証券は「特定口座年間取引報告書」を発行してくれるため、損益計算自体は簡単ですが、申告手続きは自己責任となります。
この方式は、年間の利益が20万円以下で確定申告が不要な場合や、複数の証券会社で損益通算をしたい場合に向いています。
確定申告が必要なケース
「源泉徴収なし」の特定口座を利用して利益が出た場合、原則として確定申告が必須です。
複数の証券会社で取引している場合や、損失の繰越控除を使いたい場合も同様に申告が必要となります。
会社員であっても、給与以外の所得(投資利益)が年間20万円を超える場合は確定申告を行わなければなりません。
どちらを選ぶべきかの判断基準
投資初心者や、確定申告の手間を避けたい方は「源泉徴収あり」を選ぶのが無難です。
自動で税金が納付されるため、ミスや納税漏れのリスクがありません。
一方、年間利益が20万円以下に収まりそうな場合や、複数証券会社で損益通算をしたい場合は「源泉徴収なし」を選択することで、余計な税金の支払いを防ぐことができます。
迷った場合は、まず「源泉徴収あり」でスタートし、取引規模や目的に合わせて翌年以降に切り替える方法も選択肢となります。

SBI証券 特定口座の選び方と注意点

この章では特定口座の選び方と注意点について解説します。
自分に合った口座選択のポイント
SBI証券の特定口座を選ぶときは、「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かを最初に決める必要があります。
会社員や投資初心者には「源泉徴収あり」がおすすめです。
利益が出た場合、SBI証券が自動で税金を計算し納付までしてくれるため、確定申告の手間がかかりません。
一方、「源泉徴収なし」は自分で確定申告をする必要があるため、税務知識がある人や損失の繰越控除を活用したい人向けとなります。
NISA口座を持っている場合は、NISA枠での取引は非課税なので、特定口座と使い分けるのが一般的です。
迷った場合は、まず「源泉徴収あり」を選択し、必要に応じて後から変更することもできます。
特定口座の変更・廃止手続き
特定口座の「源泉徴収あり/なし」の区分は、SBI証券のWEBサイトから変更手続きが可能です。
「口座管理」画面の「お取引関連・口座情報」から該当の変更申請を行い、必要書類を提出します。
変更が反映されるタイミングは、申請時期によって異なり、年初の取引前であれば新しい区分が適用されます。
廃止したい場合は、「特定口座廃止届出書」をカスタマーサービスセンターへ請求し、必要事項を記入して返送。
手続きが完了すると、WEBサイトのメッセージボックスに通知が届く仕組みです。
廃止後は一般口座のみとなるため、損益計算や確定申告を自分で行う必要が出てきます。
投資初心者が注意すべき点
初心者が特定口座を選ぶ際は、いくつか注意点があります。
まず、「一般口座」を選んでしまうと、税金計算や確定申告をすべて自分で行う必要があり、手間とリスクが増えます。
また、口座開設後はログインパスワードや取引パスワードの管理も重要です。
パスワードは英数字や記号を組み合わせ、定期的に変更しましょう。
操作ミスや売買ボタンの押し間違い、重要なお知らせの見落としにも気をつけてください。
ネット証券は便利ですが、ネット環境のトラブルやセキュリティリスクもあるため、バックアップサイトや公式サイトからのログインを心がけると安心です。
特定口座の選択や変更は、焦らず公式の案内に沿って進めることが大切です。

まとめ

ポイント
- 特定口座はSBI証券が損益計算や年間取引報告書の作成を代行する仕組みである
- 「源泉徴収あり」を選ぶと税金が自動で引かれ、原則として確定申告が不要となる
- 取引できる商品は国内外の株式や投資信託など幅広いが、FXや先物などは対象外である
- 一般口座やNISA口座との違いは、税金計算や申告の手間、非課税枠の有無にある
- 初心者は「特定口座・源泉徴収あり」を選択することで手続きが簡単となる
今回はSBI証券の特定口座について仕組みやメリットなどを説明してきました。
口座開設時にどれを選べばいいか悩む人が多いですが、初心者は特定口座の「源泉徴収あり」で問題ないです。
必要があれば後から変更もできるので、口座開設はササっと終わらせてしまい、少しでも早く実際に株のトレードをしてみることをおススメします。


\口座開設は無料/
参考:特定口座とは|SBI証券