ROEとROIC、どっちを重視すべきですか?

後輩ちゃん

カブヤク
視点が違うんだ。ROE=株主資本の効率、ROIC=事業に投じた資本の効率。まずは役割から押さえよう。
ROE(自己資本利益率)は株主から預かった自己資本に対する利益率、ROIC(投下資本利益率)は事業に投じた資本(投下資本)がどれだけ利益(税後の営業利益)を生んだかを測る指標です。
資本構成の影響を受けやすいのがROE、事業そのものの資本効率に近いのがROICです。
30秒で要点|定義・式・使いどころ

- ROE=当期純利益 ÷ 自己資本 ×100%(連結・親会社株主持分の期首期末平均)。
- ROIC=NOPAT(税後営業利益) ÷ 投下資本 ×100%(期首期末平均)。
- 使い分け:ROE→株主視点、ROIC→事業視点。価値創造の判断はROICとWACCの比較が定石。
定義の厳密化|式と用語をそろえる

ROE(自己資本利益率)
- 分子:当期純利益(親会社株主に帰属)。
- 分母:自己資本=親会社株主持分(非支配株主持分は含めない)。期首・期末平均を使用。
- 留意:自社株買い・配当で自己資本が減ると機械的にROEが上がることがある。
ROIC(投下資本利益率)
- 分子:NOPAT=EBIT×(1−実効税率)(金融費用の影響を外す)。
- 分母(投下資本):実務では
- 営業投資資本(NOA)=営業資産−営業負債(現金・有価証券などの非営業資産は除外)、または
- 有利子負債+株主資本−非営業資産
のいずれかで統一。期首・期末平均を使用。
- 非営業資産のうち現金は、運転に必要な最低現金を残し、余剰現金のみ除外するのが一般的。
- のれん・IFRS16・一時要因の扱いは注記で統一(比較時は同じ方針に)。
何を映すか|レバレッジの効き方と価値創造
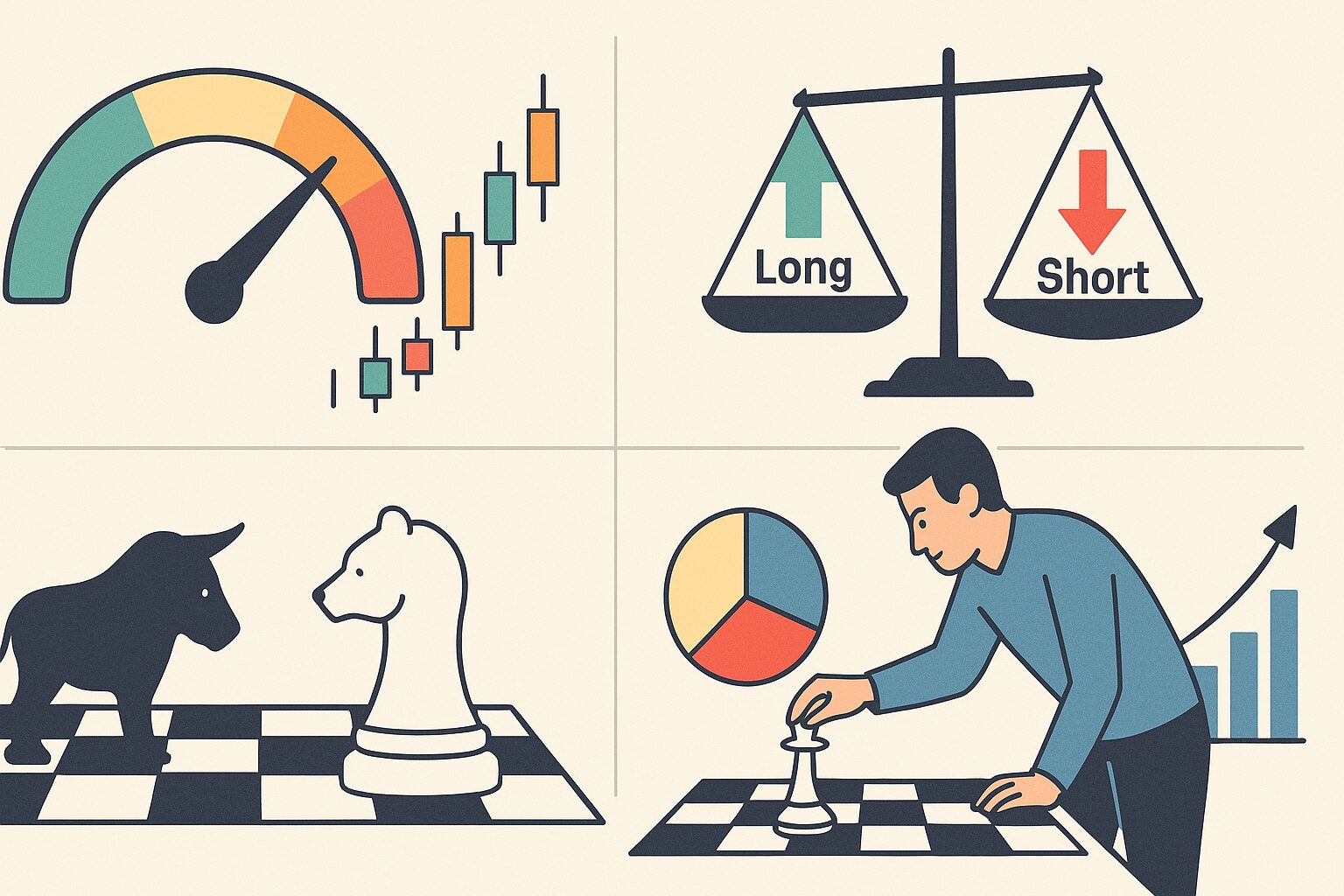
ROE:資本構成の影響を強く受ける
- 負債を増やし自己資本を薄くするとROEは上がりやすい(利益一定でも分母が減る)。
- 自社株買いはROEを押し上げやすいが、事業の稼ぐ力が上がったとは限らない。
ROIC:事業の“素の”資本効率に近い
- 金融費用の影響を外し、投下資本に対する稼ぎを測る。通常、資本構成の変更では大きくぶれにくい。
- 良否の判断はROIC > WACC(価値創造)/ROIC < WACC(価値毀損)が目安。
例題で比較|同じビジネスでもROEは資本構成で変わる

前提
- EBIT=100、実効税率30% → NOPAT=70。
- 投下資本=1,000 → ROIC=7%。
- 金利=2%。
ケースA:自己資本600/有利子負債400
- 利息=8、税引前利益=92、税金=27.6、当期純利益=64.4。
- ROE=64.4÷600=約10.7%。
ケースB:自己資本300/有利子負債700
- 利息=14、税引前利益=86、税金=25.8、当期純利益=60.2。
- ROE=60.2÷300=約20.1%。
——事業の稼ぐ力(ROIC=7%)は一定でも、レバレッジの違いでROEは大きく変わることがわかります。
価値創造の判断には、ROICとWACCの比較が欠かせません。
使い分けのコツ|現場での読み方

1. 成長戦略・投資判断
- ROIC>WACCの分野へ資本配分。新規投資やM&Aでは投下資本の回収年数とROICの維持可能性を確認。
2. 株主還元の影響
- 自社株買いはROE押し上げ効果が出やすい。一方、投下資本が不変ならROICは大きくは変わりにくい。
3. 会計方針と比較の整地
- IFRS16(リース)の影響は投下資本の定義で異なる。有利子負債+株主資本−非営業資産の定義ではリース負債分だけ投下資本が増えやすくROICは低下しやすい。
- 一方、営業資産−営業負債(NOA)定義ではROU資産とリース負債が相殺され、影響が小さい場合がある。いずれにせよ定義は必ず統一。
- のれんを分母に含めるか否かを統一(含めない“実力ROIC”を見る運用もある)。
実務チェックリスト|指標ブレを減らす前準備

データの出どころ
- ROE:連結・親会社株主持分、期首期末平均。ROIC:NOPATと投下資本の定義を固定。
一時要因の補正
- 特別損益、減損、税効果の一過性は注記で調整。NOPATの税率は実効税率で。
比較の軸
- 時系列×同業比較で傾向を確認。価値創造はROIC−WACCで評価。
- 比べるWACCは税後・同通貨・同期間でROICとそろえる(前提の不一致を避ける)。
よくある勘違いベスト8|ここだけは外さない

- ROICの分子に当期純利益を使う(正しくはNOPAT)。
- 投下資本の分母に総資産を使う(それはROAに近い)。
- 分母を期末値だけで計算(平均を使わずブレが大きくなる)。
- 連結/単体・のれん/IFRS16の扱いをそろえず比較。
- 自社株買いでROICも上がると誤解(営業投資資本が変わらなければ原則効きにくい)。
- WACCと比べずROICの高低だけで判断。
- ROEが高い=必ず高収益(レバレッジ要因の可能性)。
- 税率の一時要因(繰延税金資産等)を調整しない。
まとめ|株主視点と事業視点をセットで見る

ポイント
- ROE=株主資本の効率、ROIC=投下資本の効率。役割が違う。
- 価値創造はROIC>WACCで判断。レバレッジで動きやすいのはROE。
- 比較は連結×平均分母×定義統一が最短ルート。
まずは自社のROICとWACCを並べてみます。

後輩ちゃん

カブヤク
いいね。加えてROEの推移も見れば、レバレッジと事業効率の両輪が分かるよ。
\市場の反応をリアルタイムで追う準備を/
