

株式投資を始めるとき、多くの人が最初に出会う指標がPER(株価収益率)です。
株価だけでは割安・割高は判断しにくいですが、PERを使えば「利益に対していまの株価が高いのか低いのか」をシンプルに見比べられます。
ポイント(先に要点)
PER(株価収益率)とは?初心者にもわかりやすく

定義と読み方
PER(Price Earnings Ratio)=株価÷EPS。
株価が、その会社の1株あたり純利益(EPS)の何倍で評価されているかを表します。
EPSの基礎はこちらで詳しく解説しています。
例:株価1,000円、EPS100円 → PER=10倍(利益の10年分が株価に織り込まれているイメージ)。
なぜ重視される?
PERは「利益に対する価格」を一目で比較でき、投資判断の入口になります。
ただしPERは利益の質や将来成長を直接は語りません。
単体判断ではなく、同業比較・推移・他指標との併用が前提です。
計算式・目安・実務の注意点

PERの計算式と具体例
基本式:PER=株価÷EPS。算出は簡単ですが、EPSの一時要因(特損・為替など)でPERが大きく振れることがあります。
実務メモ:比較には原則希薄化後EPS(diluted)を用います(ストックオプションや増資の希薄化影響を含めるため)。
注:赤字(EPS<0)の期は数式上マイナスPERですが、実務では「— / N/A」と表記して比較対象から外すのが通例です。
赤字局面ではPBRやPSR、キャッシュフロー指標が有効です。
何倍なら割安・割高?
単一の「正解値」はありません。指針は次の通り:
- 同業比較:同じ業種内で相対評価(業態・収益構造が近いほど有効)。
- 推移比較:複数年のレンジ感で“平常値”からの乖離を見る。
- マクロ環境:金利・リスクプレミアム・景気局面で市場の許容PERは動きます。
直感モデル:金利・成長とPERの関係
ゴードン成長モデルの近似では、P/E ≈ 配当性向 ÷ (期待収益率 r − 永続成長率 g) と表せます。
r(金利やリスクプレミアムで上振れ)↑ならPERは縮み、g(成長期待)↑ならPERは膨らみやすい、という直感は有効です。
※「PER≒1/(r−g)」は配当性向=100%という特殊仮定の場合に限ります。
PERの使い方:割安/割高の見極めと“外しにくい”手順

見る順番(テンプレ)
- 同業他社の最新期PERで相対位置を把握。
- 自社の複数年PERレンジで「平常値」からの乖離を確認。
- EPSの質を点検(特別要因・為替・会計変更)。
- 他指標で裏取り:PBR(資産面)、ROE(資本効率)、PEG(成長調整)。
- セクターや金利・景気サイクルの文脈に置く。
「低PER=お買い得」とは限らない
- 構造的成長率の低下や一過性の高利益の反動を織り込んでいる可能性。
- 景気敏感株は底で高PER・天井で低PERになりやすい(分母EPSの循環要因)。
予想PERの扱い
アナリスト予想や会社計画を使う予想PERは“先読み”に便利ですが、前提が外れるリスクも。
複数ソースで幅を把握し、保守・中立・強気のシナリオを置いて感度を確認しましょう。
業種(セクター)で変わるPER:背景を読む
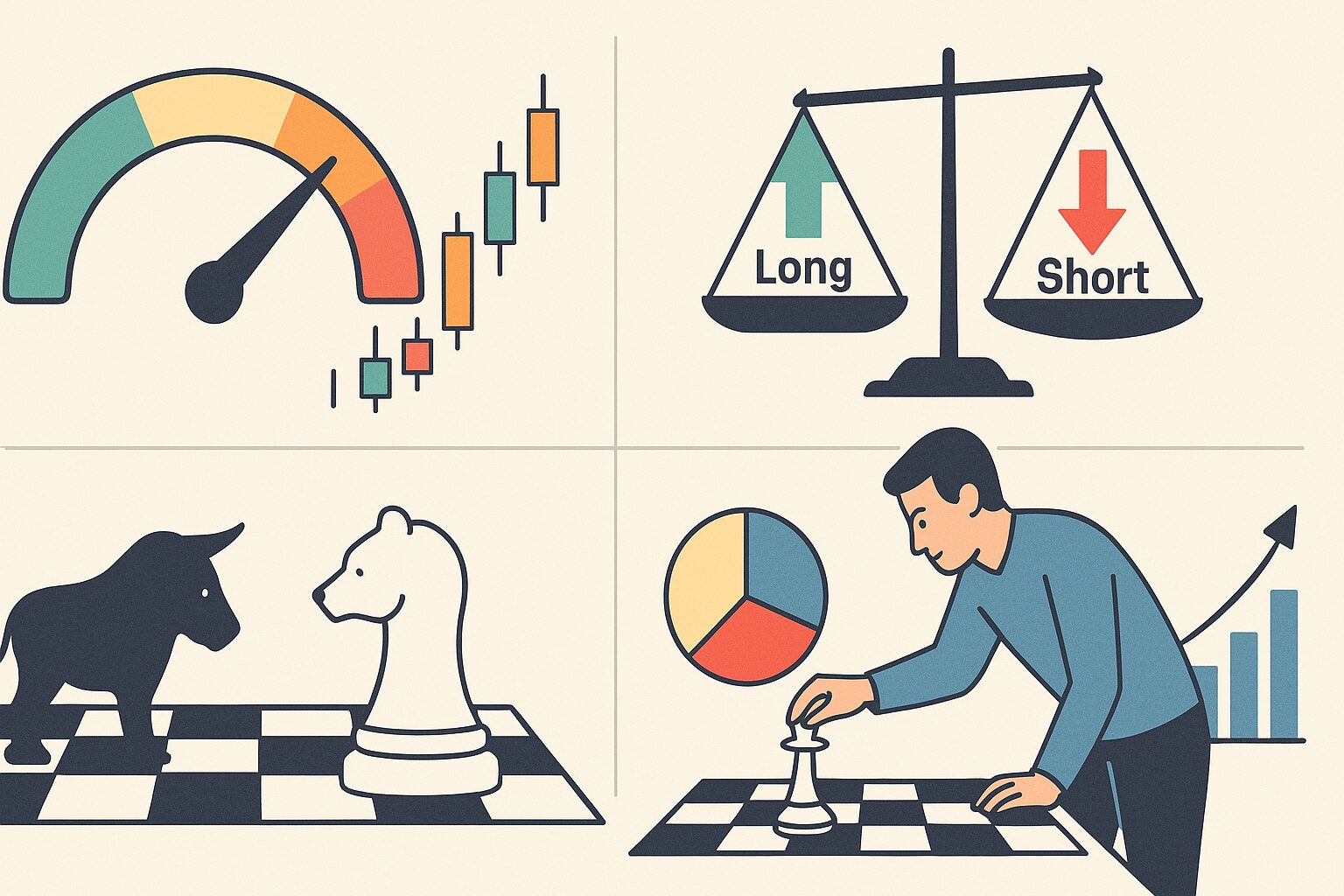
なぜ業種で違う?
市場が期待する成長率(g)や安定性が異なるからです。
成長が評価されやすい情報・通信やヘルスケアは高PERに、資産集約的・規制色の強い業種は低PERに寄りやすい傾向があります。
比較の型
- まず同業内で比較(ビジネスモデルが近いほど有効)。
- そのうえで自社の過去レンジと照合し、現在位置を把握。
- 「なぜ差があるか」をEPSの質・成長性・リスクで言語化する。
PERと他の投資指標(PBR・ROE)をどう組み合わせる?

PBR:資産価値サイドの安全マージン
PBRは「株価が1株あたり純資産(BPS)の何倍か」。
資産の裏付けを見たいときに有効です。
なお、無形資産比率が高い業種や含み損益が大きい資産構成では、PBR1倍未満=割安と単純化できない点に注意。
ROE:資本効率の質を測る
ROEは「自己資本をどれだけ効率よく利益に変えたか」。
PERが“市場の期待”なら、ROEは“稼ぐ力の効率”。
両輪で見ることで「期待に見合う実力か」を検証できます。
成長調整:PEGを使う
PEGレシオ(PER÷利益成長率)で、成長を加味した相対評価が可能に。
高成長銘柄の過度な高PERを冷静に点検できます。
PERとPBRの違い・使い分けはこちら(PERとPBRの違い)で具体例つきで解説しています。
まとめ

ポイント(総復習)
- PERは株価÷EPS。入口として強力だが、単体判断は禁物。
- 評価は同業比較+複数年の推移+EPSの質点検が基本。
- 赤字や一時要因でPERが効かない局面は、PBR・PSR・CF指標に切り替え。
- 金利・成長の直感は「P/E ≈ 配当性向 ÷ (r−g)」。環境で許容PERは動く。
- 最終判断は、ROEの効率性やPEGの成長調整で裏取りする。


\市場の反応をリアルタイムで追う準備を/
参考:
