

PCFR(株価キャッシュフロー倍率)は、株価が企業のキャッシュフローに対して何倍の評価を受けているかを見る指標です。
会計上の利益ではなく現金の流れに着目するため、減価償却などの会計要因で利益が圧縮されやすい企業でも、実態に近い比較がしやすくなります。
ただし、“何倍なら割安/割高”という絶対基準はありません。
業種や成長段階、市況でレンジは変わるため、同業比較と推移で相対的に判断するのがコツです。
PCFRの意味と計算のツボを最短で掴む

サクッと定義:式は1行
PCFR=株価 ÷ 1株あたり営業キャッシュフロー(CFPS)。
企業全体で見る場合は時価総額 ÷ 営業キャッシュフローでも同義です。
CFPSは営業キャッシュフロー ÷ 発行済株式数で算出します(実務では簡便式「当期純利益+減価償却費(÷株式数)」が用いられることもありますが、厳密には営業CFと一致しません)。
何が見える?(利益指標との違い)
利益は減価償却や一時要因でブレやすい一方、営業キャッシュフローは実際の現金創出力に近く、設備投資が重い業種でも実態比較がしやすいのが利点です。
最初に避けたい勘違い
PCFRが低い=必ずしも“お買い得”ではありません。
キャッシュフローの一時膨張(在庫圧縮など)や景気敏感度で低く出ることも。
同業比較×複数年の推移で確認するクセをつけましょう。


“目安”の考え方と業種差:絶対値より文脈

“絶対基準”はない—相対で見る
PCFRは市場局面や金利、景気循環の影響を強く受けます。
よって「○倍以上は割高」と決め打ちせず、同業平均・主な競合・自社の過去レンジで相対評価するのが安全です。
倍率の算出方法(営業CFか簡便法か)や対象母集団でも水準は変わるため、利用データの定義を必ず確認しましょう。
業種によるクセ
有形資産・減価償却が厚い業種(製造・インフラ等)はキャッシュフローが相対的に大きく、PCFRは低めに出やすい傾向。
成長期待が高い領域(IT・通信等)は高めになりがちです。
成長段階でも変わる
創業〜成長初期は投資先行でCFが安定せず、PCFRの解釈が難しい場面が増えます。
成熟企業や安定CFが確認できる企業に向いた指標と覚えておくとズレが減ります。


実務での使い方:スクリーニング→推移→同業比較

スクリーニングの入口
まずは証券会社のスクリーニング機能や国内の株式データサービスで「PCFR(P/CF)が業種平均より低め」「PER・PBRも極端に高くない」「営業CFがマイナスでない」等で一次抽出。
ここでは“候補を作る”だけに留めます。
推移で地力を見極める
3〜5年のPCFR、CFPS、売上・利益の推移を並べ、安定/加速/減速を判定。単年の“瞬間風速”ではなく、地力を確認します。
同業比較で相対位置を確認
業種内でPCFR・PBR・ROEを表にし、現金創出力×市場評価×資本効率の三点で相対位置を把握。
単一指標で決めないのが基本です。


PER・PBRとの使い分け:役割を分けてブレを減らす
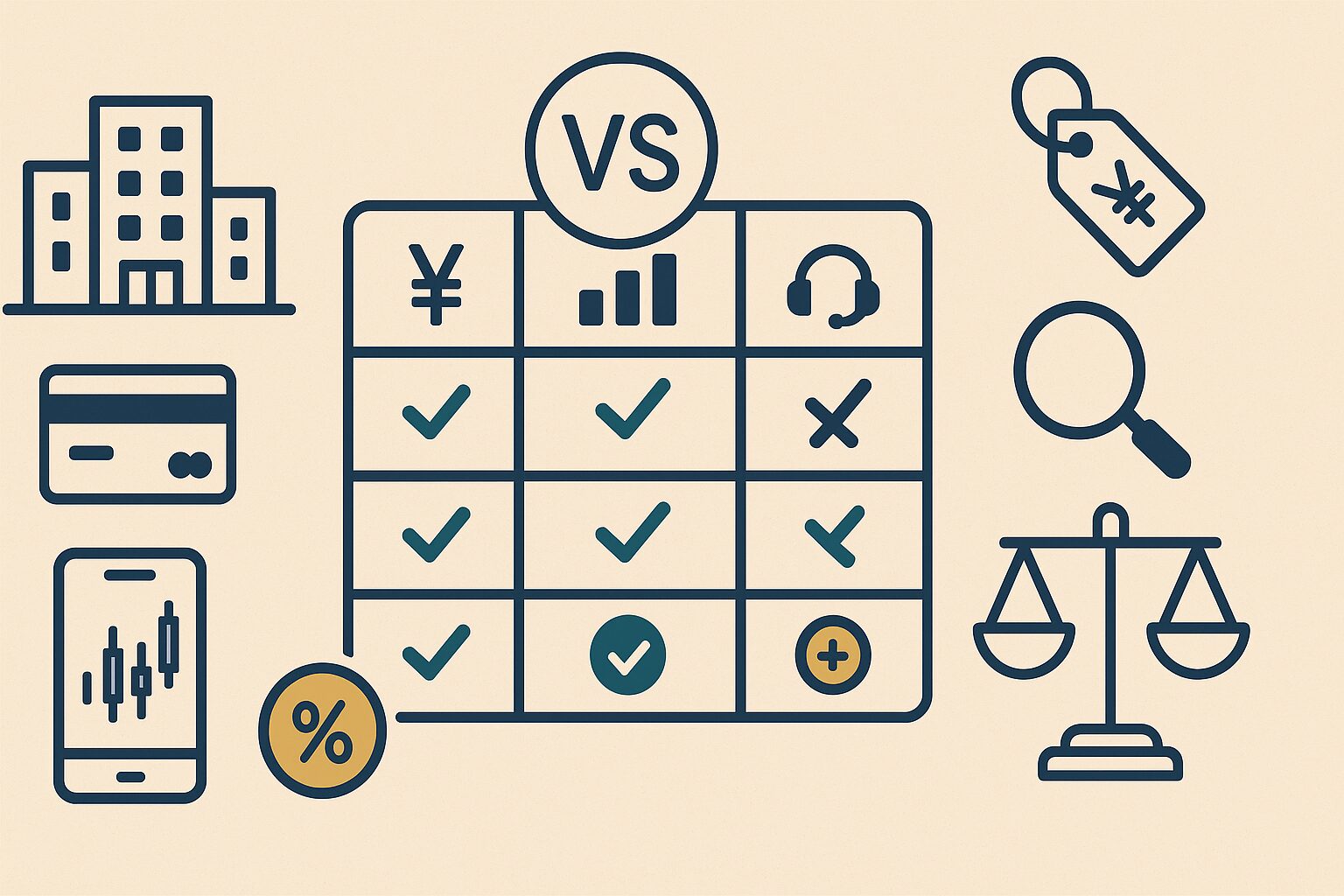
役割の違いをひと言で
PCFR=現金の稼ぐ力、PER=利益の稼ぐ力、PBR=資産の厚み(解散価値の目安)。
指標は競合ではなく相棒。組み合わせるほど誤判定が減ると覚えましょう。
組み合わせの型(例)
- 低PCFR×低PER:現金・利益の両面で割安の可能性。
- 低PCFR×高PBR:資産評価が先行—資産の質/期待の持続性を点検。
- 高PCFR×高ROE:実力評価か過熱か—持続的CF/競争優位で判定。
設備投資が重い企業で効く理由
減価償却で利益が圧縮されやすい業種では、PERだけだと割高に見えがち。
PCFRは営業CF基準なので、“実際の回収力”を反映しやすいのが強みです。


注意点と落とし穴:マイナスCF・一時要因・定義のズレ

マイナスCFは解釈が難しい
営業キャッシュフローがマイナスだとPCFRは負値や定義不能となり、割安度の判断には一般に不向きです。
一方、営業CFが安定プラスで利益が一時的に小さい企業の比較には有用です。
一時要因に要注意
在庫圧縮や運転資本の偏り、補助金・補填などでCFが一時的に膨らむ/萎むことがあります。
複数年の推移と注記で背景を確認しましょう。
定義の確認を忘れない
データベースや開示で“営業CF”やCFPSの算出方法が異なる場合があります。
決算短信・有価証券報告書で算出根拠を確認してから比較するのが安全です。


まとめ

ポイント
- PCFR=株価(または時価総額)を営業CF(またはCFPS)で割った倍率。利益より実態を捉えやすい場面がある。
- “絶対基準”でなく相対評価。業種・成長段階・市況でレンジは変わる。
- 実務は「スクリーニング→推移→同業比較」。単年ではなく地力を見る。
- PER・PBR・ROEと役割分担で使うと誤判定が減る。
- マイナスCFや一時要因、定義のズレに注意。開示で算出根拠を確認。


参考:
