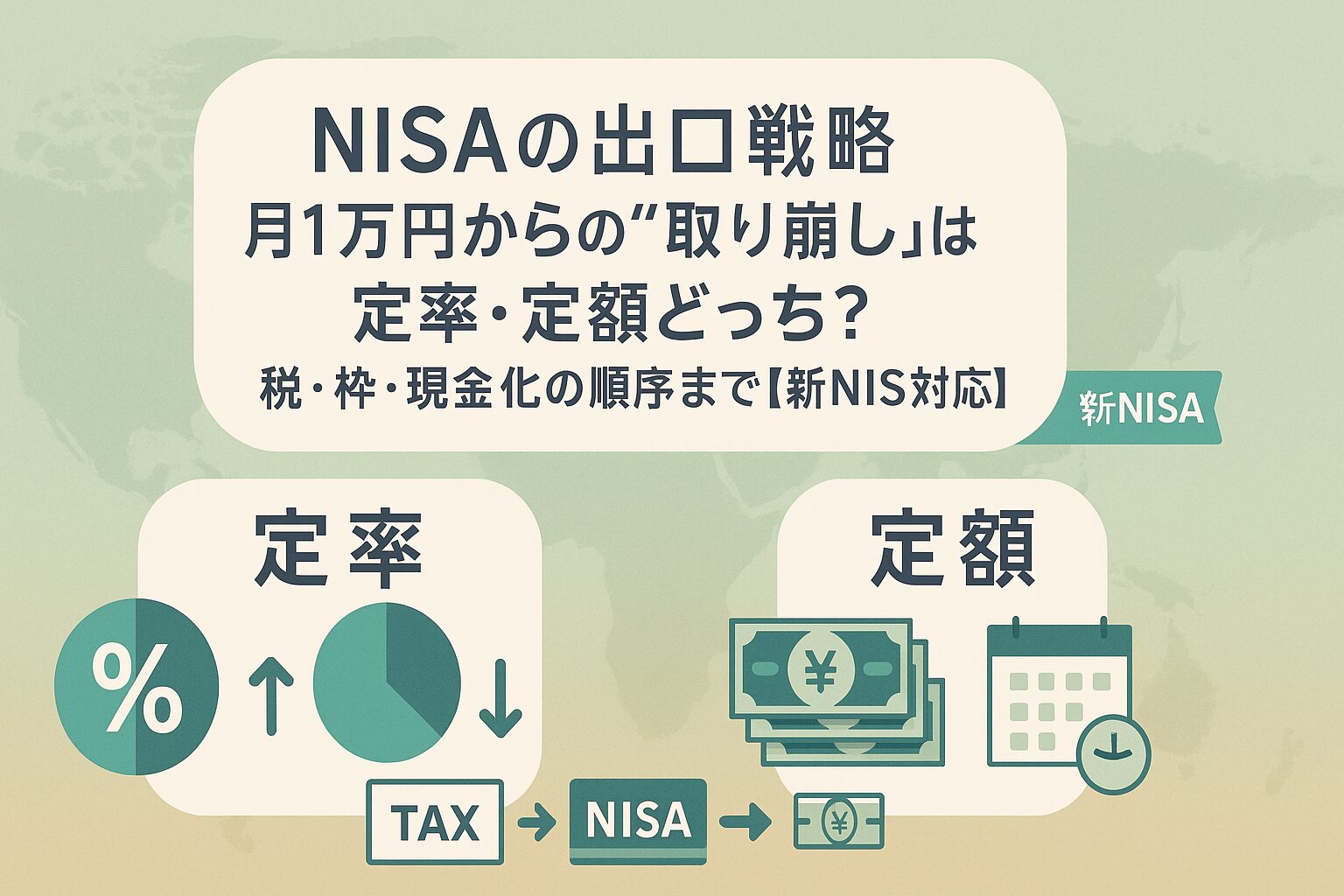この記事では、新NISAで育てた資産の「取り崩し設計」を、月1万円の積立からでも実行できる手順に落として解説します。
定額・定率・バケット法の比較、年1回の実務フロー、税と手数料の注意点、よくある誤解までを網羅します。
基礎はNISAの基礎、積立の型は積立日・頻度の最適解、リバランスはリバランス完全ガイドも参照してください。
\準備がまだの人は口座から/
出口設計の前提:目的・期限・現金の線引きを先に決める



- 目的:老後の生活費、教育費、住宅頭金など。
- 期限:開始時期(例:65歳〜)と必要期間(例:30年)。
- 現金クッション:生活防衛資金3〜6か月+取り崩し用の現金/短期債2〜3年分(目安)。参考:生活防衛資金の作り方
※現金クッションは相場の上下に耐えるための“時間の買い物”。暴落時でも取り崩しを止めないための仕組みとして必須です。
定額・定率・バケット法の比較(どれを選ぶ?)



| 方式 | やり方 | メリット | 注意点 | 相性の良い人 |
|---|---|---|---|---|
| 定額取り崩し | 毎月(年)一定額を売却して現金化。 | 収入が安定、家計管理が楽。 | 下落時に口数が多く売れ資産寿命が縮む可能性。 | シンプル重視の人。 |
| 定率取り崩し | 評価額の○%を毎年取り崩す。 | 相場に応じて額が自動調整、資産寿命を守りやすい。 | 収入が年ごとに変動、家計にクッションが必要。 | 長期最適・柔軟性重視の人。 |
| バケット法 | 短期(現金)・中期(債券)・長期(株式)に分け順番に使う。 | 暴落時も現金バケットで凌げる、心理的に続けやすい。 | 設計とメンテがやや複雑。 | メンタル安定を重視する人。 |
※取り崩し率(例:3.5〜4%)はあくまで目安。市場環境・資産配分・年金開始時期で調整しましょう。将来リターンは保証されません。
取り崩しと合わせて管理 👉 リバランス完全ガイド
実務フロー:年1回の点検→取り崩し額の計算→売却の順番
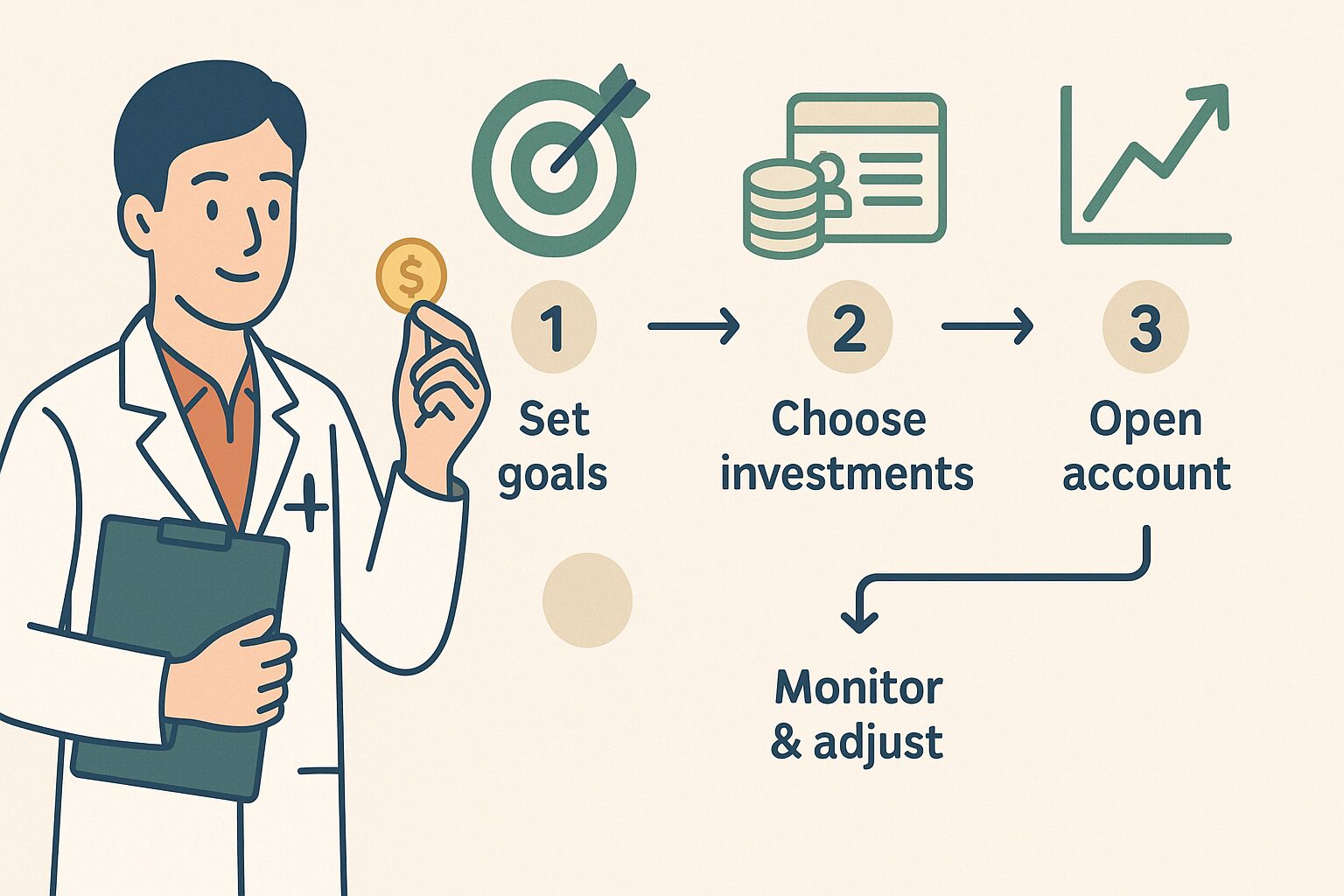


① 評価額と配分を確認
- 全体の評価額・資産配分を集計。
- 現金バケット(2〜3年分)を維持できているか点検。
- 配分のズレは“買い増しで戻す”を優先。
② 取り崩し額を決める
- 定率:前年末評価額×(例)3.5〜4%を年間の上限目安に設定。
- 定額:家計から必要額を逆算し、下落時は現金バケットで緩衝。
- 不足分は臨時収入を活用(分割スポットの最適解)。
③ 売却の順番(原則)
- 特定口座 → NISAの順で取り崩し(特定は損益通算・繰越控除が使える)。
- NISAで売却した枠は“翌年以降に簿価相当額”で復活(同年再利用不可・年間投資枠に上乗せなし)。
- 配当は原則再投資で現金化を抑制(参考:受取 vs 再投資)。
※「売却枠の復活」は翌年以降のみ。同年の再利用はできず、年間投資枠(最大360万円)に上乗せもできません。制度の詳細は最新情報を確認してください。
税と実務のチェックポイント(受取方式・海外配当・手数料)



- 国内配当の非課税条件:配当金受取を株式数比例配分方式に設定し、NISA口座で受け取る。設定が異なると国内税が課される場合があります。
- 海外配当(米国ETF等):国内税は非課税だが現地源泉(例:10%)は残る。NISAでは外国税額控除は適用不可のため、国内代替ETFとのトータルコスト比較を。
- 売買コスト/為替:定期売却時も信託報酬・スプレッド・為替手数料に注意(参考:米国ETFのコスト最適化|国内vs米国ETF)。
※税制・商品仕様は変更される可能性があります。最新の目論見書・約款・各証券会社の説明ページをご確認ください。
ケース別の型(年金前/教育費/住宅)

年金前ブリッジ(60〜65歳)
- 現金2〜3年分+定率3.5%目安。
- 相場悪化時は現金バケットで凌ぎ、株式は売らない。
教育費まで○年
- 期限接近に合わせ現金比率を段階的に引き上げ、定額中心で月々の確実性を優先。
住宅頭金
- 目標時期の2〜3年前から段階的に現金化、バケットの“長期”を縮小。
\“特定→NISA”の順番と簿価復活を理解/
家族口座もまとめて準備 👉 SBI証券の口座開設と初期設定
よくある誤解Q&A(短く要点)
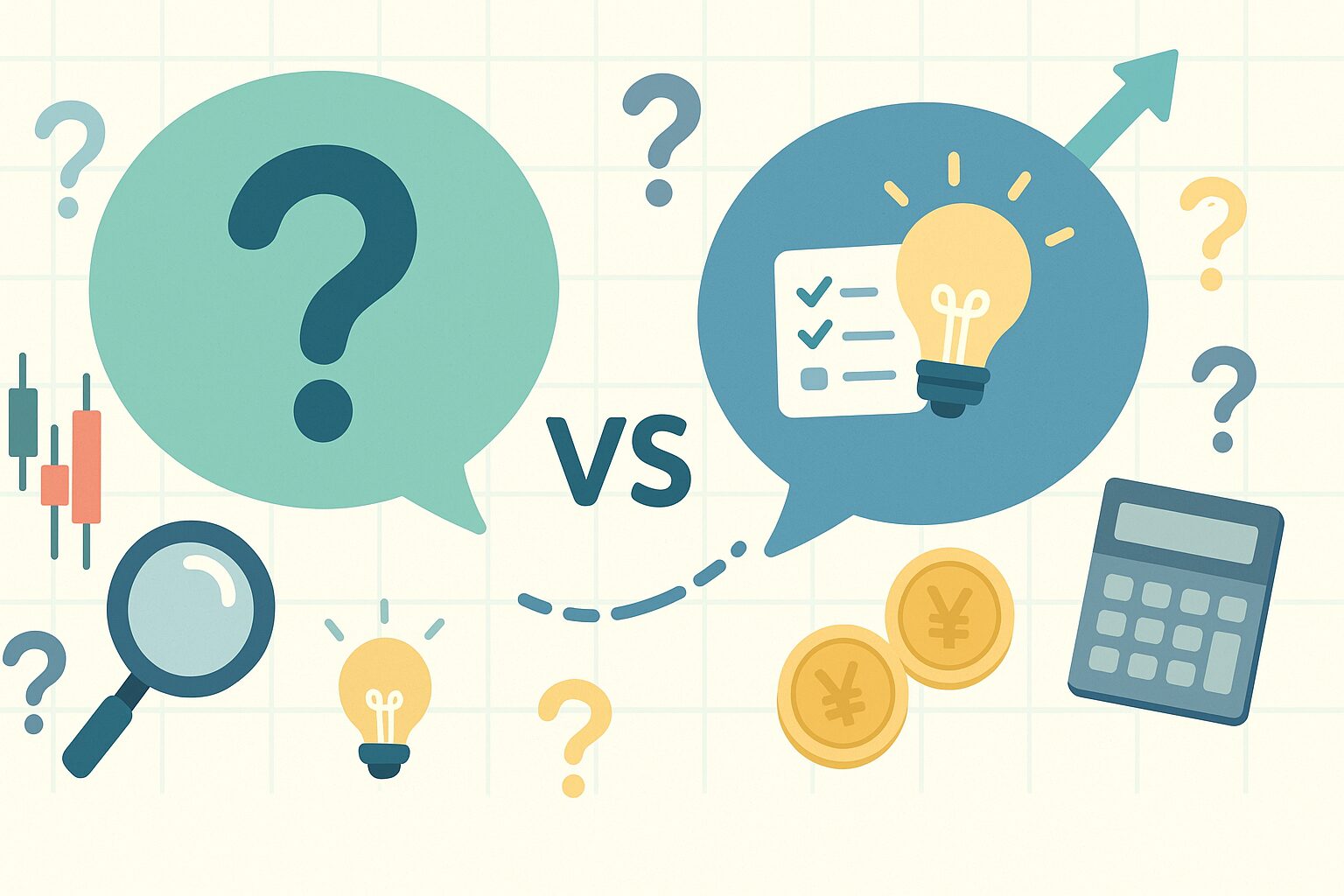
Q1.NISAは“売って枠を空ければ”同年に入れ直せる?
不可。
枠は翌年以降に簿価相当額で復活し、同年再利用や年間投資枠への上乗せはできません。
Q2.取り崩しは配当だけで賄えば売却不要?
配当だけに依存すると銘柄選好が歪みやすく、税・分散の観点でも非効率になりがち。
“必要額=配当+計画的売却”で設計しましょう。
Q3.定額と定率、どちらが有利?
有利不利は局面依存。
長期の資産寿命を守る観点では定率+現金バケットがバランス良好です。
まとめ

ポイント
- 出口は“定率+バケット法”が基本形。現金2〜3年分を先に確保。
- 売却の順番は「特定→NISA」。NISA売却枠は翌年以降に簿価復活(同年不可・上乗せ不可)。
- 国内配当の非課税は「株式数比例配分方式×NISA口座受取」が条件。海外配当は現地源泉が残り、NISAでは外国税額控除不可。
- 年1回の“点検日”を固定し、取り崩し額と配分を更新。


\今日から一歩。出口を決めて“逆算の積立”へ/
👉 次はこちら:簿価方式・枠復活の基礎