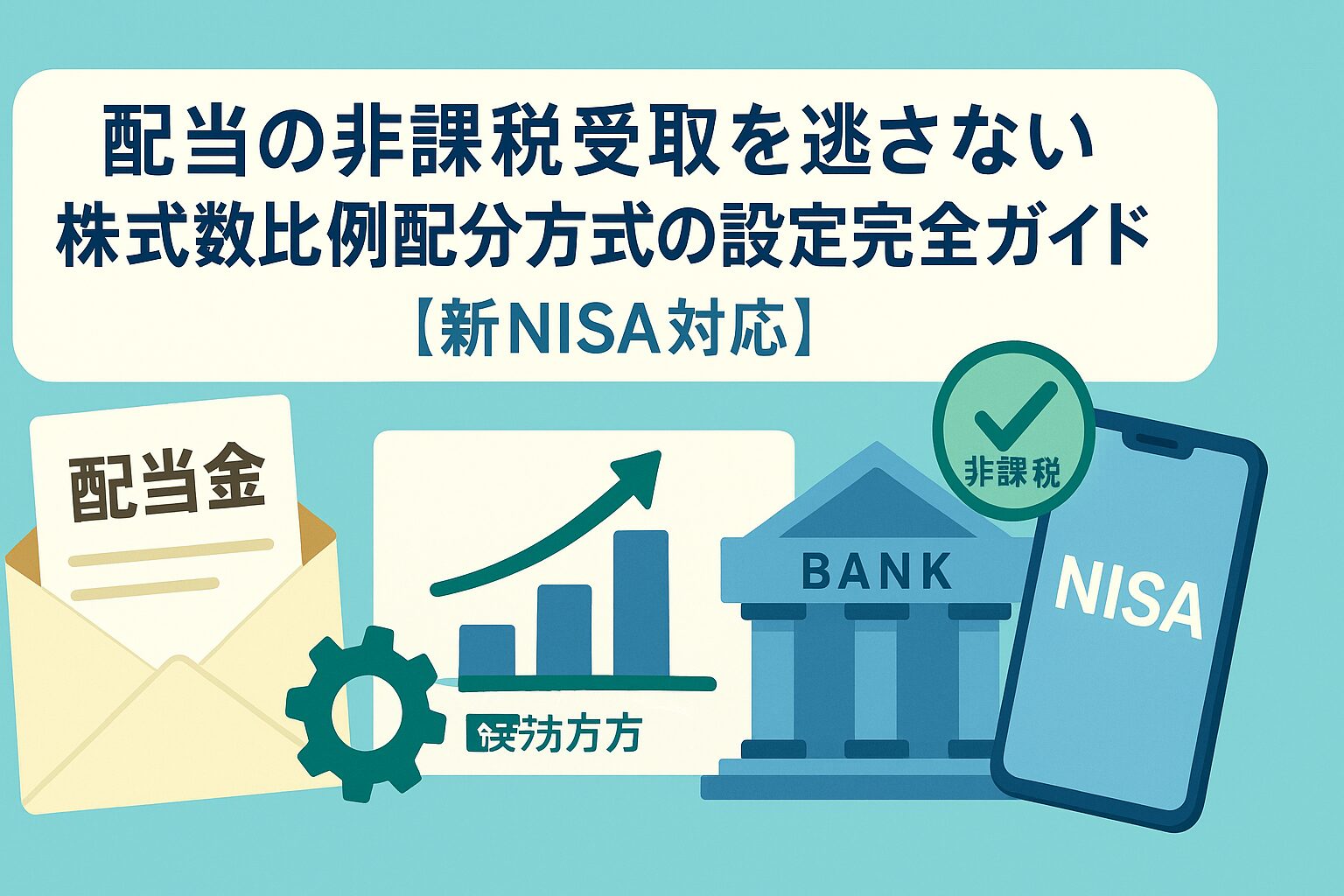この記事は、配当・分配金を新NISAで非課税に受け取るための実務ガイドです。
株式数比例配分方式の仕組み、銀行受取等との違い、SBI証券での設定手順、つまずきやすい注意点を整理します。
高配当株やETFを買う前に、まずこの設定を完了させておきましょう。
\まずはNISA口座の準備から/
非課税で受け取る仕組みと、設定を間違えたときの落とし穴

NISAで配当・分配金を非課税にする条件はシンプルです。
証券会社経由で受け取る=株式数比例配分方式に統一すること。
これを外すと、銀行口座受取や郵便受取になって課税扱いになりうる点が落とし穴です。
※補足:公募株式投資信託の分配金は金融機関経由で交付されるため、非課税適用に「株式数比例」の個別設定は不要です。
配当受取方式の比較
| 受取方式 | NISAでの非課税 | 受取口座 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 株式数比例配分方式 | ○(NISA対象の株式・ETF・REITの国内課税分) | 証券口座 | 証券会社経由で受取。NISAの非課税を適用しやすい。外国株は現地課税が残る場合あり。 |
| 登録配当金受領口座方式 | ×(課税扱いになりやすい) | 銀行口座 | 銀行受取だとNISAの非課税対象外になる可能性。NISAを活かすなら避ける。 |
| 配当金領収証方式 | ×(課税扱い) | 窓口(郵便局等) | 書類受取。NISA非課税の適用外。利便性も低い。 |
※スマホでは表が画面幅を超えます。横にスワイプしてご覧ください。
※方式変更は配当基準日前の申込が必要。直前は間に合わない場合があります(早めに設定)。
月1万円の高配当を設計するなら 👉 高配当株で月1万円積立する方法
どの器で受け取る? 👉 国内ETF vs 米国ETF
SBI証券での設定フロー(他社ユーザー向けの要点も)
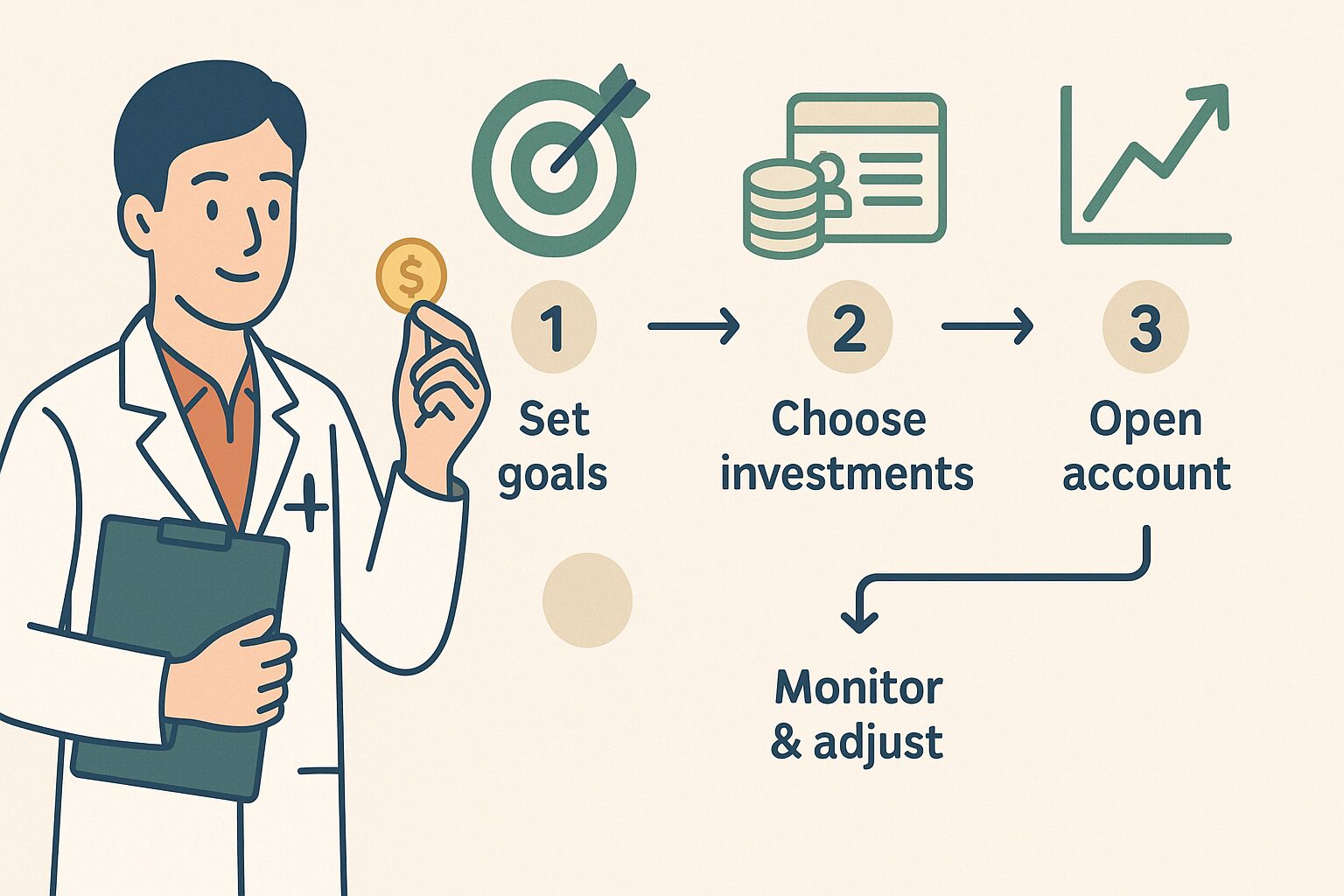
ここではSBI証券を例に、株式数比例配分方式への切り替え手順を解説します。
他社でも名称や画面は違っても、根本の考え方は同じです。
PCの基本手順
- ログイン後、口座管理(口座・サポート)へ進む。
- 配当金受取方式の設定画面を開く。
- 株式数比例配分方式を選択して保存する。
- 登録完了を確認する。
スマホアプリの基本手順
- アプリのマイページ(設定)を開く。
- 口座情報・各種設定をタップ。
- 配当金受取方式を株式数比例配分方式に変更して保存。
- 完了表示を確認する。
つまずきやすい注意点
- 名義一致は必須。口座名義と受取名義が異なるとエラーになることがあります。
- 基準日またぎは間に合わない場合があるため、早めの設定が安全です。
- 他社からの移管や口座区分変更の後は、再設定が必要になることがあります。
- 外国株の配当は現地課税(源泉)が残る場合があります。NISAは国内課税の非課税が中心です。
\設定が済んだら、つみたてと併走しよう/
Q&A:設定後の運用と、よくある誤解
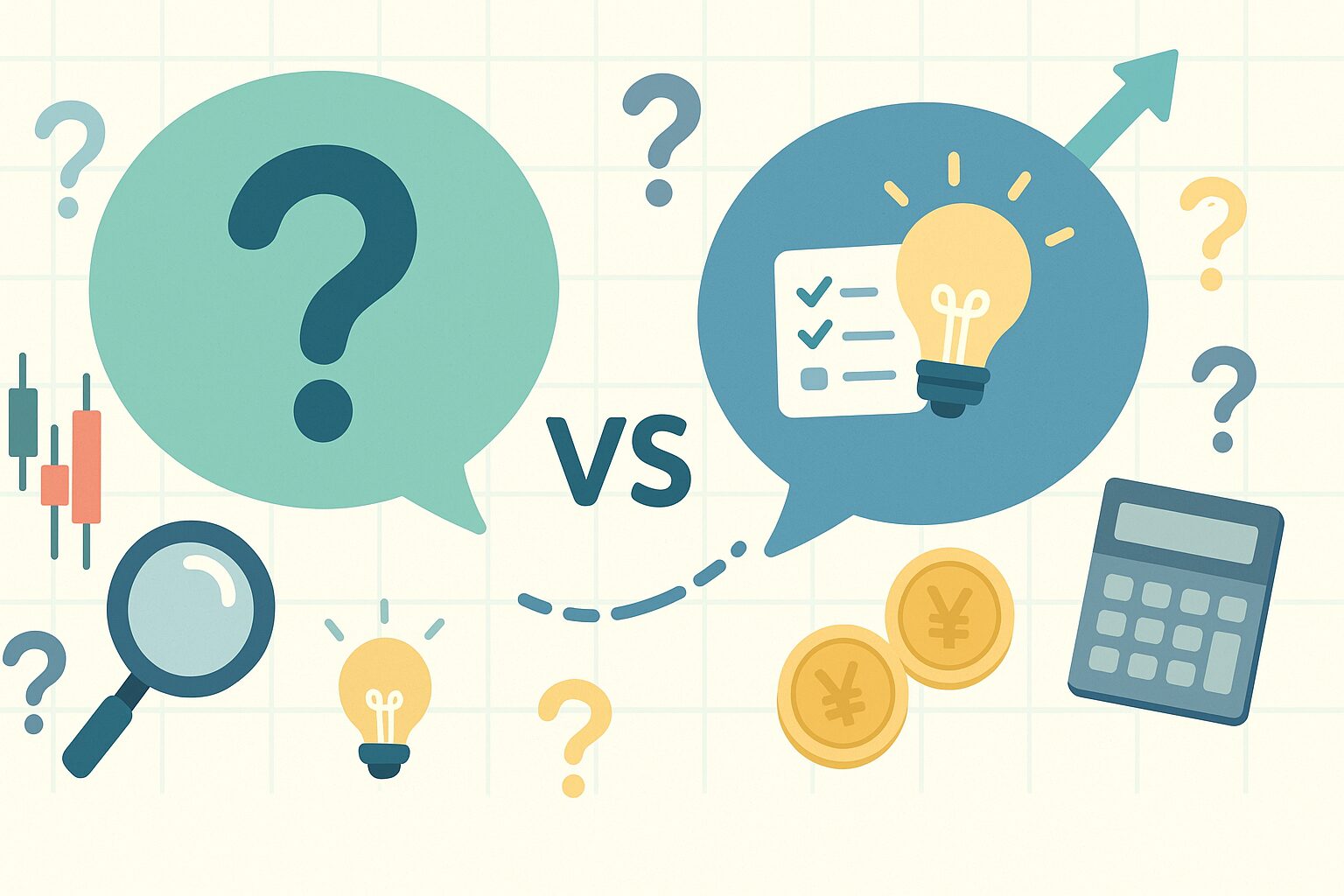
Q1.途中で方式を変えても大丈夫ですか。
大丈夫です。
ただし配当金の基準日直前では切り替えが間に合わない可能性があります。
余裕をもって早めに変更しましょう。
Q2.特定口座の配当課税とNISAの配当はどう違いますか。
NISAでは非課税枠内の配当・分配が国内課税の対象外です。
一方、特定口座の配当は通常どおり課税されます。
銘柄や数量を分けて持つときは、どちらで受け取るかを明確にしましょう。
Q3.ETFやREITの分配金も対象ですか。
国内上場のETF・REITは、NISAでの非課税対象になりえます。
株式数比例配分方式にして、証券会社経由で受け取りましょう。
Q4.外国株の配当は完全に非課税ですか。
いいえ。
NISAは国内課税の非課税が中心で、外国株の現地源泉税は課税されます。
また、NISA口座で受け取った配当は外国税額控除の対象外(二重課税にならないため)と案内されています。
月1万円投資との連動:キャッシュフローと複利の両立

高配当株や配当ETFは、配当が可視化されてモチベが続きやすい一方で、分散や減配リスクにも注意が必要です。
月1万円運用では、つみたて投信の自動積立で土台を作りつつ、必要に応じて成長投資枠で配当系を薄くのせるのが現実的です。
実務の型
- つみたて投資枠:全世界 or 米国の低コスト投信1本で自動積立。
- 成長投資枠:配当ETFや高配当株を少額で分散。まずは銘柄を絞り、慣れたら段階的に拡張。
- 配当は原則再投資で複利を最大化。
- 配分のズレは買い増しで戻す。売却ベースの調整は年1回で十分。
商品選びで迷わない 👉 つみたて投信の選び方
まとめ

ポイント
- NISAの配当・分配を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」に統一する。
- 銀行受取・領収証受取は課税扱いになりやすいので避ける。
- 月1万円運用は、つみたてで土台+配当系は薄く追加。配当は原則再投資。


\設定→つみたて→配当まで一気通貫/
👉 次はこちら:高配当株で月1万円積立する方法