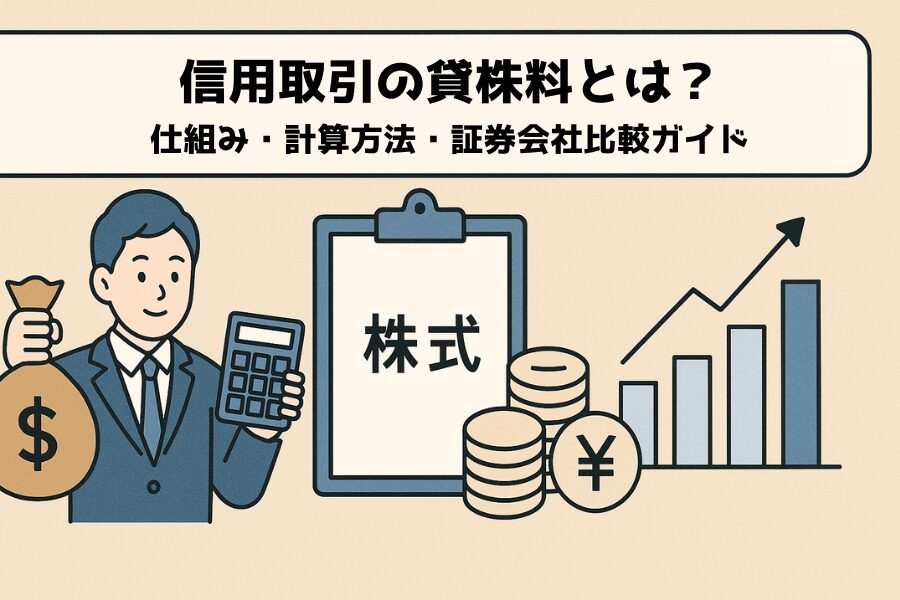信用取引は、少ない資金でも大きな取引ができる便利な仕組みです。
しかし、貸株料や逆日歩など独自のコストやリスクも存在し、仕組みを理解しないまま始めると損をする可能性があります。

本記事では、信用取引の貸株料の仕組みや計算方法、証券会社ごとの違い、コストを抑えるコツまで、初心者にもわかりやすく解説します。
また、制度信用取引と一般信用取引の違いや、貸株料が発生するタイミング、逆日歩のリスクについても具体例を交えて紹介します。
これから信用取引を始めたい方や、コストを抑えたい方はぜひ参考にしてください。
知識を身につけて、安心・納得のいく投資を目指しましょう。

ポイント
- 信用取引は証券会社から資金や株式を借りて行う仕組みである
- 貸株料は空売り時に発生するコストであり、計算式は「建玉金額×貸株料率÷365×日数」となる
- 制度信用取引と一般信用取引には返済期限や料率、対象銘柄に違いがある
- 貸株料や逆日歩は取引内容やタイミングによって大きく変動するため注意が必要である
- 各証券会社のコストやサービスを比較し、自分に合った取引方法を選択することが重要である
\口座開設は無料/
信用取引の貸株料とは?仕組みと基本知識

この章では信用取引の貸株料の仕組みと基本知識について解説します。
信用取引の基本概要
信用取引は、証券会社から資金や株式を借りて株の売買を行う仕組みです。
自分の資金や保有株だけではできない取引を可能にし、レバレッジ効果で利益を狙えます。
たとえば、手元資金が50万円でも、100万円分の株を買うことができます。
売りから入る「空売り」も信用取引の特徴で、株価が下がると利益が出る仕組みです。
初心者にとってはリスクもあるため、まずは少額から始めてみると安心でしょう。
貸株料の定義と役割
貸株料とは、信用取引で株を借りて売る(空売り)際に発生するコストです。
証券会社が投資家から株を集めて貸し出すため、その対価として貸株料がかかります。
主要ネット証券の貸株料は年率1.10%前後が一般的です。
たとえば100万円分の株を1カ月借りた場合、約916円程度の貸株料が発生します。
貸株料は売建玉(空売り)のみ発生し、買建玉ではかかりません。
コスト計算の際は「建玉金額×貸株料率÷365×日数」で算出できます。
制度信用取引と一般信用取引の違い
制度信用取引は、証券取引所が定めた銘柄とルールに従う取引です。
返済期限は6カ月以内と決まっており、貸株料や金利もほぼ統一されています。
一方、一般信用取引は証券会社独自のサービスで、返済期限が無期限の場合も多いです。
対象銘柄や貸株料率も証券会社によって異なります。
たとえば、楽天証券やSBI証券では一般信用取引の貸株料が年率1.10%と設定されていますが、キャンペーンや銘柄によっては異なる場合もあります。
それぞれの貸株料の特徴
制度信用取引の貸株料は、どの証券会社でもほぼ同じ水準で、年率1.10~1.15%程度が一般的です。
一方、一般信用取引は証券会社ごとに料率が異なり、短期・無期限・デイトレ専用など複数のプランが用意されています。
たとえば、デイトレ専用の「日計り信用」では貸株料が無料になるケースも存在します。
また、プレミアム銘柄や人気銘柄は貸株料が高く設定されることもあるため、事前に確認が必要です。
利用シーンの違い
制度信用取引は、短期間で売買したい場合や、一般信用取引で扱っていない銘柄を取引したい時に向いています。
たとえば、IPO直後の銘柄や流動性の高い大型株は制度信用での取引が主流です。
一般信用取引は、返済期限を気にせず長期で空売りしたい場合や、株主優待クロス取引(優待タダ取り)に活用されます。
自分の投資スタイルや目的に合わせて、どちらを使うか選択するのがポイントです。
貸株料が発生するタイミング
貸株料は、信用取引で新規売建を行った翌営業日から発生します。
日割りで計算され、返済(買い戻し)までの期間分がコストとなります。
たとえば、5日間売建を保有した場合は5日分の貸株料が発生。
日計り取引(当日中に決済)の場合でも1日分の貸株料がかかるため、短期売買でもコスト意識が必要です。
また、証券会社によっては約定日や受渡日ベースで計算方法が異なるため、取引前に確認しておくと安心です。

信用取引 貸株料の計算方法と実際のコスト

この章では貸株料の計算方法と実際のコストについて解説します。
貸株料の計算式と具体例
貸株料は、信用取引で株を借りて売建て(空売り)をした際に発生するコストです。
計算式は「建玉金額 × 年率貸株料 ÷ 365 × 保有日数」となります。
たとえば、100万円分の株を10日間借りた場合、年率1.10%の証券会社なら「100万円 × 1.10% × 10日 ÷ 365日」で約301円となります。
一方、年率1.15%の会社だと同じ条件で約315円です。
計算は日割りで行われるため、短期間で返済すればコストを抑えられます。
実際の取引では、建玉金額や日数によって負担額が変化する点に注意が必要です。
日割り計算のポイント
貸株料は営業日だけでなく、土日や祝日も含めた「暦日数」で計算します。
新規建ての受渡日から返済の受渡日まで、両端を含めて日数を数えます。
たとえば、水曜日に新規建て、木曜日に返済した場合、受渡日は金曜と月曜となり、土日を含めて4日分の貸株料が発生。
日計り取引(当日中に返済)でも1日分の貸株料が必要です。
計算ミスを防ぐため、受渡日ベースで日数を確認することが大切です。
建玉金額に応じたコスト比較
貸株料は建玉金額が大きいほど増加します。
例えば、50万円の株を年率1.10%で10日間借りると「50万円 × 1.10% × 10日 ÷ 365日=約150円」となります。
100万円なら同条件で約301円です。
証券会社によって年率が異なるため、同じ建玉金額・日数でもコストに差が出ます。
建玉を増やす場合は、貸株料の負担も比例して増える点を意識しましょう。
証券会社ごとの貸株料率の違い
2025年現在、主要ネット証券の制度信用取引における貸株料率は、SBI証券・楽天証券・DMM株が年率1.10%と最安水準です。
松井証券・マネックス証券・三菱UFJ eスマート証券は1.15%となっています。
わずかな差でも、取引回数や建玉金額が増えると無視できない金額になります。
証券会社選びでは、貸株料率だけでなく、手数料やサービスも比較すると良いでしょう。
なお、プレミアム金利が設定される銘柄もあり、1.0%を超えるケースも存在します。
実際にかかるその他の費用(手数料・金利など)
貸株料以外にも、信用取引にはさまざまなコストが発生します。
買建ての場合は「買方金利」がかかり、SBI証券の制度信用取引では年率2.80%、松井証券は3.10%など会社ごとに異なります。
売買手数料は取引金額やプランによって変動し、ネット証券では1日定額制や約定ごとプランが選択可能です。
また、管理料や名義書換料、逆日歩(品貸料)といった追加費用も発生する場合があります。
コストを正確に把握し、トータルで比較することが大切です。

\口座開設は無料/
信用取引 貸株料と逆日歩の違い・リスク

この章では貸株料と逆日歩の違い・リスクについて解説します。
逆日歩(品貸料)とは
逆日歩(ぎゃくひぶ、品貸料)は、信用取引で空売り(売り建て)をした際に、株式市場で貸し出せる株が不足した場合に発生する追加コストです。
通常、空売りを行うときは証券会社から株を借りて売りますが、売りたい人が多くて貸し出せる株が足りなくなると、証券金融会社が市場で不足分を調達し、そのコストを売り方に負担させます。
逆日歩は日々変動し、1株あたりの金額で発生します。
たとえば、1株あたり逆日歩が10円、100株保有なら1,000円が追加でかかる仕組みです。
貸株料と逆日歩の発生条件
貸株料は、証券会社から株を借りて空売りする際に必ず発生する“レンタル料”です。
年率1.1%前後が一般的で、建玉金額や日数に応じて日割りで計算されます。
一方、逆日歩は「株不足」のときだけ発生します。
売り建て注文が買い建て注文より多く、証券金融会社の在庫を超えてしまうと、入札で株を調達し、その費用が逆日歩として売り方に請求されるのです。
つまり、貸株料は常に発生し、逆日歩は需給バランスが崩れたときのみ発生します。
逆日歩が発生しやすいケース
逆日歩は、特定の条件下で発生しやすくなります。
たとえば、株主優待や配当の権利確定日前は、優待クロス取引(同時に買いと売りを建ててリスクを抑えつつ優待を得る手法)が増加し、売り建て注文が集中しやすいです。
また、発行済み株式数が少ない小型株や、貸借倍率が1倍未満の銘柄も注意が必要です。
貸借倍率とは、信用買い残数÷信用売り残数で算出され、1倍未満だと売りが多い状態を示します。
こうした状況では逆日歩が高額になるリスクが高まります。
貸株超過時のリスク
貸株超過とは、信用売りが信用買いを上回り、証券金融会社の貸し出せる株が足りなくなる状態です。
この場合、逆日歩が発生しやすくなり、しかも入札によって決まるため、思わぬ高額負担になることがあります。
過去には最高料率が10倍に引き上げられた例もあり、1日で数千円~数万円のコストが発生することも。
小型株や人気優待銘柄など、貸株超過のリスクが高い銘柄は特に注意が必要です。
投資家が注意すべきポイント
逆日歩は発生タイミングや金額を事前に予測しにくい点が厄介です。
特に、権利確定日付近や貸借倍率が低い銘柄では、逆日歩が突然高騰するケースも珍しくありません。
売り建てを行う前には、証券金融会社のサイトなどで直近の貸株残高や逆日歩の履歴を確認しましょう。
また、逆日歩が発生しやすい時期や銘柄は、投資家同士の情報共有や逆日歩予想ツールの活用も有効です。
リスクを回避するための対策
逆日歩リスクを減らすには、いくつかの具体策があります。
まず、貸借倍率が1倍以上の銘柄を選ぶことで、売り建て過多を避けやすくなります。
権利確定日直前の売り建ては控えるのも有効です。
小型株よりも流通量の多い大型株を選ぶことで株不足のリスクも下がります。
さらに、逆日歩が発生しない「一般信用取引」を利用する方法もあります。
証券会社によっては逆日歩予想ツールを提供しているので、こうしたツールを活用し、事前にリスクを把握しておくことが大切です。

信用取引 貸株料が安い証券会社の比較

この章では貸株料が安い証券会社の比較について解説します。
主要証券会社の貸株料率一覧
信用取引でコストを抑えたい方は、貸株料率の比較が重要です。
2025年時点で主なネット証券の制度信用取引における貸株料は、SBI証券・楽天証券・SBIネオトレード証券・GMOクリック証券が1.10%、松井証券・マネックス証券・三菱UFJ eスマート証券が1.15%となっています。
たとえば100万円分を1カ月借りる場合、SBI証券なら約917円、松井証券なら約958円が目安です。
このわずかな差も、取引回数が増えると無視できません。
また、デイトレードや一日信用取引を活用すれば、当日中決済で貸株料が無料になる証券会社も存在します。
証券会社ごとの特徴と選び方
証券会社は貸株料だけでなく、手数料やサービス面も異なります。
SBI証券や楽天証券は売買手数料が無料で、ネット証券の中でも人気が高いです。
松井証券は一日信用取引でのコストゼロが特徴で、短期売買に向いています。
自分の取引スタイルやサポートの必要性に応じて、最適な証券会社を選びましょう。
手数料・サービスの違い
ネット証券の多くは信用取引の売買手数料を無料にしています。
SBI証券や楽天証券などは、現物取引よりも安いコストで信用取引が可能です。
一方、総合証券では手数料が高めな分、対面でのアドバイスや資産運用の相談が受けられます。
また、各社でポイント還元やキャンペーンも異なるため、公式サイトで最新情報を確認してください。
サポート体制やツールの充実度
初心者の場合、サポート体制や取引ツールの使いやすさも大切です。
松井証券は専門スタッフによる無料相談や、分かりやすい取引画面が強みです。
SBI証券や楽天証券は、有人チャットやAIサポート、電話対応もあり、安心して取引できます。
また、マネックス証券は高機能なトレードツールを提供し、板発注やスピード注文が可能です。
▼口座開設について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
関連記事
コスト以外の比較ポイント
コストだけでなく、取扱銘柄数や情報提供サービスも比較ポイントです。
たとえば、IPO(新規公開株)や米国株の信用取引に対応しているか、投資情報や学習コンテンツが充実しているかも重要です。
また、スマホアプリの使い勝手や、資産管理ツールの有無もチェックしておきましょう。
自分の投資目的やライフスタイルに合った証券会社を選ぶことで、より快適に取引を進められます。

信用取引 貸株料を抑えるコツと注意点

この章では貸株料を抑えるコツと注意点について解説します。
貸株料を安く抑える方法
貸株料を少しでも安くしたい場合、まず証券会社ごとの貸株料率を比較しましょう。
2025年7月時点では、楽天証券やSBI証券、DMM.com証券など大手ネット証券が年率1.10%前後で競っています。
日計り信用(デイトレード)を活用すれば、貸株料が無料になるケースもあります。
また、一般信用取引を選ぶと逆日歩(品貸料)が発生しないため、コストが想定しやすくなります。
短期間での売建てや、権利付き最終日直前の取引は貸株料が高くなる傾向があるため、タイミングも意識してください。
証券会社選びのコツ
証券会社ごとに貸株料率や手数料、サービス内容が異なります。
例えば、楽天証券やSBI証券は売買手数料が無料で、貸株料も業界最低水準です。
加えて、キャンペーンやキャッシュバック、ポイント還元などの特典も充実しています。
取引ツールの使いやすさやサポート体制も比較ポイントです。
初心者の場合、サポートが手厚い証券会社を選ぶことで、安心して取引を始められます。
取引タイミングの工夫
貸株料は建玉を保有している日数分だけ発生します。
そのため、週末や祝日をまたぐ取引はコストがかさみやすいです。
例えば、金曜日に売建てを行うと、返済までの間に土日分も貸株料が発生します。
権利付き最終日直前は空売り需要が高まり、貸株料や逆日歩が急騰することもあります。
取引日や返済日を意識して、無駄な日数を減らす工夫が重要です。
コスト削減のためのシミュレーション活用
実際にどのくらいコストがかかるかは、証券会社が提供するシミュレーションツールを使うと具体的に把握できます。
建玉金額や貸株料率、保有日数を入力するだけで、日割りでコストが算出されるのです。
例えば「新規建時の株価×株数×貸株料率÷365×日数」で計算できます。
複数の証券会社で条件を変えて試算し、最もコストが安いパターンを選ぶのが賢い方法です。
シミュレーションを活用することで、思わぬ出費を防げます。
初心者が注意すべき落とし穴
初心者が陥りやすいのは、貸株料以外のコストやリスクを見落とすことです。
取引手数料が無料でも、品貸料(逆日歩)や管理料、名義書換料などが発生する場合があります。
また、保証金不足や株価急変による追加保証金(追証)リスクも見逃せません。
特に人気銘柄や権利付き最終日付近の売建ては、貸株料や逆日歩が急騰しやすいので要注意です。
事前に各コストを確認し、余裕を持った資金管理を心がけましょう。
最新情報のチェック方法
貸株料率や手数料は、証券会社や市場の状況によって頻繁に変わります。
公式サイトの「お知らせ」や「コスト比較ページ」を定期的に確認しましょう。
また、日本証券金融やJPX(日本取引所グループ)の公式サイトでは、貸株料や信用取引残高の最新データが公開されています。
SNSや投資系ニュースサイトも活用し、急な制度変更やキャンペーン情報を見逃さないようにしましょう。

まとめ

ポイント
- 信用取引は証券会社から資金や株式を借りて行う仕組みである
- 貸株料は空売り時に発生するコストであり、計算式は「建玉金額×貸株料率÷365×日数」となる
- 制度信用取引と一般信用取引には返済期限や料率、対象銘柄に違いがある
- 貸株料や逆日歩は取引内容やタイミングによって大きく変動するため注意が必要である
- 各証券会社のコストやサービスを比較し、自分に合った取引方法を選択することが重要である
今回は信用取引の貸株料について説明してきました。
最後にもう一度まとめます。
信用取引では、資金や株式を借りて取引できる一方、貸株料や逆日歩など独自のコストが発生します。
制度信用取引と一般信用取引でルールや料率が異なるため、取引前に内容を確認することが重要です。
貸株料は売建玉のみ日割りで発生し、逆日歩は需給バランス次第で大きく変動します。
証券会社ごとのコストやサービスを比較し、シミュレーションツールも活用しましょう。
常に最新情報をチェックし、リスク管理を徹底することで、安心して信用取引を活用できます。


\口座開設は無料/
続きを見る 続きを見る 続きを見る

証券会社ランキング|おすすめネット証券を徹底比較【2025年最新】

SBI証券口座開設のやり方・申し込み方法を徹底解説【初心者向け】

楽天証券の口座開設方法|スマホで最短申込、翌営業日スタート
参考: