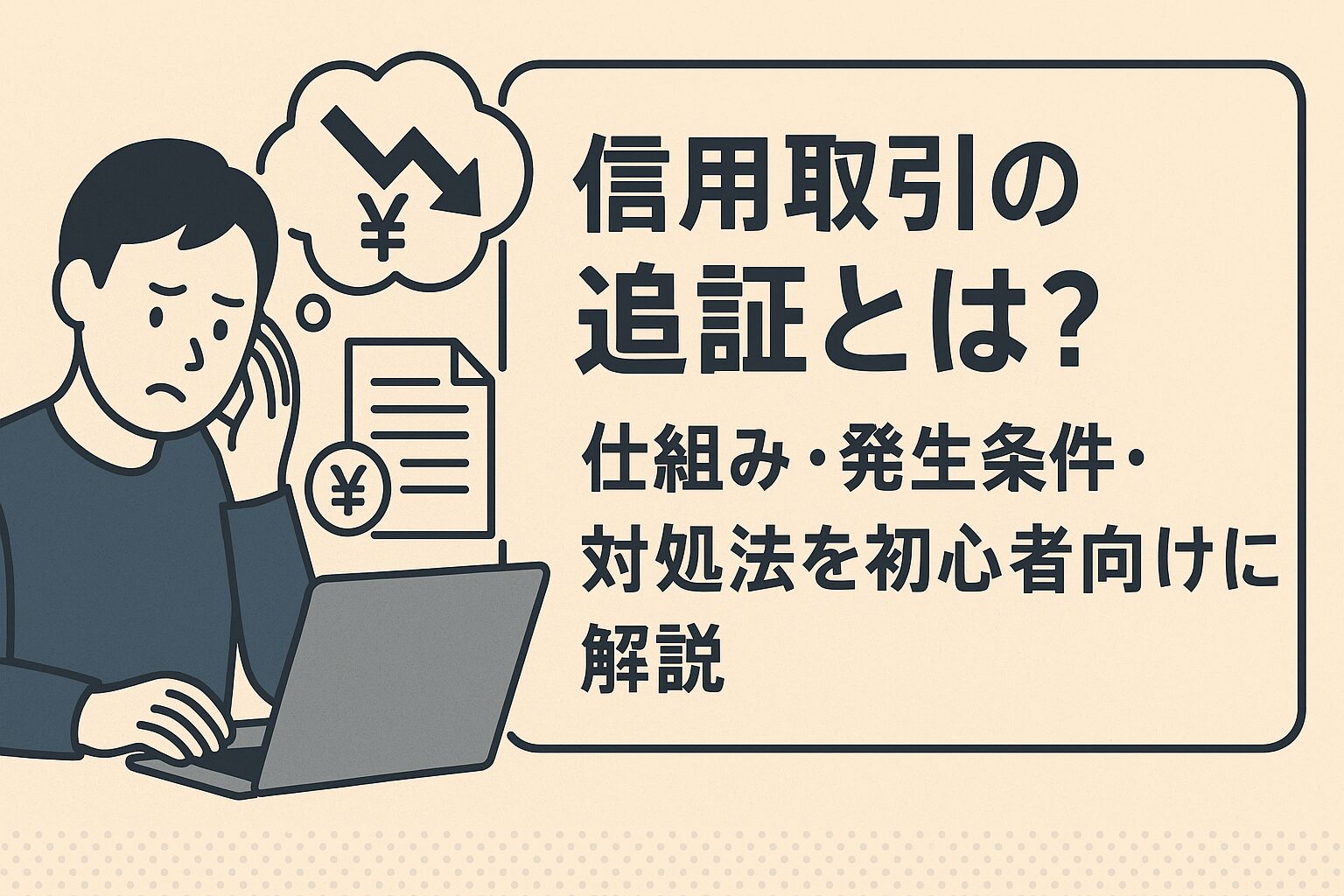信用取引を始めるとき、多くの人が「追証」という言葉に不安を感じるものです。
株価の急落や相場の変動によって、思わぬタイミングで追加保証金の請求が発生することがあります。

追証は、信用取引のリスク管理において欠かせないポイントです。
証券会社ごとにルールや計算方法が異なるため、事前の確認や資金管理がとても重要となります。
「知らなかった」では済まされない場面も多いため、この記事では追証の基本から具体的な対処法、よくある失敗例まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。
これから信用取引を始める方も、すでに経験がある方も、リスクを最小限に抑えるためのヒントをぜひ参考にしてください。

ポイント
- 追証は、信用取引で保証金維持率が基準を下回った場合に発生する追加保証金である
- 追証を入金しないと、証券会社が強制的に建玉を決済し、損失が確定することとなる
- 追証と不足金は発生理由やタイミングが異なり、どちらも追加の入金が必要となる
- 追証の発生条件や対応期限は証券会社ごとに異なるため、事前確認が重要である
- 追証の仕組みやリスクを理解し、資金管理やルール徹底で突然の請求に備えることが大切である
\口座開設は無料/
追証とは何かをわかりやすく解説

この章では追証について解説します。
追証の基本的な意味
追証(おいしょう)は、信用取引を行う際に発生する追加保証金のことを指します。
たとえば、株価が大きく下落した場合、証券会社が定める「保証金維持率」を下回ると、投資家は追加で資金を入金しなければなりません。
この「追加で入れるお金」が追証です。
もし追証を入れないと、証券会社が強制的に保有している株を売却し、損失が確定します。
初心者の方は、追証が発生する仕組みを知らずに取引を続けてしまい、突然大きな負担を背負うケースも珍しくありません。
追証はリスク管理の重要なポイントなので、仕組みをしっかり理解しておくことが大切です。
信用取引における追証の役割
信用取引では、自己資金の数倍の金額で株を売買できます。
このとき、証券会社に預ける「委託保証金」が担保となるのです。
もし株価が想定よりも下がった場合、担保の価値が減少し、証券会社はリスクを回避するために追加保証金(追証)を請求します。
たとえば、100万円分の株を信用取引で購入し、保証金維持率が20%の場合、株価が大きく下がると維持率を下回ることがあります。
その場合、証券会社から「〇日までに追証を入金してください」と通知がくるのです。
追証を入金しなければ、証券会社が自動的に建玉を決済し、損失が確定する流れです。
この仕組みは、証券会社が損失リスクを最小限に抑えるために不可欠なものといえます。
追証と不足金の違い
追証とよく混同される言葉に「不足金」があります。
追証は、信用取引の保証金維持率が基準を下回った場合に発生する追加保証金のことです。
一方、不足金は、取引の決済や手数料の支払いなどで証券口座の残高がマイナスになった場合に発生します。
たとえば、追証は「信用取引でのリスク管理」のために請求されますが、不足金は「現金残高が足りない」ことを意味します。
どちらも追加の入金が必要ですが、発生するタイミングや背景が異なります。
この違いを理解しておくことで、突然の請求に慌てずに対応できるようになります。

追証が発生する仕組みと条件

この章では追証が発生する仕組みと条件について解説します。
追証発生のタイミング
信用取引では、証券会社からお金を借りて株を売買します。
このとき、投資家は「保証金」を預けて取引を始めます。
株価が下落し、口座内の資産が一定の基準を下回ると「追証(追加保証金)」が発生するのです。
追証のタイミングは、保証金維持率(=担保として預けている資産の割合)が証券会社の定める水準を下回った瞬間です。
たとえば、保証金維持率が20%に設定されている場合、時価評価でこの水準を割り込むと追証が発生します。
追証発生の通知は、証券会社の取引画面やメールで届くことが多いです。
通知後、一定期間内に追加の保証金を入金しなければなりません。
この期間は証券会社によって異なりますが、一般的には1~3営業日以内が多いです。
入金が間に合わない場合、証券会社が強制的に建玉を決済することがあります。
株価下落による保証金維持率の低下
追証が発生する主な原因は、保有株の価格が下がることです。
たとえば、100万円分の株を30万円の保証金で買った場合、株価が急落して評価額が80万円になったとします。
このとき、保証金維持率は「(受入保証金合計-建玉評価損-諸経費等+決済損益-信用取引に係る立替金)÷建玉金額」で計算されます。
価格下落により維持率が証券会社の基準を割り込むと、追加保証金が必要となってしまうのです。
特に、相場が大きく変動したときは、短時間で追証が発生するケースも珍しくありません。
こうしたリスクを避けるには、余裕を持った資金管理が重要です。
証券会社ごとの基準の違い
追証の発生条件や維持率の基準は、証券会社ごとに異なります。
一般的な維持率は20~30%前後ですが、中には40%を設定している会社も。
また、追証発生後の対応期限や入金方法も各社で異なります。
たとえば、A証券では「翌営業日の15時までに入金」、B証券では「2営業日以内に対応」といった違いがあります。
このため、取引前に自分が利用する証券会社のルールを必ず確認しましょう。
基準が厳しい証券会社を選ぶと、リスク管理がしやすくなりますが、資金効率は下がる可能性もあります。
追証発生の具体的な例
具体例で追証の流れを説明します。
たとえば、あなたが30万円の保証金で100万円分の株を購入したとしましょう。
このとき、証券会社の維持率基準が20%の場合、株価が急落して評価額が75万円を下回ると追証が発生します。
計算式は「(受入保証金合計-建玉評価損-諸経費等+決済損益-信用取引に係る立替金)÷建玉金額」で、維持率が20%を割ると追加保証金が必要です。
追証発生後、証券会社からメールや取引画面で通知が届きます。
通知を受けたら、指定された期日までに不足分を入金するか、保有株の一部を売却して維持率を回復させる必要があるのです。
対応が遅れると、証券会社が自動的に建玉を決済し、損失が確定するリスクが高まります。
よくある誤解と注意点
追証に関して多い誤解の一つは、「追証が発生してもすぐに強制決済される」と思い込むことです。
実際には、証券会社からの通知後、一定の猶予期間が設けられています。
また、「追証=損失確定」と考える方もいますが、追証はあくまで追加保証金の入金義務です。
入金や建玉の一部決済で維持率を回復できれば、強制決済を回避できます。
さらに、証券会社ごとに追証発生の基準や対応方法が異なる点も見落としがちです。
自分の利用する証券会社のルールや通知方法、期日を事前に確認し、万が一の際に迅速に対応できる準備が大切です。

\口座開設は無料/
追証が発生した場合の対処方法

この章では追証が発生した場合の対処方法について解説します。
追加保証金の入金方法
追証が発生した場合、まず証券会社から「追加保証金を入金してください」と案内されます。
多くの証券会社では、インターネットバンキングやATMからの振込、証券口座への直接入金など複数の方法が用意されているので安心です。
例えば、SBI証券や楽天証券では、即時入金サービスを利用すると、リアルタイムで保証金が反映されるので、締切ギリギリの対応にも役立ちます。
入金期限は通常、追証発生日の翌営業日や2営業日以内と短い場合が多いです。
期限を過ぎると強制決済が行われるため、通知を受け取ったらすぐに対応しましょう。
建玉の一部または全部を決済する方法
追証を回避するもう一つの方法は、保有している建玉(ポジション)の一部または全部を決済して、保証金維持率を回復させることです。
具体的には、損失が出ている銘柄を売却し、証券会社の定める基準をクリアすれば追証が解消されます。
たとえば、複数銘柄を保有している場合、損失の大きいものから順に売却することで、必要な保証金を減らすことが可能です。
この方法は、手元資金が足りないときにも有効ですが、損失が確定する点には注意が必要です。
証券会社の取引画面から簡単に決済できるため、慌てずに操作方法を確認しましょう。
証券会社からの通知と対応フロー
追証が発生すると、証券会社はメールや取引画面、電話などで速やかに通知を行います。
通知内容には、追証の発生理由、必要な入金額、入金期限、未対応時のリスクなどが明記されています。
通知を受け取ったら、まず内容をよく確認し、入金か建玉決済か、どちらで対応するかを決めましょう。
証券会社によっては、取引画面に専用の「追証対応ページ」が用意されている場合もあります。
期限までに対応しないと、強制的に建玉が決済され、損失が確定します。
通知を見逃さないよう、メール設定やアプリのプッシュ通知を有効にしておくと安心です。
追証対応のよくある失敗例
初心者が陥りやすい失敗例として、通知を見落として対応が遅れるケースがあります。
また、入金額の計算ミスや、銀行の営業時間外で入金が間に合わないことも少なくありません。
建玉を決済する際に、損失を恐れて決断が遅れ、結果として損失が拡大することもあります。
さらに、複数の証券会社を利用している場合、どの口座で追証が発生しているか混乱することも。
こうしたミスを防ぐためには、日々の残高や建玉状況をこまめに確認し、追証発生時は冷静に対応することが重要です。

追証を回避するためのポイント

この章では追証を回避するためのポイントについて解説します。
リスク管理の基本
信用取引で追証を避けるためには、リスク管理が欠かせません。
まず、自分がどの程度の損失まで許容できるかを明確に決めておきましょう。
投資額全体に対して、1回の取引で失ってもよい金額をあらかじめ設定しておくと、冷静な判断がしやすくなります。
また、相場が大きく動いた場合のシナリオも想定しておくことが重要です。
「もし株価が急落したらどうするか?」といったケースを事前に考えておけば、パニックになりにくくなります。
余裕を持った保証金設定
保証金は、できるだけ余裕を持って設定するのが鉄則です。
最低限の保証金で取引を始めると、ちょっとした値動きでも維持率が下がり、追証のリスクが高まります。
たとえば、証券会社が定める最低保証金率が20%の場合、30%や40%など余裕を持たせて資金を入れておくと安心です。
余裕資金を多めに預けておけば、急な相場変動にも耐えやすくなります。
損切りルールの徹底
損失が一定額に達したら、迷わずポジションを手仕舞う「損切りルール」を徹底しましょう。
感情に流されて損失を抱え続けると、追証につながる危険が高まります。
たとえば、「5%下落したら必ず売却する」といった明確な基準を決めておくと、冷静に行動しやすくなります。
自分で決めたルールを守ることが、長期的な資産防衛につながります。
日々のポジション管理のコツ
毎日のポジション管理も、追証回避には欠かせません。
取引後は必ず証券会社の口座画面で、保証金維持率や評価損益をチェックしましょう。
相場が急変した場合、早めに建玉を調整することでリスクを軽減できます。
また、複数の銘柄に分散投資することで、1つの株価急落による影響を抑えることが可能です。
日々の小さな確認が、大きな損失を防ぐ第一歩となります。
-

-
分散投資とは?リスクを抑えて安定運用を目指す4つの方法と注意点
続きを見る
初心者がやりがちなミスと対策
初心者がよく陥るミスに「一度に大きな金額を投資する」「損失を引きずる」「保証金ギリギリで取引する」などがあります。
これらはすべて追証リスクを高める行動です。
対策としては、まず少額から始めて経験を積むことが大切です。
また、損失が出たときは「なぜ損したのか」を振り返り、次に生かす意識を持ちましょう。
保証金に余裕を持たせる、損切りルールを守る、といった基本を徹底することで、失敗を減らせます。
失敗を恐れず、学びながらステップアップしていく姿勢が大切です。

追証が払えない時のリスクと注意点

この章では追証が払えない時のリスクと注意点について解説します。
追証未入金時のペナルティ
追証(追加保証金)を指定された期日までに入金しない場合、証券会社は厳しいペナルティを科します。
まず、未入金のまま放置すると、証券会社は自動的に保有している株や建玉を強制的に決済します。
この強制決済によって、損失が確定し、元本以上の損失が発生するケースもあるのです。
さらに、追証未入金の履歴が残ると、今後の取引や信用取引の利用に影響することも少なくありません。
強制決済の流れ
追証の入金期限を過ぎると、証券会社は自動的に強制決済を実行します。
この際、投資家の意思とは無関係に、保有しているすべてのポジションが市場価格で売却されます。
相場が急落している場合、想定以上の損失が発生することもあり、元本を大きく超える負債を抱えるリスクも否定できません。
強制決済の通知は、メールや取引画面で行われるため、見逃さないよう注意が必要です。
口座凍結や法的措置の可能性
強制決済後も損失が埋まらず、証券口座がマイナス残高となった場合、証券会社は不足分の入金を求めます。
この請求に応じない場合、証券口座が凍結され、以後の取引ができなくなることがあります。
さらに、未払いが続くと、証券会社が法的措置を取ることもあり、最悪の場合は財産の差し押さえや裁判に発展するケースも存在するのです。
最悪のケースとその回避策
追証を払えないまま放置すると、最終的には多額の負債や法的トラブルに発展する可能性があります。
例えば、相場の急落で強制決済が間に合わず、借金を背負うケースも実際に報告されています。
こうしたリスクを避けるためには、日頃から余裕を持った保証金設定、損切りルールの徹底、ポジション管理の見直しが不可欠です。
万が一追証が発生した場合は、早めに証券会社へ連絡し、分割払いや相談の余地があるか確認するのも有効な手段です。
困った時の相談先・サポート窓口
追証の支払いが難しいと感じた場合、まずは取引している証券会社のカスタマーサポートに相談しましょう。
証券会社によっては、分割払いや一時的な猶予など、柔軟な対応をしてくれる場合もあります。
また、金融庁や日本証券業協会など、第三者機関の相談窓口も利用可能。
一人で悩まず、早めに専門機関へ相談することで、最悪の事態を回避できる可能性が高まります。

まとめ

ポイント
- 追証は、信用取引で保証金維持率が基準を下回った場合に発生する追加保証金である
- 追証を入金しないと、証券会社が強制的に建玉を決済し、損失が確定することとなる
- 追証と不足金は発生理由やタイミングが異なり、どちらも追加の入金が必要となる
- 追証の発生条件や対応期限は証券会社ごとに異なるため、事前確認が重要である
- 追証の仕組みやリスクを理解し、資金管理やルール徹底で突然の請求に備えることが大切である
今回は追証について説明してきました。
最後にもう一度まとめます。
信用取引における追証は、予想外の株価下落などで発生しやすく、放置すると強制決済や多額の損失につながる重大なリスクです。
証券会社ごとにルールや対応期限が異なるため、事前にしっかり確認し、資金管理と損切りルールを徹底しましょう。
追証が発生した場合は、通知内容を落ち着いて確認し、早めに入金や建玉の調整で対応することが重要です。
もし支払いが難しい場合は、すぐに証券会社や専門窓口に相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。
日々の管理と冷静な対応が、安心して信用取引を続けるカギとなります。


\口座開設は無料/
続きを見る 続きを見る 続きを見る

証券会社ランキング|おすすめネット証券を徹底比較【2025年最新】

SBI証券口座開設のやり方・申し込み方法を徹底解説【初心者向け】

楽天証券の口座開設方法|スマホで最短申込、翌営業日スタート
参考: