

決算発表は、企業の業績・見通し・株主還元の最新情報がまとまって公開される重要イベントです。
株価は「実績そのもの」よりも「市場の期待とのズレ」で動きやすく、良い決算でも期待超えでなければ下がることもあります。
多くの企業は引け後(取引終了後)に適時開示で発表しますが、正午や場中に出るケースもある点は覚えておきましょう。
ポイント
- 株価は「結果」よりも「期待との差」で動きやすい
- 注目は「売上・利益」「ガイダンス(見通し)」「配当・自社株買い」
- 直後はボラティリティが上がりやすい—慌てず一次情報で確認
関連:👉 運用報告書の見方(実質コスト)|👉 同一指数“寄せ替え”の手順|👉 年次メンテの型
決算発表が株価に与える影響:まずは基本

「期待とのギャップ」で動く
同じ“増収増益”でも、市場予想をどれだけ上回った/下回ったかで反応は変わります。
コンセンサス超え(ポジティブサプライズ)なら買いが入りやすく、未達(ネガティブサプライズ)なら売りが出やすいのが通例です。
瞬間的にボラティリティが上がる
アルゴリズム取引の影響もあり、秒〜分単位で素早く価格が反応する場面が増えています。
出来高が膨らみ、スプレッドが広がることも。
短期売買は指値・数量管理が大切です。
適時開示の“どこ”を見る?
- 売上・営業利益・当期純利益の前期比/会社計画比/コンセンサス比
- ガイダンス(通期・翌期の見通し)の新発表・修正
- 株主還元:配当方針(配当性向・DOE)・自社株買いの有無と規模
- セグメント別の成長ドライバー/一過性要因(特損等)の有無
決算前後の値動きパターンをつかむ

決算“前”に起きやすいこと
- 期待先行の上げ/失望先行の下げ(思惑で動きやすい)
- 同業の先出し決算・外部ニュースでの“連想”
- 出来高の減少(様子見)または先回りの増加(思惑)
決算“直後”に起きやすいこと
- ギャップアップ/ダウン(寄り付きの窓)
- アナリストのレーティング変更・目標株価見直し
- 会社側説明会・質疑応答のトーンで二段目の値動き


決算で“必ず”チェックしたい3点

① 売上・利益の成長と質
単なる増減だけでなく、粗利率・販管費率・営業CFの動きで“成長の質”を確認。
補助金や一過性益での押し上げは、注記で見抜けます。
② ガイダンス(見通し)の新情報
強気/慎重のいずれも株価に直結。
想定為替・資源価格・在庫調整などの前提条件に注目しましょう。
③ 株主還元(配当・自社株買い)
増配や自社株買いは好材料になりやすい一方、**必ず騰がると断定はできない**点に注意。
なお配当は一般に「中間は取締役会」「期末は株主総会決議」ですが、定款で取締役会に委任して期末も取締役会決議とする会社もある—という但し書きを覚えておくと◎。
関連:👉 自社株買いと株価の関係|👉 値幅制限と翌日の理論値
実務:決算日にどう動く?(初心者~中級者の型)

初心者:まずは“見てから”
- 場中の売買は最小に(ギャップ・スプレッド拡大の回避)
- 引け後に適時開示(決算短信・説明資料)を確認
- 翌日の寄り付き後、板と出来高を見ながら少額で調整
中級者:前提とシナリオを用意
- コンセンサスと会社計画のレンジを把握し、上振れ/下振れの行動を先に決める
- 決算説明会スライド・Q&Aをチェック(2段目の材料)
- 短期は損切り基準(%またはテクニカル)を事前設定
共通の落とし穴
- 「良決算=必ず上昇」の思い込み
- 一過性要因を“実力”と誤認
- ボラティリティ拡大時の逆指値未設定
関連記事:👉 PTS取引の時間・注文可否・手数料|👉 CPI/雇用統計/FOMCの日本時間まとめ
よくある質問(FAQ)
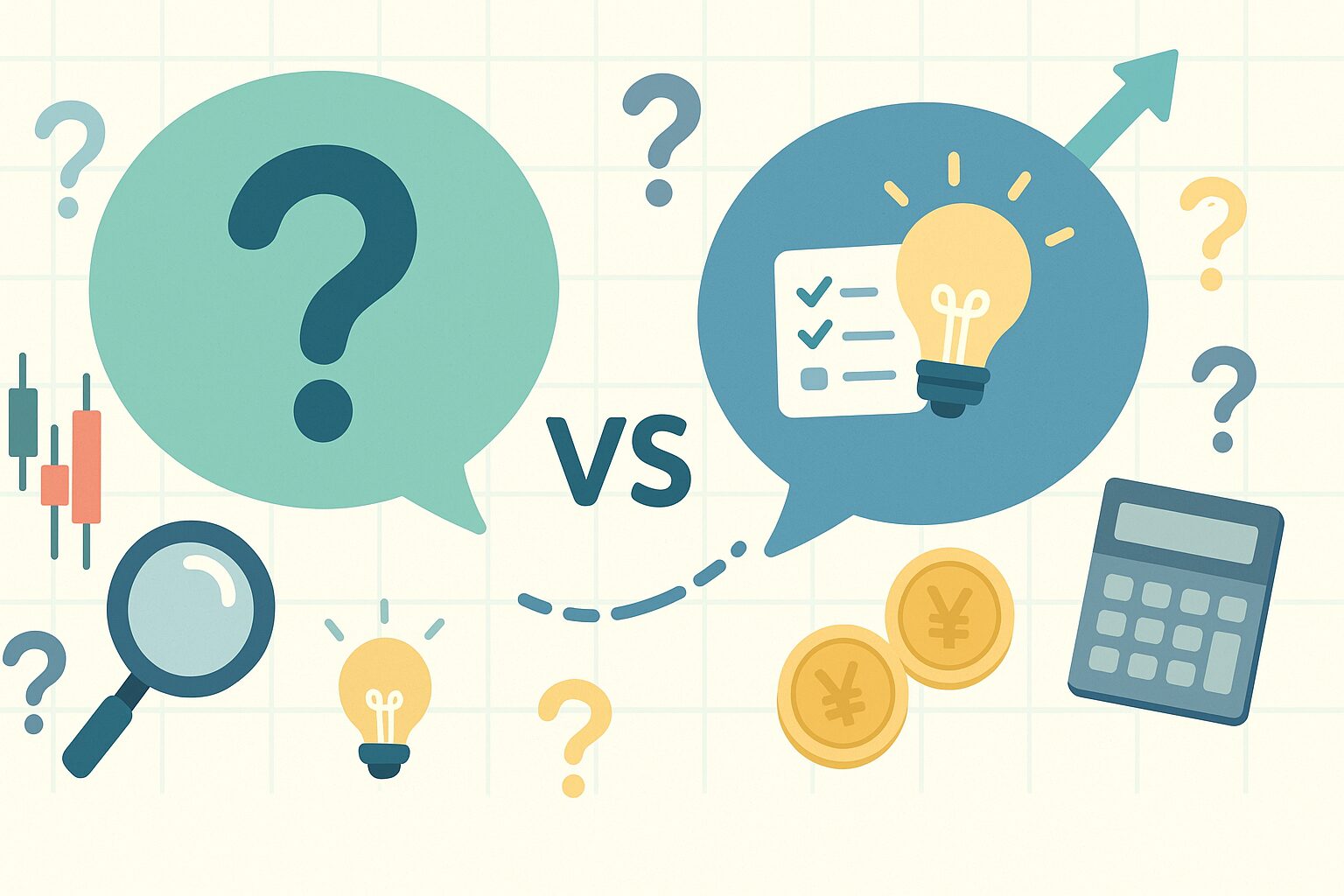
Q. 決算が良いのに下がるのはなぜ?
予想が“さらに”強く、期待が織り込み済みだった可能性。
来期ガイダンスが慎重だった、コスト増・一過性益の反動なども下落要因になります。
Q. 決算を跨ぐべき?避けるべき?
短期はボラティリティ拡大でリスク高。
跨ぐなら数量を抑える、ヘッジ(コール/プット・分散)を検討。
長期は基本方針を優先し、過度な売買を避けるのが無難です。
Q. 配当や自社株買いはどれくらい株価に効く?
一般にポジティブですが、規模・継続性・業績見通しとセットで評価されます。
短期の上昇後に伸び悩むケースも珍しくありません。
まとめ

ポイント
- 鍵は「結果」×「期待との差」—直後はボラ上昇に注意
- チェックは「売上・利益」「ガイダンス」「還元(配当・買い)」
- 初心者は“見てから少額”、中級者は事前シナリオと損切り基準


\口座開設へ進む/
👉 次はこちら:自社株買いと株価:上がりやすさの理由と注意点 / PTSで決算直後の値動きをキャッチする
