

ETFの分配金捻出売りは、毎年注目される市場イベントです。
ETFが分配金を支払うために保有株や先物を売却することで、一時的に値動きが大きくなる局面が生まれる場合があります。
例年、国内ETFは7月上旬に決算や分配が集中する傾向がありますが、具体的な日付は銘柄ごとに異なるため、必ず運用会社の最新開示を確認します。


ポイント
- 分配原資確保のための機械的な売りが需給を揺らすことがある
- 決算・基準・権利落ち・支払の各日付はETFごとに異なる(要・公式確認)
- 短期の下押し/ボラ拡大が出ても、売り一巡で落ち着くケースがある
- 指数寄与度が高い銘柄ほど相対的に影響が可視化されやすい
- 実務は「スケジュール把握→持ち高調整→分割/逆指値→再投資」が基本
ETF分配金捻出売りの仕組みと時期



ETF分配金捻出売りとは
ETFは組み入れ銘柄から受け取る配当などを原資に分配しますが、現金が不足または偏在する場合、保有する現物株や先物を売却してキャッシュを確保することがあります。
これは企業価値の変化ではなく需給要因です。
短期の値動きが拡大する局面がある一方、売り一巡後に落ち着くこともあります。
分配に関わる主要日付
決算日・基準日(Record Date)・権利落ち日(Ex-Dividend)・支払日(Pay Date)の順序を理解します。
具体の日付・間隔はETFごとに異なるため、運用会社の最新開示で確認します。


権利月の早見(国内ETFの代表例)

※決算頻度・権利落ち月・支払月は変更される場合があります。必ず最新の公式資料をご確認ください。
※横にスクロールしてください。
| ティッカー | 名称 | 決算頻度 | 権利落ち月(例) | 支払月(例) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 年1回 | 7 | 8 | 要・公式スケジュール確認 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 年1回 | 7 | 8 | 要・公式スケジュール確認 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF(JDR) | 年4回 | 3・6・9・12 | 翌月以降 | JDRの開示を参照 |


“受渡ベース(T+2)”での注意
- 権利付き最終売買日と権利落ち日のズレは受渡(T+2)で決まる。連休や月末は特に注意が必要。
- 捻出売りの実需は権利月の前後に分散する場合がある。薄い板の時間帯はスリッページに注意。
- 分配は価値の付け替えの側面がある。長期は分配再投資と積立の設計を優先。
市場への影響



短期の下押しとボラティリティ上昇
機械的な売りが重なると日中の値幅が広がりやすくなります。
指数ウエイトが大きい銘柄は影響が可視化されやすい一方、必ずしも同じ日に同じ動きになるとは限りません。
売り一巡後の挙動
出来高の減速や板の落ち着き、安値切り上げなどのサインがそろうと収れんしやすいです。
他材料(マクロ・金利・決算)が優先される局面もあるため、シナリオは複線化します。
規模感の目安

過去の報道では、国内ETFの分配金捻出売りが短期(2日間)に集中し、1兆円超との売り観測が話題になりました。
また、2025年については1.2兆円強を上回る規模の売りが出る見通しとの解説もあります(推計は前提・時点で変動します)。


備え方と攻め方
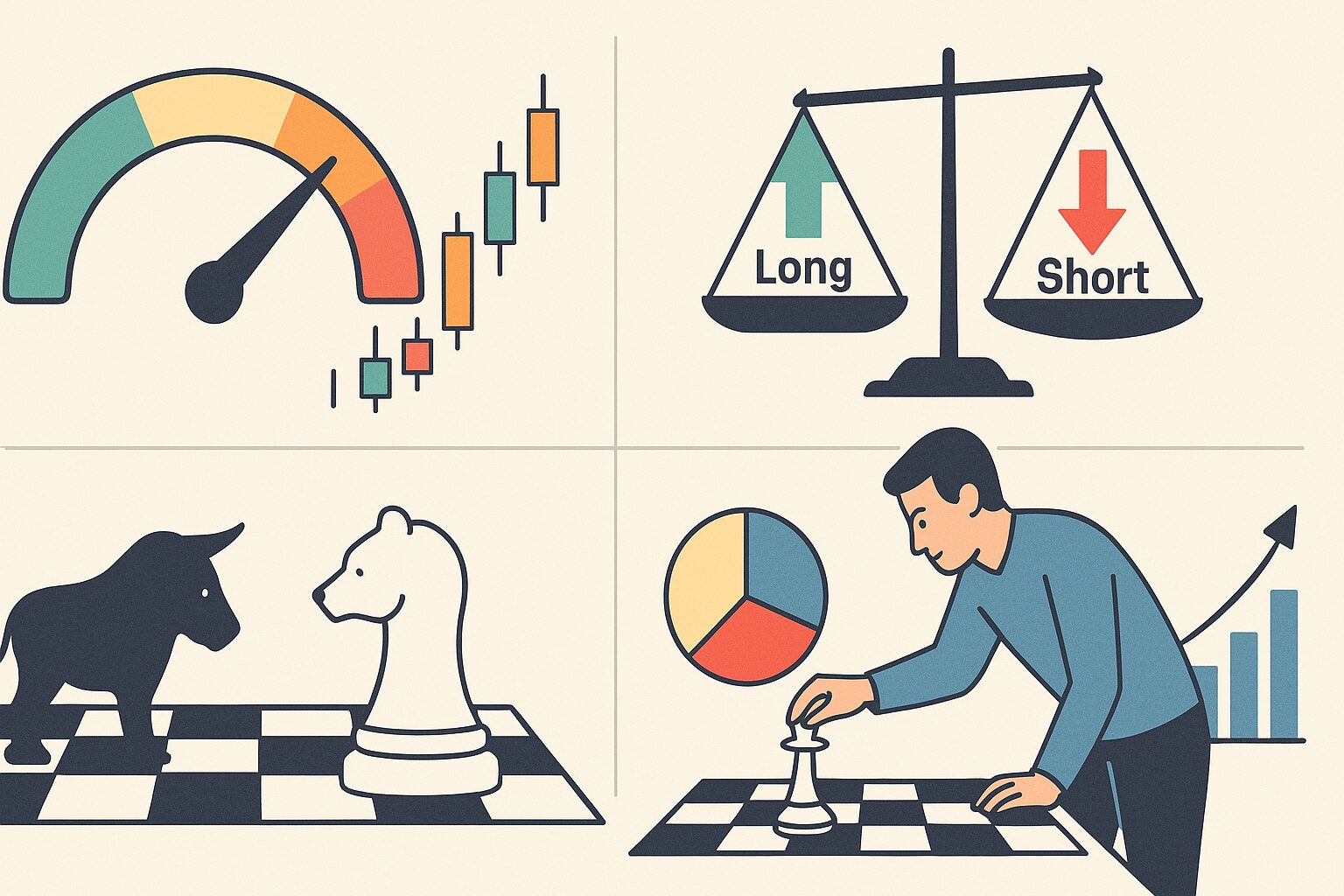
事前準備
保有・監視ETFの公式スケジュールを整理し、想定ウィンドウで持ち高やヘッジを調整します。
無分配方針のETFもあるため、目論見書の確認を習慣化します。
執行ルール
寄り引けのぶれに備え、分割指値や逆指値で損失を数量または割合で固定します。
押し目は複数条件がそろってから段階的に拾います。
分配再投資
受け取った分配金を同カテゴリへ再投資すれば、複利の観点で合理的です。
イベント後の押し目と重なるなら効率的です。


よくある質問
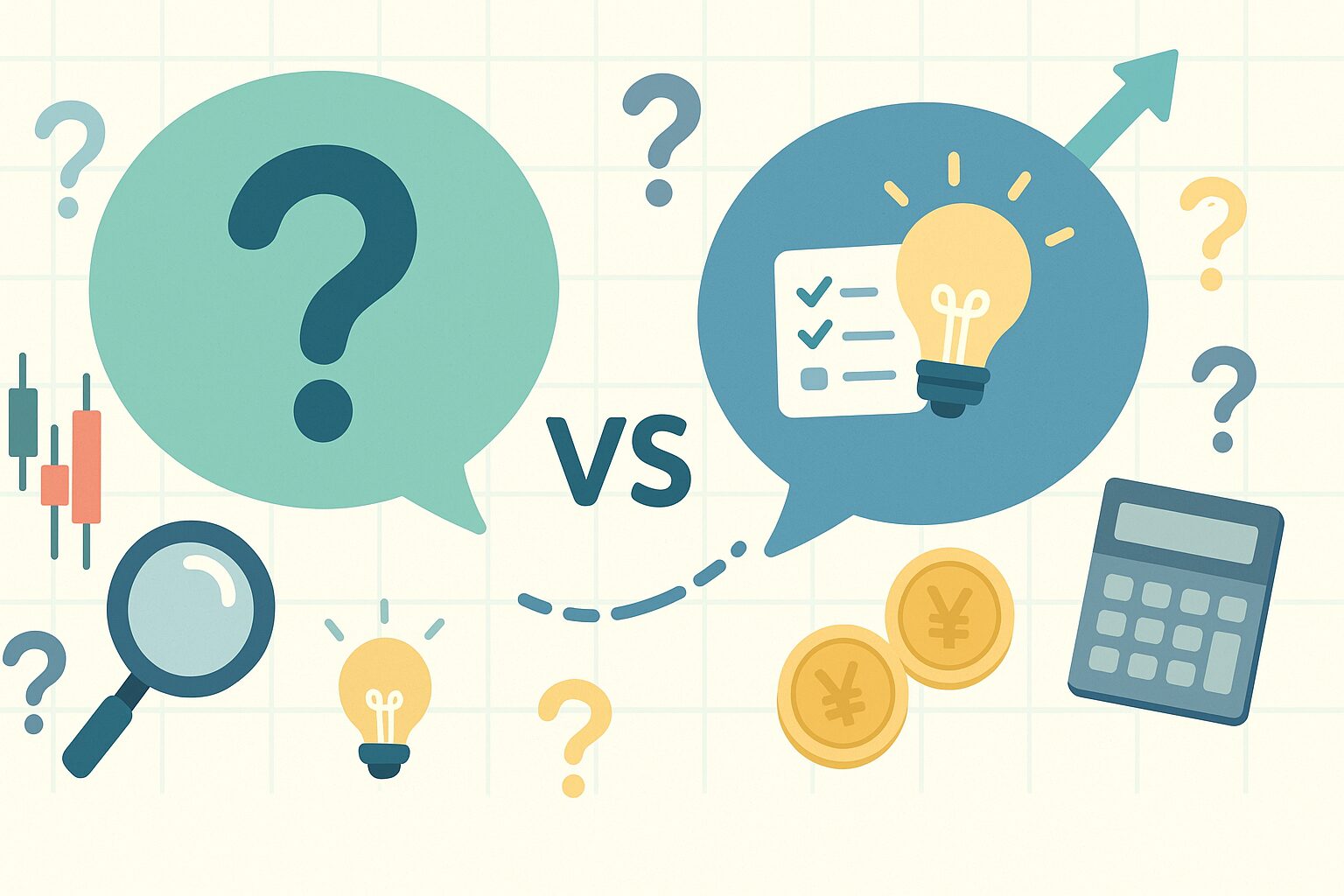
毎年同じ日に必ず起きるのか?
日付や間隔はETFごとに異なるため、最新版で要確認。
権利落ち日に必ず大きく下がるのか?
売却タイミングは分散される場合があり一律ではない。
落ちたら必ず戻るのか?
必ずとはいえない。
他材料の影響も加わる。
まとめ

チェックリスト(保存用)
- 捻出売りは分配原資確保のための売りで、主に需給に関わるイベント
- 権利月・支払月はETFごとに異なる(公式で要確認)
- 受渡(T+2)を前提に、連休・月末のズレをカレンダーで把握する
- 戦略は「スケジュール把握→持ち高調整→分割/逆指値→再投資」


\口座開設へ進む/
👉次に読む
