

選挙期間中の株価動向には「選挙は買い」というアノマリーが存在します。
これは、選挙が新たな政策や経済対策への期待を市場に与えるためです。

特に1990年以降、衆議院解散から投票日までの日経平均株価が上昇したケースが多く確認されています。
ただし、2024年には政局不安や外部要因により、この傾向が崩れる場面も見られました。
日本市場では政治イベントと株価が密接に連動しており、投資家心理や政策期待が大きな影響を及ぼします。

ポイント
- 選挙期間中は新たな政策期待から株価が上昇する傾向がある。
- 1990年以降、衆院選解散から投票日まで日経平均株価が上昇したケースが多い。
- 「選挙は買い」のアノマリーは外国人投資家の買い越しなどが要因となる。
- 政局不安や外部要因(米国大統領選など)でアノマリーが崩れるリスクもある。
- 日本市場では政治イベントと経済政策が株価に密接に影響を与える特徴がある。
選挙は買いのアノマリーと株価の関係

この章では選挙は買いのアノマリーと株価の関係について解説します。
選挙期間中に株価が上昇する理由とは?
選挙期間中に株価が上昇する背景には、いくつかの要因があります。
まず、選挙は新たな政策や経済対策への期待を市場に与えるイベントです。
特に与党が安定した支持を得ている場合、政権継続による政策の一貫性が期待され、投資家心理が改善します。
また、過去のデータでも「選挙は買い」という経験則が確認されているのです。
1990年以降、日本では衆議院解散から投票日までの期間に日経平均株価が上昇したケースが多く見られます。
例えば、2024年の衆院選でも解散後から投票日前までに外国人投資家の買い越しが進み、株価が一時的に上昇しました。
さらに、選挙直前は市場参加者がリスクを取る傾向もあります。
「噂で買って事実で売る」という相場格言通り、事前の期待感で株式市場が活発化することも理由の一つです。
「選挙は買い」のアノマリーが注目される背景
「選挙は買い」というアノマリー(経験則)が注目される背景には、過去の実績と市場心理の影響があります。
1990年以降、日本では衆院選11回中、解散から投票日前までの日経平均株価がすべて上昇したというデータがあります。
このような一貫した傾向は、多くの投資家にとって信頼できる指標となっているのです。
特に外国人投資家の動きも重要です。
過去5回の衆院選では、外国人投資家が平均約3兆円規模で日本株を買い越しており、これが株価上昇を支える要因となっています。
ただし、このアノマリーには注意も必要です。
2024年には「選挙は買い」の傾向が崩れる場面も見られました。
これは政局不安や外部要因(米国大統領選など)が影響したためであり、一概に過去の傾向だけで判断するリスクもあります。
日本市場特有の政治と経済の関係性
日本市場では、政治と経済が密接に連動しています。
例えば、与党が安定多数を確保する場合、市場では政策継続への期待感から株価が上昇しやすくなる傾向があるのです。
また、日本独自の事情として、衆議院解散総選挙は「政局安定」への期待感を伴うため、市場全体にポジティブな影響を与える傾向があります。
さらに、日本では政府主導の経済政策(例:金融緩和や財政出動)が企業業績に直接影響を及ぼすため、政治イベント時には株式市場への注目度が高まります。
海外市場(特に米国)との違い
日本と海外市場(特に米国)では、政治イベントと株価動向の関係性に違いがあります。
米国では、大統領選挙後に株価が堅調になる傾向があります。
これは、新政権による政策変更への期待感や、市場参加者によるリスク許容度の変化によるものです。
一方、日本では解散総選挙前後に株価変動が集中しやすく、「事前期待」が大きな影響を与えます。
また、日本市場は米国市場との連動性も高いため、米国大統領選など外部要因にも左右されます。
例えば、2024年には米国大統領選結果への警戒感から日本株も一時的に軟調となりました。
このような外的要因を考慮することも重要です。

衆院選が株価に与える影響を過去データで検証

この章では衆院選が株価に与える影響について解説します。
過去の衆院選と日経平均株価の動向
1990年以降、衆議院解散から投票日までの期間に日経平均株価が上昇したケースは11回中11回に達します。
例えば、2021年の衆院選では解散後1ヵ月で株価が+7.5%上昇しました。
この傾向は「選挙は買い」と呼ばれるアノマリー(経験則)として定着しています。
しかし2024年10月の総選挙では、与党の過半数割れ懸念から投票直前まで3万7913円まで下落する異例の動きも発生。
過去の法則が常に成立するわけではない点に注意が必要です。
解散から投票日までの株価推移
解散直後から投票日までは平均+4.2%の上昇率を示します(1990-2024年データ)。
特に景気敏感株(電機・鉄鋼)が買われやすく、2012年衆院選ではトヨタ自動車が+18%上昇しました。
ただし2024年は米国大統領選との重複で上昇幅が+1.8%に抑制されるなど、外部要因の影響も顕在化しています。
投票日後の株価変動パターン
投票後1ヵ月の株価は上昇4回/下落7回と不安定です。
2012年自民党圧勝時は+29.7%上昇した一方、2009年民主党政権誕生時は4.2%下落するなど、結果次第で大きく分かれます。
2024年総選挙後は円安進行(1ドル=153円台)を背景に+800円の大幅反発も記録しました。
政権交代が市場に与えるインパクト
政権交代が発生した3事例(1993年/2009年/2012年)の平均株価変動率は+6.1%です。
2012年自民党復権時は「アベノミクス期待」で半年間+29.7%上昇する一方、2009年民主党政権時はマニフェスト不安から4.2%下落。
2024年は野党過半数未達で政権交代回避となり、選挙後初日に+2.1%反発する展開に。
市場は「政局不安解消」を評価しました。
データが示す通り、政権の安定性と政策実行力が株価変動の鍵を握っています。
投資判断には選挙後の政策具体化スピードにも注目が必要です。

選挙関連銘柄の特徴と注目ポイント

選挙関連銘柄は、国政選挙や地方選挙の実施に伴い、業績が向上する可能性がある企業群を指します。
選挙期間中は投票用紙や広告物の制作、世論調査などの需要が急増するため、これらに関連する業種や企業が注目されます。
また、短期的なテーマ株として物色されることが多く、株価の動きも比較的活発です。
選挙関連銘柄とは?その特徴を解説
選挙関連銘柄は、選挙運営に必要なサービスや製品を提供する企業で構成されています。
具体的には、投票用紙や封筒を作る印刷業、選挙カー用機材を提供する音響メーカー、世論調査を行うマーケティング企業などがあります。
これらの企業は、選挙期間中に収益が集中する傾向があり、短期的な業績向上が期待されているのです。
印刷業や広告業など短期的に注目される業種
印刷業は選挙関連銘柄の中核を担う業種です。
投票用紙や通知封筒の制作だけでなく、ポスターやパンフレットなども手掛けるため、大量受注が期待されます。
広告業も重要な役割を果たし、候補者の認知度向上を目的とした広告キャンペーンや街頭演説の広報活動などで収益を上げることがあります。
景気敏感株が選ばれる理由
景気敏感株とは、経済状況に応じて業績が変動しやすい企業群です。
選挙期間中は市場全体の期待感が高まり、このような銘柄にも資金が流入しやすくなります。
例えば、鉄鋼や電機メーカーなどは景気回復期待とともに買われる傾向があるのです。
また、防衛関連株や公共事業関連株も政策テーマに応じて注目されることがあります。

投票日後の株価リスクと投資戦略

この章では投票日後の株価リスクと投資戦略について解説します。
投票日後に株価が下落するリスク要因
政局不安定化による市場不透明感
選挙結果が政治的な不安定を引き起こす場合、市場は敏感に反応します。
特に、与党が過半数を失うようなケースでは、政策の実行力が低下し、経済改革が停滞する可能性があります。
例えば、2024年の日本総選挙では与党連立が議席を減らした結果、政策の方向性が不透明となり、株式市場に一時的な売り圧力が生じました。
このような状況では、投資家は短期的なリスク回避行動を取る傾向があります。
海外市場との連動による影響
日本市場は海外市場と密接に連動しており、特に米国経済やドル円相場の変動が大きな影響を及ぼします。
例えば、米国で金利が引き下げられる一方で日本では金利上昇が進むと、円高傾向が強まり輸出企業の利益が圧迫される可能性があります。
また、中国経済の減速や地政学的リスクも日本市場に波及するため、多角的な視点でリスクを把握する必要があるのです。
▼金利について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-
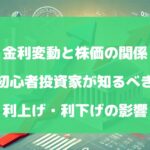
-
金利変動と株価の関係:初心者投資家が知るべき利上げ・利下げの影響
続きを見る
投資家が取るべきリスク管理方法
分散投資でリスクを軽減する方法
分散投資は、株式市場のボラティリティを抑える有効な手段です。
具体的には、異なる業種や地域への投資を組み合わせることで、一部の市場が低迷しても他の市場で損失を補うことができます。
例えば、日本株だけでなく米国株や新興国市場への分散投資を検討することで、地域的なリスクを軽減できるのです。
また、不動産投資信託(REIT)や債券など異なるアセットクラスも活用すると安定性が向上します。
短期売買と長期保有、どちらが有効か?
短期売買は、市場の変動を利用して利益を狙う戦略ですが、高い分析力と迅速な意思決定が求められます。
一方で長期保有は、一時的な価格変動に左右されず、企業価値の成長を享受する戦略です。
例えば、市場全体が不安定な状況では長期保有戦略が有効とされます。
特に、日本企業のガバナンス改善や配当増加の恩恵を受けるには長期的視点が重要です。
ただし、自身の投資スタイルやリスク許容度に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

選挙期間中に注目すべきセクターと銘柄

この章では選挙期間中に注目すべきセクターと銘柄について解説します。
「選挙は買い」で注目されるセクターとは?
選挙期間中の株式市場では、特定のセクターや銘柄が注目される傾向があります。
これは、選挙による政策期待や経済刺激策が特定の業界にポジティブな影響を与えるためです。
特に「景気敏感セクター」と「公共事業関連セクター」が挙げられます。
景気敏感セクターは、経済成長やインフラ投資の強化が追い風となりやすい分野です。
一方で、防衛関連やエネルギー関連も、選挙公約や政策議論の焦点となることで注目されます。
例えば、防衛費増額が議論される場合、三菱重工業などの防衛関連株が買われる可能性があります。
景気敏感セクター(鉄鋼、電機など)の特徴
景気敏感セクターは、経済全体の動向に強く影響される業界です。
鉄鋼や電機などは、政府の大型公共事業やインフラ整備計画が発表されると大きな恩恵を受けます。
例えば、鉄鋼業界では新日本製鐵やJFEホールディングスが代表的な銘柄です。
これらは建設需要の増加時に株価が上昇する傾向があります。
また、電機業界ではパナソニックや日立製作所が注目。
特に、省エネ技術や再生可能エネルギー関連製品を手掛ける企業は、中長期的にも期待されています。
防衛関連や公共事業関連の可能性も検討
防衛関連銘柄は、選挙公約で防衛費増額が掲げられると注目を集めます。
具体例として三菱重工業やIHIなどがあります。
これらは防衛装備品を製造しており、政策変更の影響を受けやすいです。
公共事業関連では、大成建設や清水建設などのゼネコン企業が挙げられます。
政府がインフラ投資を拡大する方針を示した場合、これらの企業への需要が高まります。
選挙期間中のニュースが与える影響を見極める
選挙期間中はニュースによって市場心理が大きく動きます。
例えば、「与党勝利予測」のニュースが流れると、市場全体で楽観ムードが広がり株価上昇につながります。
一方で、「政権交代」など不透明感を伴うニュースは株価下落要因となり得るのです。
このため、市場動向をリアルタイムで確認しながら柔軟に対応することが重要です。
具体例として、防衛費増額報道があれば防衛関連株に資金流入する可能性があります。
また、公共事業拡大計画発表時にはゼネコン株への注目度が高まります。
初心者でもニュースアプリなどで情報収集し、市場の反応を観察する習慣をつけましょう。

まとめ

ポイント
- 選挙期間中は新たな政策期待から株価が上昇する傾向がある。
- 1990年以降、衆院選解散から投票日まで日経平均株価が上昇したケースが多い。
- 「選挙は買い」のアノマリーは外国人投資家の買い越しなどが要因となる。
- 政局不安や外部要因(米国大統領選など)でアノマリーが崩れるリスクもある。
- 日本市場では政治イベントと経済政策が株価に密接に影響を与える特徴がある。
今回は「選挙は買い」について説明してきました。
1990年以降、衆院選解散から投票日まで日経平均株価が上昇したケースが多く確認されています。
ただし、2024年には政局不安や外部要因でこの傾向が崩れる場面もありました。
投資家は政策期待や外国人投資家の動向を注視しつつ、外的リスクも考慮する必要があります。
分散投資や市場ニュースの活用を通じて柔軟な投資戦略を立てることが重要です。


-

-
【参院選】参議院選挙で株価はどう動く?投資家必見の影響と対策ガイド
続きを見る
参考:
- 「総選挙、解散日から投票日まで日経平均株価は上昇する」を1990年以降のデータで4ケースを検証する。―景気の予告信号灯としての身近なデータ(2024年10月1日)―|宅森昭吉(景気探検家・エコノミスト)
- 衆議院選挙と株価の動きを検証 解散から選挙までの日本株は16回連続上昇 | 三井住友DSアセットマネジメント
- 【日本株】与党大敗、相場はどうなる? | 市場のテーマを再訪する。アナリストが読み解くテーマの本質 | マネクリ マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア
- 解散総選挙により○○の日まで株価は上昇する!?過去30年の衆議院選挙前後の株価データを分析したイベント投資の達人が、儲けるポイントを徹底解析!|ザイスポ!|ザイ・オンライン
