

ドルコスト平均法は、投資初心者から経験者まで幅広く利用されている資産運用の手法です。
この方法は、金融商品の価格が変動する中で、一定の金額を定期的に投資し続けることで、購入タイミングを分散させる仕組みとなります。
価格が高いときは少なく、安いときは多く購入できるため、平均購入単価が平準化され、高値掴みのリスクを軽減できます。
一括投資と異なり、相場の動向やタイミングを気にする必要がなく、少額からでも始められる点が魅力です。
ただし、相場が長期的に右肩上がりの場合は一括投資の方がリターンが大きくなることもあり、また手数料や税金にも注意が必要です。

長期的な資産形成を目指す方や、忙しくて相場を常にチェックできない方にとって、ドルコスト平均法は精神的な負担を減らし、安定した投資を続けやすい選択肢となります。
一方で、短期間で大きな利益を狙う場合や、相場の動きを読むのが得意な方には向かないこともあります。
ご自身の投資目的やライフスタイルに合わせて、最適な運用方法を選ぶことが大切です。

ポイント
- ドルコスト平均法は、一定額を定期的に投資し、価格変動リスクを分散する方法である
- 価格が安い時に多く、高い時に少なく買うことで、平均購入単価を抑えやすくなる
- 投資タイミングを気にせず、少額から長期的に資産形成ができる仕組みである
- 上昇相場では一括投資の方が利益が大きくなる場合もあるため、万能ではない
- 手数料や税金にも注意し、非課税制度や低コスト商品を活用することが重要である
\口座開設は無料/
ドルコスト平均法とは?わかりやすく仕組みを解説

この章ではドルコスト平均法の仕組みについて解説します。
ドルコスト平均法の基本的な考え方
ドルコスト平均法(DCA)は、毎月や毎週など決まったタイミングで、一定の金額を同じ金融商品に投資し続ける方法です。
たとえば、毎月1万円ずつ投資信託を買う場合、価格が高い月は少ない口数しか買えませんが、価格が安い月は多くの口数を買うことができます。
この積み重ねによって、購入単価が平均化され、高値掴みのリスクを減らせるのが特徴です。
短期間で大きな利益を狙うのではなく、長期的にコツコツと資産を増やしたい人に向いています。
株価が下がった月は多く、上がった月は少なく購入することで、最終的な平均購入単価が下がることが多いです。
この仕組みは、相場の上下に一喜一憂せず、安定した資産形成を目指す初心者にも分かりやすい投資法といえるでしょう。
一括投資との違い
一括投資は、まとまった資金を一度に投資する方法です。
一方、ドルコスト平均法は、資金を分割して定期的に投資します。
一括投資の場合、投資した直後に相場が下がると大きな損失を被ることがあります。
ドルコスト平均法なら、価格が下がったときにも追加で買うため、平均購入単価を抑えやすいです。
たとえば、10万円を一括で投資すると、その時の価格で全てを購入します。
同じ10万円を毎月1万円ずつ10回に分けて投資すると、価格が安いときに多く、高いときに少なく買うため、平均購入単価が下がることが期待できます。
ただし、相場がずっと右肩上がりの場合は、一括投資の方がリターンが大きくなることもあります。
精神的な負担も異なります。
一括投資はタイミングを見極める必要があり、初心者にはハードルが高いです。
ドルコスト平均法は、投資タイミングを気にせず自動的に積立できるため、投資経験が少ない方にも向いています。
どんな人におすすめ?
ドルコスト平均法は、投資初心者や忙しい社会人、主婦など、投資に時間や知識をあまり割けない人におすすめです。
また、まとまった資金がなく、少額から資産形成を始めたい方にも適しています。
相場のタイミングを読む自信がない場合や、価格変動に左右されずにコツコツ投資を続けたい人にもおすすめです。
たとえば、毎月の給料から一定額を自動で積立する仕組みを作れば、無理なく投資を続けられます。
長期的な資産形成を目指す人や、将来のために安定的にお金を増やしたい人にもメリットがあるのです。
一方で、短期間で大きな利益を狙いたい人や、相場の動きを読むのが得意な人には、一括投資の方が合う場合もあります。
自分のライフスタイルや投資目的に合わせて選ぶことが大切です。

ドルコスト平均法のメリット・デメリットを初心者向けに説明

この章ではドルコスト平均法のメリット・デメリットについて解説します。
メリット
リスク分散ができる理由
ドルコスト平均法の最大のメリットは、価格変動リスクを抑えられる点です。
この手法では、毎月や毎週など決まったタイミングで一定額を投資します。
価格が高いときは少なく、安いときは多く買う仕組みなので、結果的に平均購入単価が平準化されます。
例えば、投資信託の基準価額が10,000円のときに1万円分購入すると1口買えますが、8,000円に下がったときは1.25口買える計算です。
このように、相場が下がっても自動的に多く買うことで、長期的に見ると高値づかみのリスクを軽減できます。
複数のタイミングに分けて買うため、一度にまとまった資金を投じるよりも精神的な負担も小さくなります。
時間を味方につけてコツコツ資産を増やしたい人に向いている方法です。
相場のタイミングを気にしなくていい
投資初心者が悩みがちなのが「いつ買えばいいのか」というタイミングの問題です。
ドルコスト平均法なら、相場を読む必要がありません。
あらかじめ決めた日付に自動で買い付けるだけなので、値動きを毎日チェックする手間が省けます。
例えば、証券会社の自動積立サービスを利用すれば、設定した金額が毎月自動的に投資に回ります。
これなら忙しい人でも無理なく続けられますし、感情に左右されて焦って売買するリスクも減ります。
投資のプロでもタイミングを完璧に当てるのは難しいため、初心者にとっては大きな安心材料です。
少額から始められる
ドルコスト平均法は、まとまった資金がなくても始められるのが特徴です。
例えば、月1,000円や5,000円など、無理のない金額からコツコツ積み立てることができるのです。
最近はつみたてNISAなど少額投資向けの制度も充実していて、学生や新社会人、主婦など幅広い層が利用しています。
一度に大きなお金を準備する必要がないので、資産運用のハードルがぐっと下がります。
「投資はお金持ちだけのもの」と感じていた人も、少額からのスタートで経験を積むことができるのです。
デメリット
上昇相場では一括投資が有利な場合も
ドルコスト平均法は、価格が上下することで平均購入単価を抑える効果があります。
しかし、相場がずっと右肩上がりの場合は、一括で最初にまとめて投資したほうが利益が大きくなることもあるのです。
例えば、株価が毎月上がり続けるケースでは、後から買う分がすべて高値買いになってしまうため、最初に全額投じていた方がリターンは大きくなります。
このため、ドルコスト平均法は「どんな相場でも万能」というわけではありません。
相場の状況や自分の投資スタイルに合わせて使い分けることが大切です。
短期的な利益は期待しにくい
ドルコスト平均法は、長期的な資産形成を目的とした手法です。
短期間で大きな利益を狙いたい場合には向いていません。
積立を始めてすぐに利益が出ることは少なく、むしろ一時的な含み損を抱えることもあります。
「すぐに結果を出したい」「短期間で資産を増やしたい」という人には、他の投資方法を検討した方が良いでしょう。
ゆっくりでも着実に資産を増やしたい人に適しています。
手数料や税金に注意
積立投資は毎回の買付ごとに手数料が発生する場合があります。
一括投資よりも取引回数が多くなるため、手数料の総額がかさむことも。
また、運用益に対しては税金がかかるため、NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用するのがおすすめです。
商品選びの際は、手数料が安い投資信託やノーロード商品を選ぶとコストを抑えやすくなります。
「手数料や税金を考えずに始めてしまい、思ったより利益が残らなかった」という失敗例もあるので、事前にしっかり確認しましょう。

ドルコスト平均法のやり方と始め方【具体的な手順】

この章ではドルコスト平均法のやり方と始め方について解説します。
証券口座の開設方法
投資を始めるには、まず証券口座の開設が必要です。
ネット証券を利用すれば、スマホやパソコンから24時間いつでも申し込みができます。
SBI証券や楽天証券など、多くのネット証券が初心者向けに分かりやすいガイドを用意しています。
口座開設の流れは次の通りです。
- 最初に証券会社の公式サイトで「口座開設」ボタンをクリック。
- メールアドレスや基本情報を入力し、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をアップロード。
- ネットで本人確認が完了すれば、最短で翌営業日から取引が可能。
郵送での手続きも選べますが、1週間ほどかかる場合があります。
NISA口座も同時に申し込む場合、税務署の審査が入るため、開設まで10日ほどかかることもあります。
口座開設が完了したら、証券会社からログインIDやパスワードが届きます。
ログイン後は、初期設定や銀行口座の登録などを済ませておきましょう。
-
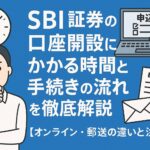
-
SBI証券の口座開設にかかる時間と手続きの流れを徹底解説【オンライン・郵送の違いと注意点】
続きを見る
積立投資の設定手順
証券口座が開設できたら、いよいよ積立投資の設定です。
まずは投資信託やETFなど、積み立てたい商品を選びます。
楽天証券やSBI証券の場合、ログイン後に「投資信託」メニューから商品を検索し、積立設定画面に進みます。
積立設定では、毎月の積立金額や積立頻度、引き落とし方法(銀行口座やクレジットカードなど)を選択。
クレジットカード積立を利用すれば、ポイントが貯まるなどのメリットもあります。
積立頻度は「毎月」「毎日」などから選べますが、証券会社によって対応状況が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
設定内容を確認し、目論見書に同意したら、取引パスワードを入力して設定を完了します。
この設定が終われば、あとは自動で積立が行われるので、投資初心者でも手間なく続けられます。
積立金額の決め方
積立金額は「無理のない範囲」で設定することが大切です。
一般的には、手取り収入の30%以内に抑えるのが目安とされています。
生活費や急な出費に影響しない範囲で、余裕資金から積み立てましょう。
また、積立額は「目標金額」と「運用年数」から逆算して決めるのも有効です。
たとえば「20年後に1000万円貯めたい」といった目標があれば、毎月いくら積み立てる必要があるか計算できます。
金融庁などが提供するシミュレーションツールを活用すれば、利回りも考慮した積立額の目安が分かります。
証券会社によっては、月100円や1000円など少額から積立を始められるため、初心者でも気軽にスタートできます。
積立頻度の選び方
積立頻度は「毎月」「毎週」「毎日」などから選べます。
どの頻度を選んでも、長期的なリターンに大きな差は出にくいです。
毎日積立は購入回数が多く、時間の分散効果がより高まるという特徴があります。
一方で、毎月積立は管理がしやすく、多くの人が選んでいる方法です。
証券会社によっては毎日積立に対応していない場合もあるので、希望する場合は事前に確認しましょう。
基準価額の変動が気になる人は、毎日積立を選ぶことで値動きを気にせず運用できます。
自分のライフスタイルや管理のしやすさに合わせて選ぶのがおすすめです。

\口座開設は無料/
ドルコスト平均法に向いている金融商品と選び方のポイント

この章ではドルコスト平均法に向いている金融商品と選び方のポイントについて解説します。
おすすめの金融商品
投資信託
投資信託は、投資家から集めたお金をプロの運用会社が株式や債券などに分散して投資・運用する金融商品です。
少額から始められ、分散投資が簡単にできるため、投資初心者に非常に人気があります。
たとえば、1万円からでも世界中の株式や債券に投資できるのが特徴です。
個人で複数の株や債券を買うのは難しいですが、投資信託なら自動的に分散投資が実現します。
運用は専門家が行うため、難しい知識がなくても始めやすいです。
毎月一定額を積み立てることで、ドルコスト平均法の効果を最大限に活用できます。
インデックスファンド
インデックスファンドは、日経平均やS&P500などの株価指数に連動することを目指す投資信託です。
手数料が低く、運用方針が分かりやすいので、初心者にもおすすめ。
たとえば「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」などが人気です。
100円から積立できる商品も多く、毎月自動で購入設定ができるため、忙しい方でも無理なく続けられます。
長期でコツコツ積み立てることで、世界や米国の経済成長の恩恵を受けやすくなります。
つみたてNISA対象商品
つみたてNISAは、年間120万円までの投資で得た運用益が非課税になる制度です。
対象となるのは、金融庁が厳しく選定した長期・積立・分散投資に適した投資信託やETFのみです。
2025年4月時点で、インデックス型投資信託が254本、アクティブ型が57本、ETFが8本選ばれています。
これらの商品は、購入時手数料が無料(ノーロード)で、信託報酬も低く設定されています。
つみたてNISA対応商品を選ぶことで、税制メリットを受けながら、安心して長期積立投資ができます。
商品選びのチェックポイント
手数料の安さ
投資信託を選ぶ際は、手数料の水準を必ず確認しましょう。
特に注目すべきは「信託報酬」と呼ばれる運用管理費用です。
信託報酬が0.1%違うだけでも、長期運用では最終的なリターンに大きな差が生まれます。
つみたてNISA対象商品は、購入時手数料がゼロ(ノーロード)で、信託報酬も低水準です。
たとえば「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は信託報酬0.05775%と、世界でもトップクラスの低コストです。
ネット証券を利用すれば、ほとんどの投資信託は売買手数料無料で購入できます。
運用実績とリスク
商品を選ぶ際は、過去の運用実績やリスク水準もチェックが必要です。
たとえば、全世界株式インデックスファンドの場合、直近1年のリターンが+25.21%、5年で+18.36%(年率)という実績もあります。
一方で、リスク(価格の変動幅)も年率15%前後と比較的高めです。
リターンが高い商品はリスクも大きくなる傾向があります。
自分のリスク許容度や投資目的に合わせて、運用実績とリスクのバランスを見て選びましょう。
比較サイトや証券会社のランキングも参考になります。
投資信託やインデックスファンド、つみたてNISA対応商品は、ドルコスト平均法での積立投資に最適です。
手数料や運用実績をしっかり比較し、自分の目的に合った商品を選ぶことが、長期的な資産形成の第一歩となります。

ドルコスト平均法で失敗しないための注意点と成功のコツ

この章ではドルコスト平均法で失敗しないための注意点と成功のコツについて解説します。
長期投資を継続するコツ
ドルコスト平均法は、長期間コツコツと積み立てることで効果を発揮します。
途中でやめてしまうと、価格変動のリスクを平均化するメリットが十分に得られません。
そのため、最初に「どのくらいの期間続けるか」目標を決めておくことが大切です。
自動積立サービスを活用すると、毎月自動で投資ができるので、相場を気にしすぎずに続けやすくなります。
また、生活費や急な出費に備えて、無理のない金額で設定することもポイントです。
たとえば、「毎月5,000円」など、家計に負担がかからない範囲で始めると長続きしやすくなります。
定期的に運用状況を確認し、必要に応じて積立額を見直すことも忘れないでください。
長期投資の成功には「続ける仕組み」を作ることが重要です。
相場下落時の心構え
相場が下がると不安になり、積立をやめたくなることがあります。
しかし、ドルコスト平均法では、価格が下がったときこそ多くの口数を買うチャンスです。
実際、下落時に積立を継続した人のほうが、相場が回復したときに大きなリターンを得やすい傾向があります。
暴落はプロでも予測が難しいため、焦って売却や積立停止をしないことが大切です。
「今は安く買えている」と前向きに捉え、計画通り積立を続けましょう。
ただし、投資先が長期的に成長する見込みがあるかも定期的に確認してください。
不安なときは、分散投資を取り入れることでリスクをさらに抑えることもできます。
やめどき・出口戦略の考え方
ドルコスト平均法は「いつやめるか」も重要なポイントです。
目標金額や投資期間をあらかじめ決めておくと、迷わず出口を迎えられます。
たとえば「10年後に教育資金として使う」「老後資金が〇万円貯まったら一部売却する」など、具体的なゴールを設定しましょう。
積立をやめるタイミングでは、その時点の相場状況によって利益や損失が変わります。
一度に全額売却するのではなく、必要な分だけ少しずつ取り崩す方法も有効です。
また、積立をやめた後も、資産を安定運用に切り替えるなど柔軟に対応すると安心です。
出口戦略を明確にしておけば、相場の変動に惑わされずに冷静な判断ができます。
よくある失敗例と対策
よくある失敗例として、相場が下がったときに積立を中止してしまうケースがあります。
この場合、安い価格で多く買うチャンスを逃してしまい、回復時のリターンも減ってしまいます。
また、短期間で結果を求めてしまい、すぐにやめてしまうのも失敗の原因です。
ドルコスト平均法は短期では効果が出にくく、長期でこそリスク分散のメリットが活きます。
さらに、手数料の高い商品を選んでしまうと、利益が圧迫されることもあるので注意が必要です。
ノーロード(購入手数料無料)の投資信託や、つみたてNISAを活用することで、コストを抑えやすくなります。
対策としては、「長期継続」「無理のない金額設定」「低コスト商品選び」を意識しましょう。
また、投資先が長期的に成長する見込みがあるか、定期的に見直すことも大切です。

まとめ

ポイント
- ドルコスト平均法は、一定額を定期的に投資し、価格変動リスクを分散する方法である
- 価格が安い時に多く、高い時に少なく買うことで、平均購入単価を抑えやすくなる
- 投資タイミングを気にせず、少額から長期的に資産形成ができる仕組みである
- 上昇相場では一括投資の方が利益が大きくなる場合もあるため、万能ではない
- 手数料や税金にも注意し、非課税制度や低コスト商品を活用することが重要である
今回はドルコスト平均法について説明してきました。
ドルコスト平均法は長期目線の投資家に役立つ手法です。
どうしても短期目線で大きな利益を得ることは難しいですが、長期目線ではリスクも考慮しながら比較的簡単に続けられる投資法です。
メリット・デメリットをしっかりと理解して自分に合った投資法を見つけましょう。


\口座開設は無料/
参考:
