

自己資本比率は、会社の資産をどれだけ自己資本(株主の持分)で賄っているかを示す安全性の指標です。
数値が高いほど、借入に依存しない財務の安定度が高いと解釈できます。
30秒で要点|定義・式・読み方

- 定義:自己資本比率=自己資本÷総資産×100%。
- 自己資本の中身:自己資本=株主資本+その他の包括利益累計額(=親会社株主持分)。連結では新株予約権・非支配株主持分は含めません。
- 読み方:高いほど負債耐性が強く、低いほど金利や景気の逆風の影響を受けやすい。
まずは「売上や利益の前に倒れにくさを確認する」つもりで、この比率を押さえましょう。
ひとことで言うと|「借金に頼らない体力」
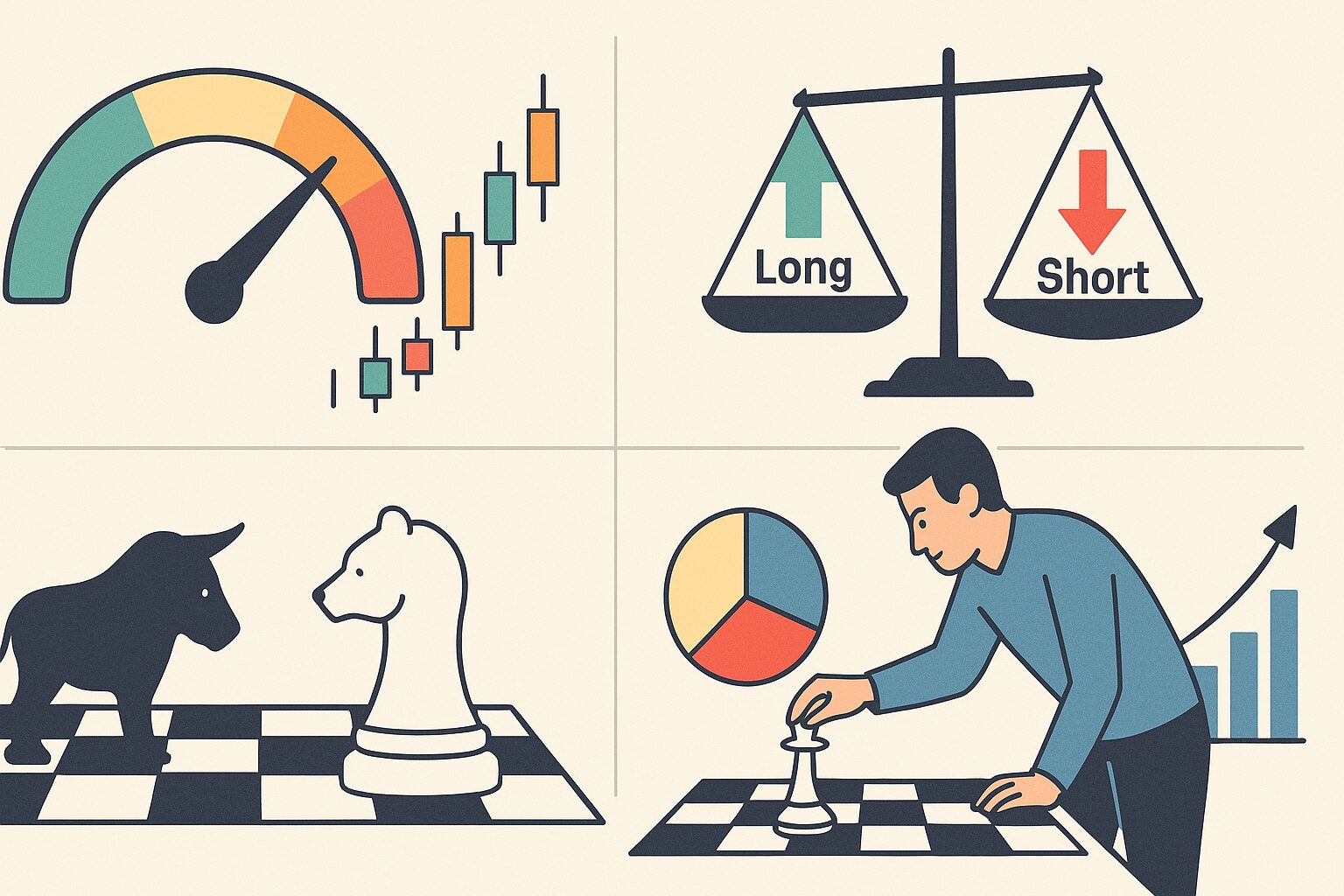
自己資本比率は、資産を「自前の資本」か「他人資本(負債)」のどちらで支えるかの比率です。
比率が高いほど、景気後退・金利上昇・為替の逆風に持ちこたえる力が大きいと考えられます。


計算式と考え方|用語のそろえ方と連結の見方

式
自己資本比率=自己資本÷総資産×100%。
用語のそろえ方
- 自己資本:株主資本+その他の包括利益累計額=親会社株主持分を用いるのが安定。
- 総資産:貸借対照表の合計資産(連結BSを使うのが基本)。
実務メモ(IFRSの注意)
- 表示名称は Equity(自己資本)/ Total assets(総資産)。「経常利益」の区分はIFRSに無いが、本指標の概念は共通。
- IFRS16(リース)のオンバランス化で総資産・総負債が増え、比率が低下しやすい。特に小売・運輸・ホテル等で影響が大きい傾向。
クイックチェック
資料は「連結BS」を見て、Equity attributable to owners of parent(親会社株主持分)とTotal assets(総資産)で算出します。
例題で計算|数値で感覚をつかむ

前提
総資産1,000、親会社株主持分400、非支配株主持分50、負債600。
計算
- 自己資本=親会社株主持分=400。
- 自己資本比率=400÷1,000×100=40%。
解釈
資産の40%を自前資本で賄い、60%は負債で賄っている状態。
景気や金利の逆風が強いほど、40%がどれだけ心強いかを考えます。


目安と使い方|業界差・成長局面・金利環境

業界差
- 資産が軽いサービス・ソフトウェアは比率が高めになりやすい。
- 製造・インフラ等の資本集約型は借入活用が多く、比率は相対的に低め。
成長局面
- 拡大投資期は負債を使ってレバレッジをかけることがあり、一時的に比率が下がる。
- 成熟・安定期は内部留保の蓄積で比率がじわじわ上がることが多い。
金利・為替・景気
- 金利上昇局面は借入コスト増で負債耐性が問われる。自己資本比率が高い企業は揺れにくい。
改善の打ち手|数字を動かす具体策

自己資本を厚くする
- 利益の蓄積(配当と自己株買いのバランス設計)。
- 増資(希薄化の影響を事前に確認)。
総資産を絞る
- 遊休・非中核資産の売却、在庫圧縮、回収サイト短縮。
- IFRS16の影響を踏まえたリース戦略の見直し。
負債構成を見直す
- 長短バランスの最適化、固定/変動金利配分、通貨エクスポージャー管理。
英語表記の早見|海外資料で迷わない

- 親会社株主持分:Equity attributable to owners of parent
- 総資産:Total assets
- 自己資本比率:Equity ratio / Capital adequacy ratio(文脈により表記差)
ケーススタディ|数値パターンで読み分ける

パターンA:比率が急低下
IFRS16の初年度適用や大型設備投資で総資産・負債が増加→一時的に比率低下。
固定費・金利耐性と改善計画を確認。
パターンB:比率が高止まり
潤沢な内部留保で負債を抑制。
成長性とのバランス(ROE・投資計画)を併読。
パターンC:比率は低いが改善傾向
非中核資産売却・在庫圧縮・増益で親会社株主持分が厚くなっている兆候。
継続性を注記で確認。
関連指標と次の一歩|安全性から効率へ

安全性(倒れにくさ)の次は、資本をどれだけ効率よく増やしたかをROEで確認します。
まとめ|今日から使う着眼点

ポイント
- 自己資本比率=自己資本÷総資産×100%。自己資本は「株主資本+その他の包括利益累計額(親会社株主持分)」で算出。
- 同業比較×時系列で判断し、会計基準差(IFRS16等)をまたぐ比較は注記で補う。
- 改善は「自己資本を厚く」「総資産を絞る」「負債構成を整える」の3本柱で考える。


\市場の反応をリアルタイムで追う準備を/
