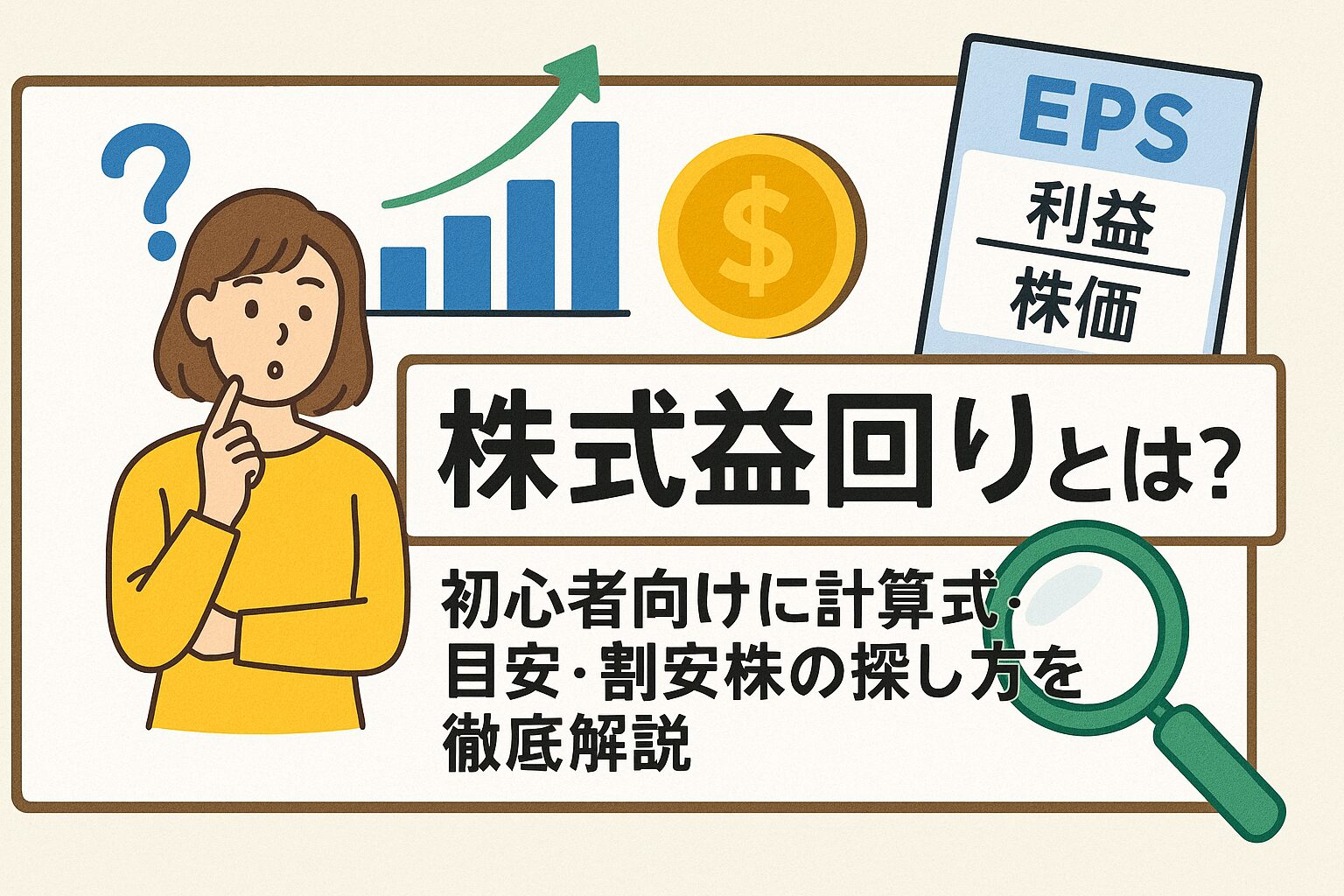株式益回りは、割安・割高を判断するときの入口の指標として便利です。
この記事では、意味と計算式、PER・配当利回りとの違い、使い方のコツと注意点を順に整理します。
株式益回りとは?初心者にもわかりやすく解説

定義(まず式をつかむ)
株式益回りは、株価に対して企業がどれだけ利益を生み出しているかを表す比率です。
計算式は「株式益回り(%)= EPS ÷ 株価 × 100」。
英語ではEarnings Yieldと呼ばれ、PER(株価収益率)の逆数としても扱えます。
👉 EPS を先に押さえると、式の意味がクリアになります。
使い方の入口
数値が高いほど、株価に対して利益水準が厚い=相対的に割安と解釈されやすくなります。
ただし単独で決めつけず、推移や同業平均、金利環境などと合わせて見るのが基本です。

👉 価格倍率の基礎は PER もあわせて。
株式益回りの計算方法とPER・配当利回りとの違い

計算式と具体イメージ
株式益回り=EPS ÷ 株価 × 100(%)。
たとえばEPSが100円、株価2,000円なら益回りは5%。
PERの逆数なので、PER 20倍 ↔ 益回り 5%、PER 10倍 ↔ 益回り 10%という関係です。
PERとの違い
PER=株価÷EPSは「株価が利益の何倍か」を表す指標。
株式益回り=EPS÷株価は「投じた株価に対して利益が何%か」を示します。
視点は反対でも、同業比較や過去推移の確認が大切なのは共通です。
配当利回りとの違い
配当利回り=1株配当÷株価×100は受け取る配当金にフォーカス。
一方、株式益回りは配当で支払われない内部留保の利益も含めて評価できます。
目的に応じて併用し、食い違いが大きいときはその理由(投資負担、景気敏感、一時要因など)を点検しましょう。

👉 受け取り収入の視点は 配当利回り が参考になります。
株式益回りの目安と業種差の見方

一般的な目安(断定しない)
益回りは金利や景気局面で動きます。
一桁後半〜二桁台をひとつの目安とする見方もありますが、固定値ではなく、同業平均・過去推移・金利水準と並べて相対評価するのが基本です。
業種ごとのクセ
- 景気敏感:利益の波が大きく、益回りも振れやすい。
- 安定ディフェンシブ:平常時は中庸、割高でも許容されやすい。
- 高成長:当面の益回りは低くても、将来期待で株価が先行しやすい。

👉 資産面の比較軸は PBR もチェック。
株式益回りを使った割安株の見つけ方
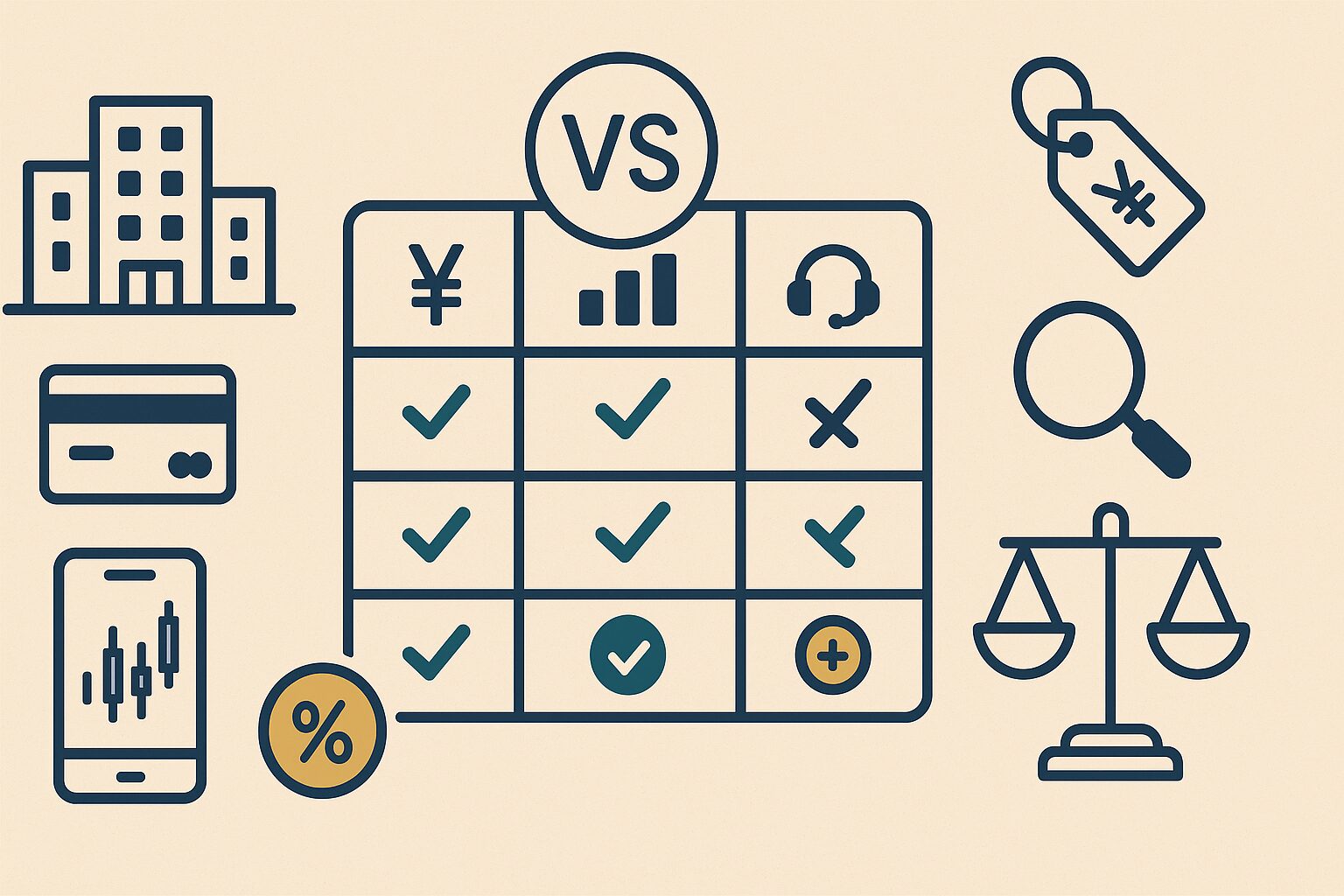
スクリーニングの基本
まずは条件を素直に置きます。
例:益回り(予想)に下限を設定、PERは過度に高くないか、PBRの水準感を確認……など。
候補を絞ったら、業績の安定性や一過性の有無、財務健全性(自己資本比率など)を重ねて精査します。
他指標との組み合わせ
益回りが高いのに配当利回りが低いなら、内部留保を成長投資に振っている可能性も。
逆に両者が近いなら、高い還元方針かもしれません。
ROEや売上成長、キャッシュフローも合わせれば、見落としが減ります。

👉 収益性の軸は ROE と組み合わせると輪郭がはっきりします。
投資判断に活かすポイントと注意点

メリットと留意点
- メリット:式が簡単、他資産(債券利回り等)と並べやすい。
- 留意点:利益はブレやすい。一時要因・会計要因で極端な数値になることがある。
金利・債券利回りとの並べ方
益回りと国債利回りの差(イールドスプレッド)を見る手法は定番です。
差が大きいほど株式の妙味が意識されやすい一方、差が縮む局面では過度な強気は禁物。
金利環境が変われば“普通の水準”も動く点に注意しましょう。
一時要因への対処
特益・減損・在庫評価などでEPSが跳ねる/沈むと、益回りも歪みます。
過去の平常水準・予想値・同業比較を並べ、単年シグナルに振り回されない設計にしておくと安心です。

👉 価格倍率の整理は PSR も参考に。
まとめ

ポイント
- 株式益回りはEPS÷株価×100。PERの逆数で把握しやすい。
- 単独ではなく、同業・推移・金利と並べて相対評価する。
- 配当利回り・ROE・PBRなどと組み合わせ、見落としを減らす。


\市場の反応をリアルタイムで追う準備を/