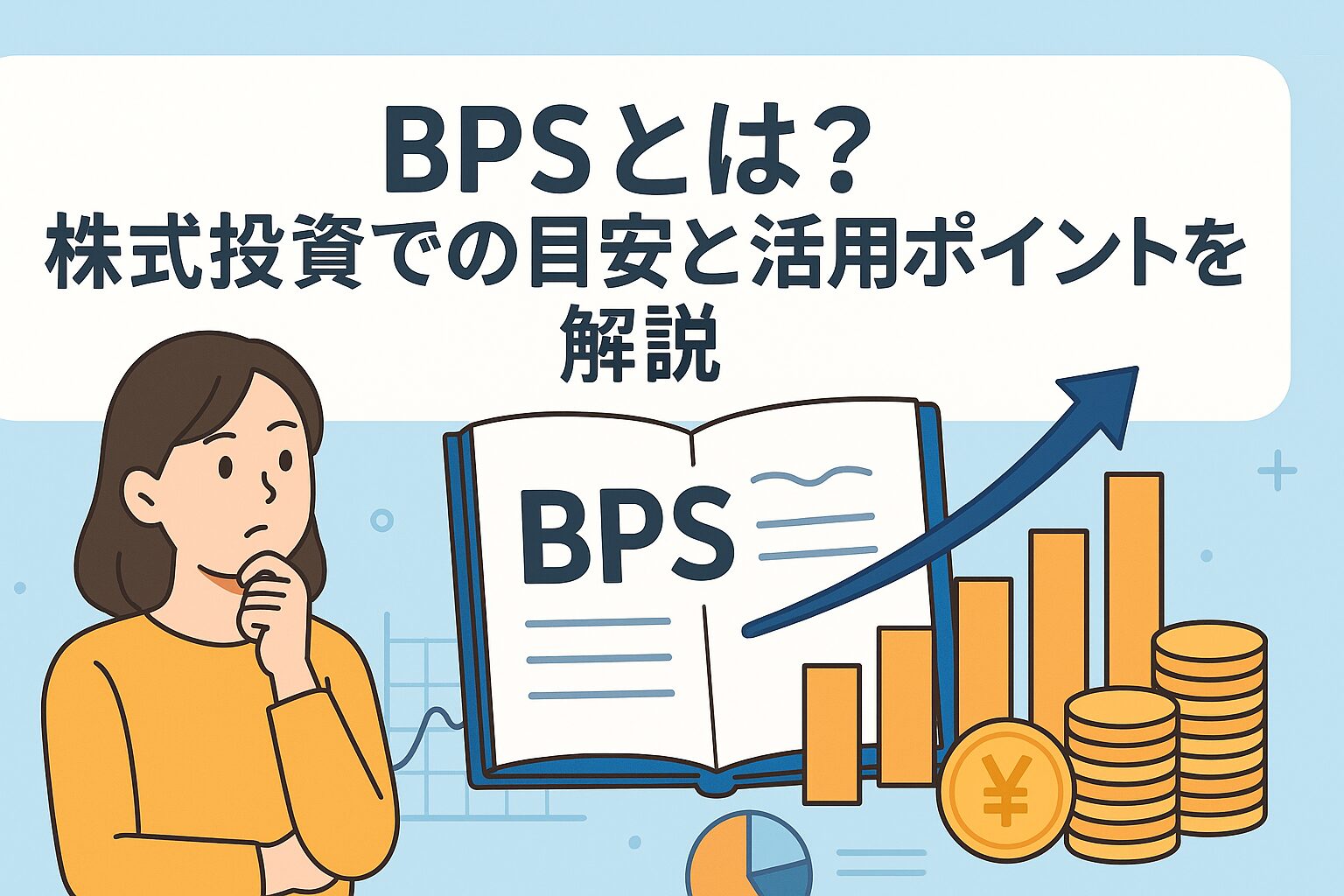BPS(1株当たり純資産)は、企業が持つ純資産を発行済株式数で割った値です。
シンプルですが、財務の安定性や解散価値の粗い目安として活用されます。
ただし解釈は業種・成長段階・資本政策で大きく変化。
この記事は「式は1行」「読み方は3視点」「注意点で失敗回避」を合言葉に、初心者でも腹落ちする流れで整理します。
迷ったら全体の並びから確認すると迷走しません。
BPSとは?数字の“意味”を最短でつかむ

サクッと定義:式は1行
BPS=純資産(親会社株主に帰属する持分)÷発行済株式数。
株式数は実務上自己株式を除くのが一般的です。
1株に均すことで、企業の“土台の厚み”を同業間で比べられます。
この数値で見えること
同業比較で資産の厚み、自社の時系列で内部留保の積み上がりや安定度が見えます。
文脈次第で「解散価値の目安」とも説明されます。
最初に避けたい誤解
BPSが高い=必ず優良ではありません。
資産の質(含み損益・減損リスク・無形資産比率)や資本効率(ROE)も併せて確認しましょう。


目安と業種差:同じBPSでも“重み”が違う

最短ルートは、まず“土俵合わせ”(業種・段階)をしてから数字を比べることです。
資産型 vs. サービス型
工場・設備・在庫など有形資産が厚い業種(機械・建設・素材など)はBPSが相対的に高め。
人的資本中心のサービス・ITはBPSが低めでも、成長性で評価されるケースが多いです。
金融と非金融で読み方が変わる
銀行・保険など金融は会計・規制の影響が強く、水準の単純比較が難しい分野。
製造・インフラは有形資産がBPSに直結しやすく、資産の質(耐用年数・減損可能性)の点検が効きます。
成長段階の違い
創業〜成長期は投資先行でBPSが伸びにくい一方、成熟期は利益の内部留保でBPSが積み上がりやすい。
段階によって“見える景色”は変わります。


実務での使い方:割安探しと“推移”のチェック

割安シグナルの入り口(PBR)
PBR=株価÷BPS。
一般にPBRが1倍未満だと「BPSより株価が低い」状態で、割安探索の出発点になります。
ただし低PBRの背景(業績懸念・資産の質・ガバナンス)を必ず確認しましょう。
時系列で“地力”を把握
3〜5年のBPS推移を並べ、安定上昇か、減少・乱高下かを判別。
増加は利益の内部留保や評価替え、減少は赤字・減損・希薄化などのサインで追加調査の合図です。
同業比較の型
同業内でBPS・PBR・ROEを表にし、資産の厚み(BPS)×市場評価(PBR)×資本効率(ROE)で相対位置を確認。
単一指標で決めず、立体的に揃えて見るのがコツです。


BPS×ほかの指標:役割分担でブレない判断に

役割の切り分け
BPS=資産の厚み、ROE=資本効率、EPS=1株の稼ぐ力、PER=利益への評価倍率。
役割が違うから、組み合わせるほど判断がブレにくくなります。
よくある組み合わせ例
- 低PBR×低ROE:構造課題の可能性→再評価には改善の証拠が必要。
- 低PBR×高ROE:未評価余地。
- 高PBR×高ROE:実力評価か過熱かは成長持続性で判定。
- 高PBR×低ROE:期待先行の可能性。


注意点と誤解:分母トラップと“簿価”の限界

自社株買い・増資・分割の影響
自社株買いは、買付価格が既存BPSより低いとBPS押し上げ、高いと押し下げ要因になり得ます(純資産の減り方と株数減のバランスで決まるため)。
増資は一般にBPS希薄化方向ですが、条件次第で逆もあります。
株式分割は企業価値を変えません。
1株当たり数値は分割比率で機械的に薄まりますが、比較時は分割を跨ぐ期間の注記や調整後値を確認しましょう。
“簿価”ゆえの限界
BPSは帳簿価額ベース。
含み損益、減損リスク、無形資産比率などで実力とのズレが出ます。
有形の堅さを重視する場面では「有形BPS(無形資産控除)」を見る選択も有効です。
赤字・特殊要因の扱い
一時的な評価替えや特別損益でBPSがブレる年があります。
単年ではなく複数年の推移で“地力”を確認し、注記・IRで背景まで辿るのが安全です。


まとめ:BPSは“土台”を見る指標—効率指標と並べて判断

ポイント
- BPS=純資産÷発行済株式数(親会社株主持分、自己株式は除くのが一般的)。
- 業種・成長段階で水準は変わる。まず“土俵合わせ”。
- 活用は「低PBR探索」「3〜5年のBPS推移」「同業比較」が基本。
- 自社株買いは価格次第でBPS↑↓、増資は希薄化方向。分割は価値不変で比較時は調整後値に注意。
- 簿価の限界(含み・減損・無形)を意識し、ROE・EPS・PERと組み合わせる。


\市場の反応をリアルタイムで追う準備を/