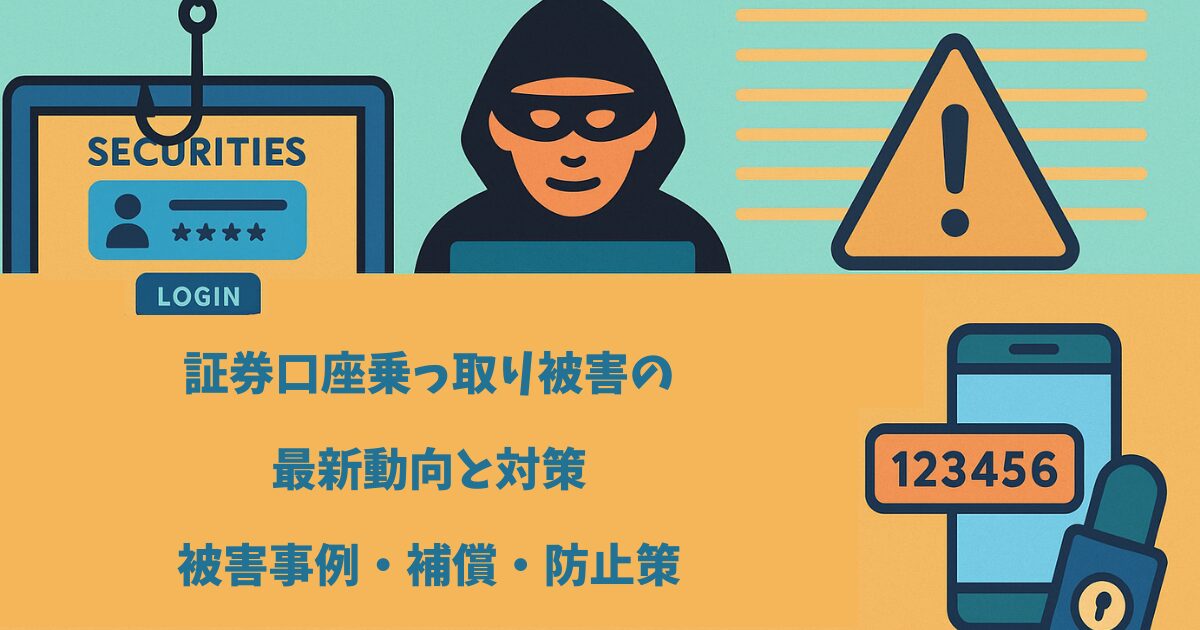証券口座の乗っ取り被害が全国で急増しています。
フィッシング詐欺やマルウェアによってIDやパスワードが盗まれ、知らないうちに自分の株が勝手に売却される事例が後を絶ちません。
被害は楽天証券やSBI証券、野村證券など大手証券会社を中心に広がり、2025年春には不正取引の件数が1400件を超えました。
犯人は巧妙な偽サイトや偽アプリを使い、公式と見分けがつかない手口で利用者を騙します。

被害者の口座では、保有株が売却され、その資金で中国株や低位株が大量に購入されるなど、相場操縦の疑いも指摘されています。
この問題は個人の資産被害にとどまらず、市場全体の信頼性にも影響を与える深刻な社会問題です。
証券会社や金融庁は、多要素認証の導入やセキュリティ対策の強化を急いでいますが、利用者自身も日々の対策が不可欠です。

ポイント
- フィッシング詐欺やマルウェア感染による情報窃取が証券口座乗っ取りの主な手口である
- 偽サイトや偽アプリを利用した巧妙な詐欺が多発している状況である
- 実際に多額の損失事例が発生し、大手証券会社でも被害が確認されている
- セキュリティ対策として強固なパスワード管理や二段階認証の導入が重要である
- 定期的な口座確認や公式情報のチェックを習慣化することが被害防止につながる
証券口座乗っ取りの最新手口と被害事例

この章では証券口座乗っ取りの最新手口と被害事例について解説します。
証券口座乗っ取りの主な手口
フィッシング詐欺による情報窃取
証券口座乗っ取りの最大の入り口は、フィッシング詐欺です。
犯人は証券会社を装ったメールやSMSを送りつけ、「アカウント確認が必要」「不審なログインがあった」などと不安を煽ります。
メールやSMSに記載されたリンク先は、本物そっくりに作られた偽サイトです。
ここでIDやパスワード、場合によっては暗証番号まで入力させ、情報を盗み取ります。
たとえば「SBI証券」や「楽天証券」などの名前で届くメールが典型例です。
公式の連絡と見分けがつきにくいのが特徴で、実際に多くの利用者が偽サイトで情報を入力してしまっています。
証券会社からのメールやSMSに記載されたリンクは絶対にクリックせず、公式サイトやアプリから直接アクセスすることが重要です。
マルウェア・インフォスティーラーの感染
もう一つの主要な手口が、マルウェア「インフォスティーラー」の感染です。
このウイルスは、メールの添付ファイルや不審なウェブサイト経由でパソコンやスマホに侵入します。
感染すると、端末内に保存されたIDやパスワード、入力した内容、さらにはスクリーンショットまで外部に送信されてしまいます。
セキュリティソフトでも検知しにくく、知らないうちに長期間情報を抜き取られるケースも珍しくありません。
実際に、証券口座の乗っ取り被害の多くでインフォスティーラーが使われたと報告されています。
感染経路はメール添付だけでなく、偽のブラウザ拡張機能や偽CAPTCHAを使った手口も確認されています。
少しでも不審なファイルやサイトには絶対にアクセスしないことが大切です。
偽サイトや偽アプリの特徴
フィッシング詐欺やマルウェア感染の多くは、偽サイトや偽アプリが入り口となります。
偽サイトは公式サイトと見分けがつかないほど精巧に作られており、URLが微妙に違う、SSL証明書がない、など細かな違いしかありません。
最近では、Google検索結果や広告枠にも偽サイトが表示されるケースがあり、注意が必要です。
偽アプリの場合、公式ストア以外からインストールすることで感染するリスクが高まります。
「証券会社公式アプリ」と称して、実際には情報を抜き取るだけの偽物も存在します。
公式サイトや公式アプリストアからのみアクセス・インストールすることが、被害防止の第一歩です。
最近の証券口座乗っ取り被害事例
実際の被害者の体験談
2025年春、65歳の女性が証券会社を装うメールを受信しました。
メールのリンクから偽サイトに誘導され、氏名や住所を入力しただけで不正ログインが発生。
その後、保有株がすべて売却され、代わりに知らない複数の株が勝手に購入されていました。
損失額は1日で1800万円にも上り、証券会社からは補償を受けられず、警察に相談したものの救済措置はありませんでした。
また、別のケースでは、1500万円以上の株式が勝手に売買され、200万円以上の損失が発生した例も報告されています。
どちらも、最初は偽メールや偽サイトから情報が抜き取られたのが原因です。
被害が多発している証券会社
被害が確認されているのは、楽天証券、SBI証券、野村證券、SMBC日興証券、マネックス証券、松井証券、大和証券、三菱UFJ eスマート証券など大手8社です。
2025年2月から4月中旬の約2カ月半で、6社合計1454件の不正取引、総額954億円にのぼる被害が発生しました。
特に楽天証券やSBI証券、野村證券で多くの被害が集中しています。
これらの証券会社をかたる偽メールやSMSが大量に出回っており、利用者は細心の注意が必要です。
乗っ取り被害が急増している背景
証券口座乗っ取り被害が急増している背景には、主に3つの要因があります。
まず、フィッシング詐欺やマルウェアの手口が年々巧妙化し、初心者でも騙されやすくなっています。
次に、ネット証券の普及で口座数が増え、狙われる対象が拡大したことが挙げられます。
さらに、攻撃者は盗んだ口座で株価の低い中国株や日本の小型株を大量に買い付け、株価を操作して利益を得る「相場操縦」の手口を使い始めました。
この手法は資金を直接盗むのではなく、被害者に高値掴みの株を押し付けるため、発見が遅れやすいのが特徴です。
2025年に入り、組織的なサイバー犯罪グループが日本を標的とした大規模攻撃を仕掛けていることも、急増の一因となっています。

証券口座乗っ取りを防ぐためのセキュリティ対策

この章では証券口座乗っ取りを防ぐためのセキュリティ対策について解説します。
基本のセキュリティ設定
証券口座を守るためには、まず基本となるセキュリティ設定を徹底することが重要です。
パスワードの管理や二段階認証の導入は、被害を未然に防ぐための第一歩となります。
証券会社によっては、リスクベース認証を導入しており、普段と異なる端末や場所からアクセスがあった場合に追加認証を求める仕組みもあります。
また、ログイン履歴や取引履歴をこまめにチェックすることで、不正アクセスの早期発見につながるのです。
「自分は大丈夫」と思い込まず、定期的にセキュリティ設定を見直す習慣をつけましょう。
証券会社の公式サイトで推奨されているセキュリティ対策も必ず確認することが大切です。
たとえば、SBI証券や楽天証券などは、公式ページで最新のセキュリティ情報や注意喚起を発信しています。
こうした情報を定期的にチェックするだけでも、被害リスクを大きく減らすことができます。
強固なパスワードの作り方と管理方法
パスワードは、証券口座の安全を守る最初の砦です。
8文字以上で、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせるのが基本です。
誕生日や電話番号、ペットの名前など、個人情報に関連する単語は避けましょう。
「Password123」や「abcd1234」のような単純なパスワードは、すぐに突破されてしまいます。
他のサービスと同じパスワードを使い回すのも危険です。
パスワード管理が不安な場合は、パスワードマネージャー(管理アプリ)の利用をおすすめします。
定期的な変更も大切で、3か月に1回を目安に新しいものにしましょう。
紙に書いて保管する場合は、家族や他人の目に触れない場所を選んでください。
パスワードを忘れた場合の再設定方法も、事前に確認しておくと安心です。
二段階認証の重要性と設定方法
二段階認証は、IDとパスワードだけでなく、追加の認証要素を組み合わせることで、不正ログインを防ぐ強力な手段です。
たとえば、スマートフォンに送られる認証コードや、認証アプリを使ったワンタイムパスワードが一般的です。
証券会社によっては、初回ログインや普段と異なる環境からのアクセス時に自動的に二段階認証が求められます。
設定方法は証券会社ごとに異なりますが、多くの場合、マイページやセキュリティ設定画面から簡単に登録できます。
認証コードは他人に絶対教えないようにしましょう。
また、スマートフォンを紛失した場合の対応策も、事前に確認しておくと安心です。
二段階認証を導入するだけで、乗っ取りリスクを大幅に減らせます。
フィッシング詐欺・マルウェア対策
怪しいメールやSMSの見分け方
フィッシング詐欺は、証券口座乗っ取りの主な原因の一つです。
本物そっくりのメールやSMSで偽サイトに誘導し、IDやパスワードを盗み取ります。
たとえば、「口座に問題が発生しました」「緊急対応が必要です」など、不安をあおる文言が使われることが多いです。
送信元アドレスが公式と微妙に違う、リンク先のURLが不自然、という特徴もあります。
メール内のリンクは直接クリックせず、必ず公式サイトからログインしましょう。
また、日本語が不自然だったり、ロゴやデザインが粗い場合も要注意です。
少しでも違和感を覚えたら、証券会社のサポート窓口に確認することが大切です。
セキュリティソフトの活用
マルウェア感染による情報流出も、証券口座乗っ取りの大きなリスクです。
パソコンやスマートフォンには、必ず最新のセキュリティソフトを導入しましょう。
セキュリティソフトは、ウイルスやスパイウェア、フィッシングサイトへのアクセスを自動でブロックしてくれます。
定期的なウイルススキャンも忘れずに行うことが重要です。
OSやアプリのアップデートも、セキュリティ強化には欠かせません。
無料のソフトよりも、信頼できる有料版を選ぶと安心です。
スマートフォンにも対応したセキュリティアプリをインストールしておきましょう。
不審なアプリのインストールや、怪しいサイトへのアクセスは避けてください。
日常で気をつけるポイント
日常生活でも、ちょっとした注意が証券口座の安全につながります。
公共のWi-Fiを使って証券口座にログインするのは避けましょう。
カフェや駅などのフリーWi-Fiは、通信内容が盗み見られるリスクがあります。
自宅のWi-Fiも、必ずパスワードを設定し、定期的に変更してください。
パソコンやスマートフォンを他人に貸す場合は、必ずログアウトしてから渡しましょう。
また、取引履歴やログイン履歴を定期的にチェックし、身に覚えのない操作がないか確認する習慣をつけることが大切です。
証券会社からの公式アナウンスや注意喚起も、こまめにチェックしましょう。
こうした日々の積み重ねが、乗っ取り被害を未然に防ぐ最大のポイントです。

証券会社ごとの乗っ取り被害と補償対応の違い

この章では証券会社ごとの乗っ取り被害と補償対応の違いについて解説します。
主な証券会社の被害状況比較
2025年春、証券口座の乗っ取り被害が大手ネット証券を中心に急増しました。
楽天証券、SBI証券、野村證券、SMBC日興証券、マネックス証券、松井証券などで被害が確認されています。
手口は、フィッシング詐欺やマルウェアでIDやパスワードを盗み、不正ログイン後に保有株を勝手に売却。
その資金で中国株などを大量購入し、株価をつり上げて利益を得るというものです。
実際に、楽天証券やSBI証券では、数百万円から数千万円規模の損失を被った事例も報告されています。
2025年2月から4月中旬までのわずか2カ月半で、全国の証券会社で1454件、被害総額は約950億円に達しました。
特に3月以降、被害件数が急増し、犯罪グループの組織的な関与が指摘されています。
楽天証券・SBI証券・野村證券などの事例
楽天証券では、2025年3月に不正アクセスによる被害が発生。
ログイン情報を盗まれた顧客の口座で、勝手に株が売却される被害が相次ぎました。
SBI証券でも、過去に不正アクセス事件が発生し、保有株の売却と不正な銀行口座への出金が確認されています。
この際、SBI証券は被害者への個別連絡と補償対応を進めました。
野村證券でも、フィッシング詐欺による不正アクセスが多発。
2025年4月にはセキュリティ強化のため、オンラインサービスの利用条件や認証方法を見直しています。
これらの事例から、どの証券会社もフィッシング詐欺やマルウェアによる情報漏洩が主な原因であり、利用者側の注意も求められています。
証券会社ごとの補償方針
証券会社による補償の有無や条件は、2025年春時点で大きな注目を集めています。
これまで、IDやパスワードを使った正規のログインによる取引は「本人の意思」とみなされ、原則として補償されないケースが多かったです。
しかし、被害の急増を受け、大手証券10社と日本証券業協会は、損失を被った顧客に対して被害額の一部を補償する方針を共同で表明しました。
ただし、補償の内容や条件は会社ごとに異なり、今後も個別の状況を踏まえて検討される見通しです。
補償の有無と条件
楽天証券やSBI証券では、これまで「本人によるID・パスワード利用の場合は原則補償なし」としてきました。
一方、SBI証券は2020年の不正アクセス事件で、被害者に個別連絡のうえ、資産保護を最優先に補償対応を進めた実績があります。
野村證券の場合も、被害に遭った場合は速やかな連絡と警察への被害届提出などを条件に、補償を検討しています。
今後は、フィッシング詐欺やマルウェアによる被害も補償対象となる方向ですが、利用者に重大な過失があった場合や、被害発生から30日以上経過して連絡した場合などは補償されないこともあります。
補償を受けるための手続き
補償を受けるためには、まず証券会社への速やかな連絡が必要です。
次に、警察への被害届提出や、証券会社の調査に協力することが求められます。
被害の内容や経緯を詳しく説明し、必要な書類を提出することで審査が行われます。
また、各社とも被害発生から30日以内の連絡が原則条件となっているため、早めの対応が重要です。
セキュリティ対策の取り組み比較
各証券会社は、被害拡大を受けてセキュリティ対策を強化しています。
楽天証券は2025年3月、リスクベース認証の導入を発表。
通常とは異なる環境からのログイン時に追加認証を求める仕組みで、不正アクセスのリスクを大幅に低減できるとされています。
SBI証券は、多要素認証(FIDO認証)やデバイス認証、出金時の2段階認証など、複数のセキュリティ機能を導入。
スマートフォンの生体認証やPINコードも活用できます。
野村證券も、フィッシング詐欺への注意喚起やセキュリティ強化策を進めており、2025年4月からオンラインサービスの利用条件を改定しています。
どの証券会社も、今後は多要素認証の義務化や、より高度な認証方式の導入が進む見込みです。
利用者自身も、パスワードの使い回しを避ける、怪しいメールやサイトに注意するなど、日常的な対策が欠かせません。

証券口座が乗っ取られた場合の対処法と相談先

この章では証券口座が乗っ取られた場合の対処法と相談先について解説します。
被害発覚時にまずやるべきこと
証券口座の乗っ取りが疑われる場合、最初にやるべきことは「被害拡大の防止」と「証拠の確保」です。
ログイン履歴や取引履歴をすぐに確認し、不審な取引や出金がないかチェックします。
もし身に覚えのない取引を発見したら、速やかに証券会社のサポート窓口に連絡してください。
証拠として、画面のスクリーンショットやメールの内容も保存しておくと、後の対応がスムーズです。
また、パスワードや取引暗証番号の変更も急ぎましょう。
この初動対応が遅れると、被害がさらに広がる恐れがあります。
口座凍結・パスワード変更
不正アクセスが疑われた場合、まず証券会社に連絡し、口座の一時凍結を依頼します。
これにより、第三者による取引や出金をストップできます。
次に、ログインパスワードや取引暗証番号を新しいものに変更してください。
パスワードは英数字や記号を組み合わせ、推測されにくいものに設定します。
また、出金時のSMS認証など、多要素認証も必ず設定しましょう。
これらの対応を速やかに行うことで、追加被害を防げます。
証券会社への連絡方法
証券会社ごとに緊急連絡先やサポート窓口が設けられています。
楽天証券やSBI証券などは、公式サイトの「不正アクセス・乗っ取り被害」専用ページやカスタマーサービスセンターで24時間対応しています。
電話やウェブフォームで「不正アクセスの疑いがある」と伝え、指示に従ってください。
連絡時には、本人確認のための情報(氏名、口座番号、生年月日など)が必要です。
証券会社によっては、被害状況のヒアリングやアクセスログの確認も行われます。
できるだけ早く連絡し、対応を仰ぐことが重要です。
警察や金融庁への相談手順
証券会社への連絡と同時に、警察や金融庁にも相談しましょう。
警察への相談は、最寄りの警察署やサイバー犯罪相談窓口で受け付けています。
オンラインでの通報も可能で、証拠となるログイン履歴や取引履歴、メールの内容などを持参します。
金融庁では「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」や、一般の金融トラブル相談窓口が設けられています。
電話やウェブサイトから相談でき、必要に応じて他の機関を紹介してもらえます。
警察や金融庁に相談することで、被害の全容把握や今後の対応策についてアドバイスを受けられます。
被害拡大を防ぐためのポイント
被害を最小限に抑えるには、初動対応の速さがカギとなります。
まず、多要素認証やSMS認証を必ず設定し、パスワードは定期的に変更しましょう。
取引通知やログイン通知のメールを必ず確認し、少しでも不審な点があればすぐに行動します。
また、OSやセキュリティソフトを常に最新の状態に保つことも大切です。
家族や高齢者などITに詳しくない人にも、定期的な口座確認やセキュリティ対策の重要性を伝えてください。
被害に気づいたら、証券会社・警察・金融庁の3カ所に同時に相談することで、迅速な対応と被害拡大の防止につながります。

証券口座乗っ取り被害を防ぐために今すぐできること

この章では証券口座乗っ取り被害を防ぐために今すぐできることについて解説します。
今日から始めるセキュリティチェックリスト
証券口座の乗っ取りを防ぐには、まず基本のセキュリティ対策を徹底することが重要です。
最初に、パスワードを他のサービスと使い回さず、英数字や記号を組み合わせた強固なものに変更しましょう。
二段階認証(2FA)を必ず設定してください。
証券会社の公式アプリやサイトからのみログインする習慣をつけることも大切です。
メールやSMSで届くリンクは絶対にクリックせず、公式サイトのブックマークからアクセスしましょう。
パソコンやスマホには最新のセキュリティソフトを導入し、常にアップデートを忘れないでください。
これらの対策を今日から始めることで、被害リスクを大きく減らせます。
家族や高齢者への注意喚起方法
家族や高齢者は、フィッシング詐欺や偽サイトの被害に遭いやすい傾向があります。
まず、証券会社からのメールやSMSに記載されたリンクは絶対に開かないよう、具体的な例を交えて説明しましょう。
「公式サイトは必ず自分で検索し、ブックマークからアクセスする」と伝えることが効果的です。
また、パスワードの管理方法や二段階認証の設定方法を一緒に確認しながら実践するのも良い方法です。
不審なメールや画面が表示された場合は、すぐに家族に相談するよう促してください。
米国の金融機関も、高齢者への啓発活動や家族のサポートを推奨しています。
身近な人と一緒にセキュリティ対策を進めることで、被害を未然に防げます。
定期的な口座確認とモニタリングのすすめ
証券口座の不正利用は、早期発見が被害拡大を防ぐカギです。
週に一度は必ず口座残高や取引履歴をチェックしましょう。
身に覚えのない取引やログイン履歴があれば、すぐに証券会社へ連絡してください。
スマホの証券アプリには「通知機能」や「アラート機能」があります。
これを活用すれば、ログインや大きな取引があった際に即座に気付けます。
海外の証券会社でも、定期的なモニタリングやアラート設定が推奨されています。
小まめな確認と通知の活用で、不正被害のリスクを最小限に抑えられます。

まとめ

ポイント
- フィッシング詐欺やマルウェア感染による情報窃取が証券口座乗っ取りの主な手口である
- 偽サイトや偽アプリを利用した巧妙な詐欺が多発している状況である
- 実際に多額の損失事例が発生し、大手証券会社でも被害が確認されている
- セキュリティ対策として強固なパスワード管理や二段階認証の導入が重要である
- 定期的な口座確認や公式情報のチェックを習慣化することが被害防止につながる
今回は証券口座の乗っ取りについて説明してきました。
どんな対策をしても100%安全とは正直言い難いですが、自分でできる対策はしっかりしておかないと、あとで後悔することになります。
まずは上記に挙げた対策法を実践して、定期的に自分の証券口座を見ておく癖をつけておくことが重要です。


参考: