
今週の結果

結果
- 週間累計:+129,134円
- 4月累計:+214,313円
- 年間パフォーマンス:-6.6%
今週は水曜日から急上昇したので成績が良く、含み損も少しずつですが減ってきました。
しかし、まだまだ予断は許さない状況です。
トランプの一声でまた株価が変動する恐れもあります。
以前よりは安定してきましたが、毎日ドキドキの連続ですね。


-
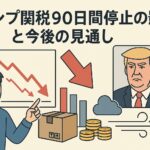
-
トランプ関税90日間停止の影響と今後の見通しをわかりやすく解説
続きを見る
▼月別の詳細なアノマリーを知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
続きを見る 続きを見る

【日経平均株価】月ごとの動きとアノマリーを探る
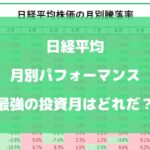
【過去20年間の日経平均月別パフォーマンス】最強の投資月はどれだ?
2025年4月第4週の日本株式市場:日本株市場の振り返り

この章では2025年4月第4週の日本株式市場の振り返りをしていきます。
主要株価指数(日経平均・TOPIXなど)の動き
2025年4月第4週、日経平均株価は大きく値動きしました。
週のはじめは米国の強硬な関税政策や円高進行が重しとなり、一時3万4200円台まで下落する場面も見られました。
21日(月)と22日(火)は連続して下落し、特に輸出関連株が売られやすい状況。
しかし、週半ばから米中貿易摩擦の緩和期待や米国株の反発を背景に流れが一変します。
23日(水)には日経平均が前日比648円高と急反発。
24日(木)には3万5000円台を回復し、週末25日(金)にはさらに上昇して3万5705円で取引を終えました。
1週間で約975円(2.8%)の上昇となった形です。
TOPIXも同様に堅調で、週末には2,628ポイントまで上昇。
テクノロジー株や一部大型株が相場をけん引し、全体的にリスクオンの雰囲気が強まった週となりました。
2025年4月第4週のマーケット全体の特徴
この週の日本株市場は、前週までの不安定な動きから一転し、落ち着きを取り戻しました。
大きな材料となったのは、米国の関税政策の修正観測と米中協議の進展期待です。
週前半は円高や海外市場の下落を受けて売りが先行。
23日以降は米国の政策転換や中国との関係改善期待が広がり、投資家心理が一気に改善しました。
医薬品や電機、自動車など幅広い業種で買い戻しが入り、33業種中25業種が上昇。
特に半導体関連や内需株、医薬品株の上昇が目立ちました。
また、決算発表シーズンに入り、好業績銘柄への物色も活発化。
市場全体として「リスク回避」から「リスク選好」への転換が鮮明になった週が印象的です。
市場参加者(個人・海外投資家など)の動向
投資部門別の売買動向を見ると、海外投資家が4週ぶりに大幅な買い越しに転じました。
現物と先物を合わせた買い越し額は約3,450億円にのぼり、これは前週の売り越しからの大きな転換です。
一方、個人投資家は2週連続で売り越しとなり、利益確定やリスク回避の動きが優勢でした。
信託銀行や事業法人(企業の自社株買いなど)も引き続き買い越し基調を維持。
海外勢の買い戻しが相場の押し上げ要因となった一方、個人投資家は慎重な姿勢を崩していません。
市場では「海外勢の動向が相場を左右する」という構図がより一層強まった週といえるでしょう。
初心者の方は、こうした投資家ごとの売買傾向を知ることで、相場全体の流れをつかみやすくなります。

日本株式市場の急落要因と回復の背景

この章では日本株式市場の急落要因と回復の背景について説明します。
米中関税摩擦と世界経済の影響
2025年4月、日本株式市場は米中の関税摩擦による影響を大きく受けました。
アメリカは日本からの輸入品に最大24%の関税を課し、中国にも高率の関税を発動。
これにより、日本の自動車や機械などの主要輸出産業はコスト増加や需要減少のリスクに直面しています。
たとえば、自動車業界では米国向け輸出が減少し、国内の雇用や経済成長にも悪影響が及ぶと指摘されました。
国際通貨基金(IMF)は、こうした関税政策の影響で2025年の世界経済成長率を2.8%へ下方修正しました。
これは昨年より0.5ポイント低い水準となります。
日本の成長率も0.6%に落ち込む見通しとなり、企業や投資家は先行き不透明感を強く感じています。
米中の対立は半導体やEV(電気自動車)、デジタル分野にも波及。
サプライチェーンの再構築やコスト転嫁が進んでいる状況です。
過去の関税政策の例からも、こうした摩擦は企業収益や株価に予想外の影響をもたらすことが多いと考えられます。
為替動向(円高・円安)が与えた影響
2025年4月は円高が進行し、1ドル=140円台まで円が買われました。
円高になると、日本企業の海外での売上が円換算で目減りし、特に輸出型企業の業績が圧迫されやすくなります。
たとえば、トヨタやソニーのようなグローバル企業は、為替の変動によって利益が大きく左右されるため、円高局面では株価が下落しやすい傾向があるのです。
円高の背景には、日銀の利上げ観測や米国の景気減速、米金利の低下があります。
2025年は米国の利下げ観測が強まり、日米の金利差が縮小することで円が買われやすくなりました。
加えて、世界的なリスク回避の動きが強まると、安全資産とされる円への需要が高まりやすいです。
一方、円高は輸入コストを下げる効果もあり、内需関連企業や消費者にとってはメリットとなる場合もあります。
実際、4月後半には円高メリットを受ける内需株が底堅く推移し、市場全体の下支え要因となりました。
-
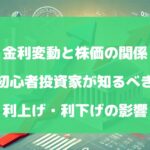
-
金利変動と株価の関係:初心者投資家が知るべき利上げ・利下げの影響
続きを見る
投資家心理と市場センチメントの変化
リスク回避の動きとその背景
4月初旬、日本株市場ではリスク回避の動きが強まりました。
米中関税摩擦の激化や世界経済の減速懸念が広がり、日経平均株価は一時3万1,000円台まで急落。
こうした局面では、投資家は安全資産へのシフトや現金化を進める傾向があります。
実際、東証プライム市場では値下がり銘柄が全体の9割を占めるなど、広範囲に売りが広がりました。
背景には、海外の主要株価指数の急落や、米国の関税政策に対する不透明感が挙げられます。
また、為替市場での円高進行も投資家のリスク回避姿勢を強める要因となりました。
初心者の方は、こうした局面では慌てて売却せず、冷静に状況を見極めることが大切です。
リバウンドのきっかけとなった要素
4月中旬以降、市場にはリバウンド(反発)の動きが見られました。
主なきっかけは、米国の政策姿勢の変化や米中貿易交渉の進展期待。
たとえば、トランプ大統領がFRB議長の解任を否定したり、米財務長官が「中国との交渉進展は可能」と発言したことで、投資家心理が改善しました。
さらに、米中関税の一部除外や、決算発表で好業績を示した企業が買い戻される動きもリバウンドを後押ししました。
内需関連株や半導体株など、これまで売り込まれていた銘柄に押し目買いが入り、日経平均株価は3万5,000円台を回復しています。
このように、ネガティブな材料が一巡し、政策や企業業績に明るい兆しが見えたとき、市場は急速に回復することがあります。
初心者の方も、短期的な下落に動揺せず、冷静に情報を集めて判断することが重要です。

今後の日本株式市場見通しと投資戦略

この章では今後の日本株式市場見通しと投資戦略について説明します。
今後のリスク要因と注目ポイント
2025年の日本株式市場は、国内外の経済や政治の動きに大きく左右される展開が予想されます。
特に注目すべきリスクは、米中対立の激化やトランプ政権による関税政策の強化。
これらは世界経済の不透明感を高め、市場のボラティリティを押し上げる要因となるでしょう。
また、日銀の追加利上げや円高の進行も企業業績に影響を与えやすい状況です。
国内では、賃上げや設備投資の拡大が続けば企業業績の底上げが期待できますが、消費増税や政局の不安定化には注意が必要となります。
こうした外部環境の変化に敏感に反応できるよう、最新の経済ニュースや政策動向を常にチェックする姿勢が求められます。
短期的な値動きに振り回されず、長期的な視点で市場全体の流れをつかむことが大切です。
有望な投資テーマとセクター
2025年は、データセンターやAI、半導体関連などのテクノロジー分野が引き続き注目されています。
世界的なデジタル化の流れを背景に、これらの分野は成長が期待できる分野といえるでしょう。
また、防衛関連や原子力、再生可能エネルギーも有望なテーマとなっています。
大阪万博や高齢化社会を見据えた医療・介護関連、雇用サービス、アニメ・コンテンツといったサービス分野も注目されています。
セクター別では、銀行や情報通信、建設・資材など内需関連が堅調。
割安株(バリュー株)への資金流入も続いており、バリュー株とグロース株のバランスを意識した投資が有効と考えられます。
具体的な銘柄選びでは、業績回復が見込める中小型株や高配当株にも目を向けたいところです。
個人投資家が取るべきリスク管理・投資戦略
長期投資・分散投資の重要性
市場の先行きが不透明な時期ほど、長期投資と分散投資の効果が発揮されます。
長期投資は「複利」の力を活かし、資産をじっくり増やす方法。
例えば、毎月一定額を積み立てていくことで、購入タイミングを分散でき、平均購入価格を抑えることが可能です。
これを「ドル・コスト平均法」と呼びます。
また、株式だけでなく債券や不動産、海外資産など複数の資産に分けて投資することで、一つの資産が値下がりしても他でカバーできる仕組みが作れます。
投資先を「卵」と「カゴ」に例えると、卵を一つのカゴにまとめて入れるより、複数のカゴに分けておく方がリスクが減るイメージ。
短期的な値動きに一喜一憂せず、長い目で資産形成を考える姿勢が重要となります。
▼ドルコスト平均法について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-

-
ドルコスト平均法をわかりやすく説明|仕組みと始め方・注意点まで解説
続きを見る
新NISA活用のポイント
2024年から始まった新NISAは、非課税枠の拡大や期間の無制限化など、個人投資家にとって非常に有利な制度です。
つみたて投資枠と成長投資枠を併用すれば、年間最大360万円まで非課税で投資できます。
売却した分の非課税枠が翌年に再利用できる点も大きな特徴です。
初心者の方は、まず「長期・積立・分散投資」を基本に、毎月無理のない範囲で積立投資を始めてみましょう。
高配当株やインデックスファンドなど、リスクとリターンのバランスを考えた商品選びが重要となります。
将来のライフイベントや資金ニーズに合わせて、つみたて投資枠と成長投資枠を使い分けると、より効率的に資産を増やすことが可能です。
新NISAを活用することで、税金を抑えながら着実に資産形成を目指せます。

まとめ

2025年4月第4週の日本株式市場は、米中関税摩擦や円高の影響で週初に大きく下落しましたが、週半ばから米中協議進展や米国株高を受けて急反発しました。
日経平均は週末に3万5705円まで回復し、TOPIXも堅調。
海外投資家が大幅買い越しに転じ、リスク選好ムードが強まりました。
米国の関税政策や為替動向が引き続き注目され、今後も市場は外部要因に左右されやすい状況が続くと見られます。


月別の詳細なアノマリーを知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-

-
【日経平均株価】月ごとの動きとアノマリーを探る
続きを見る
-
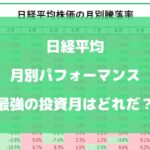
-
【過去20年間の日経平均月別パフォーマンス】最強の投資月はどれだ?
続きを見る
参考:
