
今週の結果

結果
- 週間累計:+82,950円
- 4月累計:+102,103円
- 年間パフォーマンス:-17.5%
見事にブラックマンデーでやられ、関税の一時停止で少し回復した感じです。
週間累計では結果が出ていますが、含み損が多く、非常に危険な状態。
4/9に仕込み、4/10の急上昇で得られたものがほとんどです。
フィボナッチで見ると、ちょうど転換期だと思ったので買いに入れている現状。
もう一度ドカンと下げが来るとゲームオーバーかなという感じです。


▼過去の暴落・ショックについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
2025年4月第2週の日本株式市場:日本株市場の振り返り

この章では2025年4月第2週の日本株式市場の振り返りをしていきます。
2025年4月第2週の日本株市場を取り巻く主なトピック
2025年4月第2週は、日本株式市場が大きく揺れ動いた週となりました。
日経平均株価は週初に急落し、一時3万1000円を割り込む場面も見られました。
これはトランプ政権による関税政策と、中国の報復措置による米中貿易摩擦の激化が主な要因です。
週中盤には、米国市場でハイテク株が買われた流れを受けて日経平均が急反発しました。
4月10日には2,894円高と歴代2位の上昇幅を記録し、3万5000円に迫る場面もありました。
しかし、週末には再び下落に転じ、最終的に195円安の3万3585円58銭で終了しています。
このように、相場は乱高下を繰り返し、投資家心理が不安定な状況が続きました。
国内外の経済ニュースが与えた影響
今週の日本株式市場には、国内外の経済ニュースが大きな影響を与えました。
特に注目されたのはトランプ政権による関税政策で、中国製品に対する税率を145%まで引き上げる発表です。
これにより、世界的な貿易摩擦への懸念が高まり、日本市場でも大量の売り注文が殺到しました。
一方で、米国市場では相互関税停止措置が好感され、ダウ平均が過去最大の上昇幅を記録。
この流れを受けて、日本市場でも輸出関連株や半導体株が買われたことで短期的な反発が見られました。
また、為替市場では円高傾向が進み、一時1ドル=143円台まで円高ドル安となりました。
これにより輸出企業への懸念が強まり、自動車株など一部セクターでは売り圧力が増加しました。
-
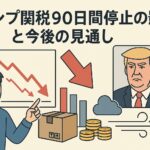
-
トランプ関税90日間停止の影響と今後の見通しをわかりやすく解説
続きを見る
投資家心理と市場のボラティリティ
今週の相場展開では、投資家心理の変動と市場ボラティリティの高さが際立ちました。
特にトランプ関税政策や中国の報復措置など、不透明感のあるニュースが続いたことで、投資家心理は悪化。
ボラティリティ指数(VIX)は急上昇し、週末には新型コロナウイルスパンデミック初期以来の高水準となりました。
これは短期的な不安感を反映したもので、市場全体で安全資産への逃避行動が見られました。
ただし、一部では「底打ち感」が広まる局面も。
例えば、日経平均株価が節目となる水準を割り込んだ際には押し目買いが入り、一時的な反発につながる場面もありました。
このような状況下で、投資家は慎重な姿勢を維持しつつも、一部銘柄への選別買いを進めている様子でした。

-
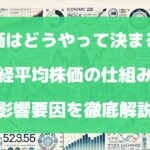
-
株価はどうやって決まる?日経平均株価の仕組みと影響要因を徹底解説
続きを見る
-

-
コロナショックで急落した株価の回復期間と要因
続きを見る
日経平均株価動向

この章では日経平均株価動向について説明します。
日経平均株価の週間推移と終値
2025年4月第2週の日経平均株価は、乱高下の激しい週となりました。
週初には米国市場でのハイテク株の反発が好感され、日経平均は急伸しましたが、週末にはトランプ政権による関税政策の影響で再び大きく下落しています。
具体的には、4月7日には30,792.74円まで下落しましたが、翌8日には33,012.58円へと急回復しました。
その後も乱高下を繰り返し、週末の終値は33,585.36円となりました。
4月第2週の日経平均株価の上昇・下落要因
上昇要因としては、米国市場でのハイテク株反発やトランプ政権が関税を90日間停止をしたことが挙げられます。
週末にかけてはトランプ政権が中国製品への関税をさらに引き上げる方針を示したことで、投資家心理が悪化し、大幅な売りが発生しました。

トランプ関税政策と日本株への影響

この章ではトランプ関税政策と日本株への影響について解説します。
トランプ政権が発表した新たな関税政策とは?
2025年4月2日、トランプ大統領は全ての輸入品に対する10%のベースライン関税を導入すると発表しました。
この政策により、輸入品コストが上昇し、米国内外の経済に広範な影響を及ぼすと予想されています。
日本からの輸出品には24%の関税が課されることが決定し、自動車や電子部品など主要産業への打撃が懸念されています。
特に自動車業界は、米国市場への依存度が高いため、大きな影響を受ける可能性があります。
自動車業界への影響と関連銘柄の動向
トヨタやホンダなど主要自動車メーカーの株価推移
新たな関税政策により、米国への輸出コストが増加するため、これら企業の利益率が圧迫される可能性があります。
特にトヨタやホンダは米国市場でのシェアが高く、短期的には株価の下落リスクがあると見られています。
サプライチェーンにおける部品メーカーへの波及効果
自動車部品メーカーも大きな影響を受ける見込みです。
例えば、エンジン部品や電子制御システムを供給する企業は、コスト増加分を価格に転嫁できない場合、利益率が低下します。
また、鉄鋼やアルミニウムなど原材料価格の上昇も懸念材料です。これにより、自動車関連株全体で弱含みの展開が予想されています。
米中貿易摩擦と日本市場への間接的影響
中国関連銘柄(機械・電子部品)の動き
トランプ政権は中国製品に対して累計145%もの追加関税を課す方針を発表しました。
この影響で、中国関連銘柄として知られるファナック(6954)や安川電機(6506)の株価が下落しています。
これら企業は中国市場からの収益依存度が高いため、米中貿易摩擦の激化による需要減少が直撃しています。
また、日本国内でも中国向け輸出依存度が高い企業は慎重な経営判断を迫られる状況です。
このように、新たな関税政策や米中貿易摩擦は、日本経済および株式市場に大きな波紋を広げています。

注目セクターと銘柄:半導体株や自動車株の動き

この章では注目セクターと銘柄について説明します。
半導体セクターが注目される理由
世界的な半導体需要増加と日本企業の立ち位置
近年、半導体の需要はAIやデータセンター、電気自動車(EV)の普及によって急速に拡大しています。
特にAIを活用したデータ処理や次世代通信技術(5G/6G)の基盤として、高性能チップが不可欠です。
日本は、長らく半導体市場で後退していましたが、現在は政府主導で国内生産を強化しています。
例えば、台湾のTSMCを誘致し、先端プロセス技術の開発を進めています。
また、Rapidus社が2027年までに2nmチップの量産を目指しており、日本の技術力を再び世界に示す計画です。
ただし、日本企業は成熟プロセス分野(自動車・家電用チップ)に強みを持つ一方で、先端プロセス技術では韓国や台湾に遅れを取っています。
この課題を克服するためには、研究開発投資や国際的な連携が鍵となります。
自動車セクターの課題と可能性
電気自動車(EV)関連銘柄の成長性
電気自動車市場は急速に成長しており、日本でもEV関連銘柄への注目が高まっています。
特にトヨタやホンダは、新型バッテリー技術やAI活用による自動運転技術の開発に注力。
また、ホンダもソニーとの提携によりEV市場への参入を加速させています。
これらの動きは、持続可能なモビリティ実現への一歩といえるでしょう。
さらに、日本政府はEV購入者への補助金制度を拡充しており、この政策が市場成長を後押ししています。
ただし、充電インフラ整備が遅れている点は課題として残ります。
内燃機関車メーカーが直面する課題
内燃機関車(ICE)メーカーは、EVシフトによる大きな転換期に直面しています。
日本ではハイブリッド車(HEV)が依然として主流ですが、欧米や中国では完全なゼロエミッション車への移行が進んでいるのです。
また、EV生産には従来よりも部品点数が少なくなるため、多くの部品サプライヤーが事業モデルの見直しを迫られています。
この変化に対応できない場合、日本全体の製造業にも影響が及ぶ可能性があるのです。
一方で、水素エンジンなど新たな技術も注目されています。
トヨタは水素燃料エンジン開発に取り組み、短時間で燃料補給可能な利便性とゼロエミッションというメリットを提供しています。
これらの技術革新が、日本自動車産業再構築へのカギとなるでしょう。

個人投資家が押さえるべき今後の市場展望

この章では今後の市場展望について説明します。
2025年後半に向けた日本株市場の見通し
国内外の経済指標が与える影響予測
2025年後半の日本株市場は、国内外の経済指標が鍵を握ると予想されています。
特に注目されるのは、日本銀行が発表する「日銀短観」や米国の「雇用統計」です。
日銀短観は、日本企業の景況感を示す重要な指標であり、業況判断指数(DI)がプラスに転じれば、株価上昇への期待が高まります。
一方、米国雇用統計では非農業部門雇用者数や失業率が注目され、これらの結果が良好であれば、米国経済の安定を背景に日本株にもポジティブな影響を与える可能性があります。
また、為替動向も重要です。
円安が進めば輸出企業に追い風となり、自動車や機械セクターの株価上昇が期待されます。
一方で、円高局面では輸出企業への圧力が強まり、防御的なディフェンシブ銘柄への資金シフトが進む可能性があります。
-

-
日銀短観と株価の関係:業況判断指数が株価に与える影響
続きを見る
-
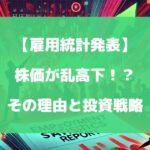
-
雇用統計発表で株価が乱高下!?その理由と投資戦略
続きを見る
金融政策(利上げ・利下げ)のシナリオ別分析
2025年末までの日銀の金融政策は、複数のシナリオが考えられます。
最も可能性が高いとされるのは、0.5~0.75%までの利上げを段階的に実施するケースです。
この場合、銀行株など金利上昇による恩恵を受けるセクターに注目が集まるでしょう。
一方で、急激な利上げは住宅ローンや企業借入コストを増加させ、不動産や建設セクターには逆風となる可能性があります。
逆に、米国で利下げが進行した場合、日本でも緩和的な政策へ転換する可能性があります。
この場合、安全資産とされる債券や金への投資需要が高まり、リスクオフの流れが強まることも考えられるでしょう。
▼金利について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-
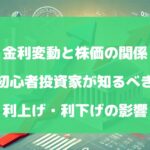
-
金利変動と株価の関係:初心者投資家が知るべき利上げ・利下げの影響
続きを見る
「リスクオフ」の流れに備える投資戦略とは?
ディフェンシブ銘柄(食品・医薬品)の選び方
市場全体が不安定になる局面では、ディフェンシブ銘柄への投資が有効です。
これらは景気変動に影響されにくく、安定した収益基盤を持つ企業群を指します。
例えば、日本たばこ産業(JT)や味の素など食品関連企業は、人々の日常生活に欠かせない製品を提供しており、不況期でも需要が大きく減少しません。
また、大手製薬会社は医薬品需要の安定性から収益性が高く、不況時にも比較的堅調なパフォーマンスを示します。
選定時には、高配当銘柄や財務基盤がしっかりしている企業を優先することがポイントです。
これにより、不況時でも配当収入を得ながら資産価値を守ることができます。
安全資産として注目される金や債券投資
リスクオフ局面では、安全資産として知られる金や債券への投資も有効です。
金はインフレ耐性や価値保存性に優れており、不確実性が高まる場面でその魅力が増します。
例えば、過去の金融危機時には金価格が急騰した事例もありました。
特に長期保有することで資産全体のリスク分散効果を得られる点も魅力です。
一方、債券は安定した利息収入と元本保証性から、安全性を重視する投資家に支持されています。
特に投資適格債(高格付け債券)は不況時でも相対的に高い回復力を持つため、中長期的なポートフォリオ運用には最適です。
これらを組み合わせたバランス型ポートフォリオ構築によって、市場変動への耐性を高めることが可能です。
以上の戦略を活用すれば、不確実な市場環境下でも安定した運用成果を目指すことができるでしょう。

まとめ

2025年4月第2週の日本株市場は、米中貿易摩擦やトランプ政権の関税政策の影響で大きく乱高下しました。
週初には関税引き上げ発表を受けて日経平均株価が急落し、一時3万1000円を割り込みましたが、米国市場でのハイテク株反発や関税一時停止措置が好感され、急回復する場面もありました。
4月10日には一時2894円高と歴代2位の上昇幅を記録しましたが、週末には再び下落し、最終的に33,585.36円で終了しています。
この間、為替市場では円高が進み、輸出企業への懸念が強まりました。
市場は不安定な状況が続き、投資家心理も揺れ動いています。


月別の詳細なアノマリーを知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
-

-
【日経平均株価】月ごとの動きとアノマリーを探る
続きを見る
-
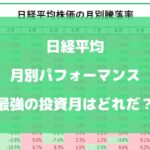
-
【過去20年間の日経平均月別パフォーマンス】最強の投資月はどれだ?
続きを見る
